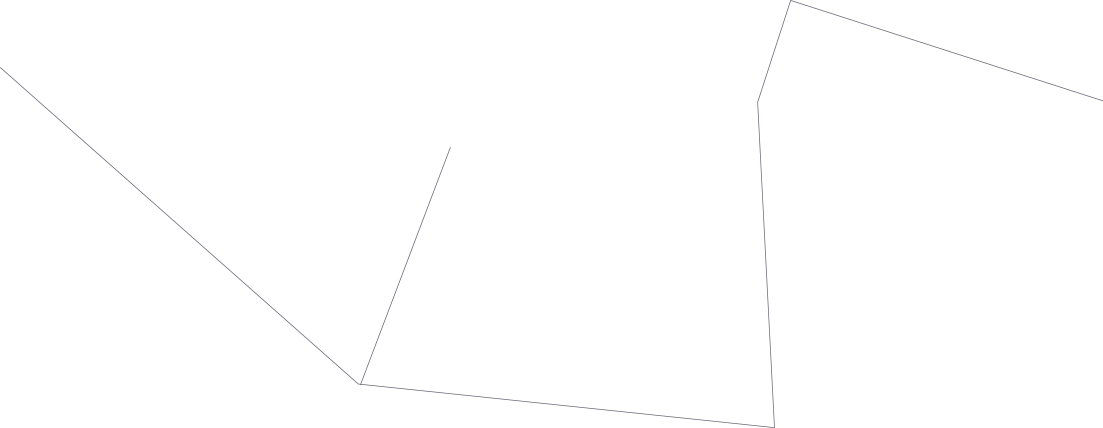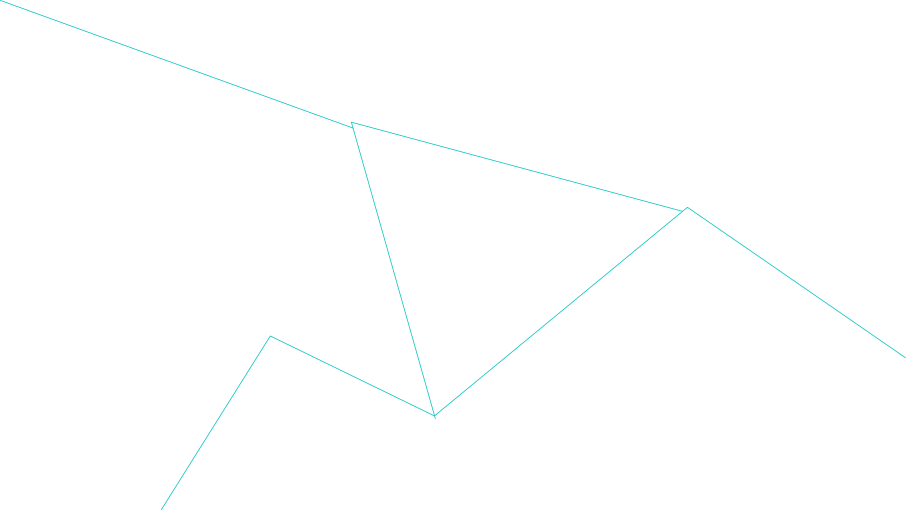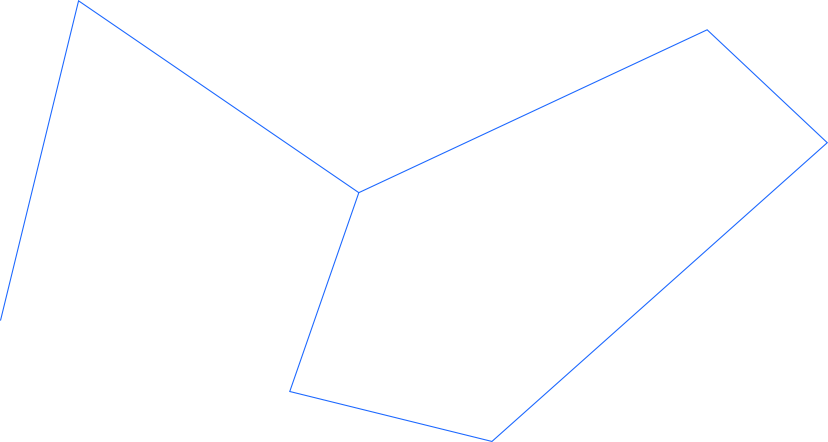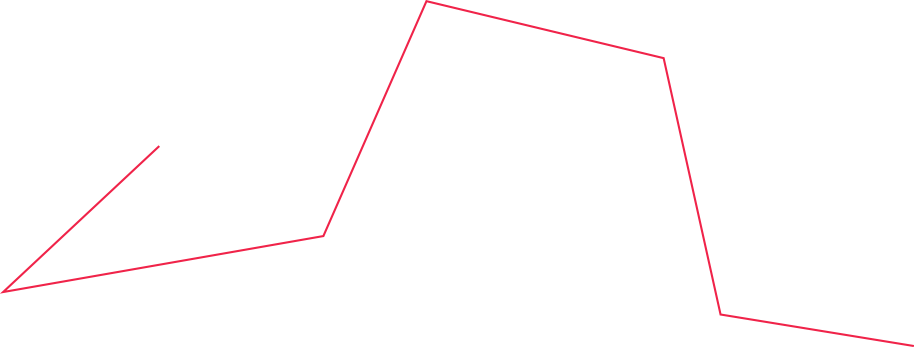No. 3213
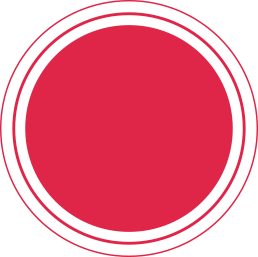
薬膳の知恵を、和食やイタリアンなどの日常食に取り入れる新たな食のスタイル『フュージョン薬膳』が、クックパッドが発表する食トレンド予測2026に選出されるなど話題になっている。クコの実を使ったカプレーゼや、生姜たっぷりの和風パスタなど、身近な食材を活かしながら美容や健康維持につながるレシピが注目だ。「体調に合った旬の食材を選ぶ」という薬膳の基本を、特別な材料がない日常で実践することを目指す。海老・ニラ・生姜などの組み合わせで代謝と血行促進で冷え対策を狙う海老ニラ焼きそば。りんご・レーズン・くるみ・バターで腸活を期待するりんごのバターソテートーストなど、単純に料理としてもおいしそう+体に良いという両輪は広く受け入れられることになりそうだ。
【参考URL】
https://mainichi.jp/articles/20251126/ckp/00m/100/023000c
No. 3212
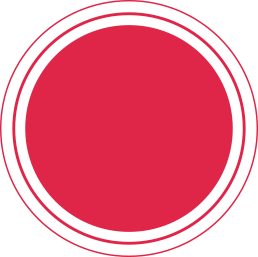
江戸時代の走り方を10年にわたり研究する大場氏が紹介する『江戸走り』が、今年10月頃からSNSで大バズリし、1300万回を超える再生数を叩き出した。江戸時代の飛脚がしていたと言われる、左右同じ手と足を出す「ナンバ走り」を応用した体を横に構えて脱力して走る「横走り」が、一見ふざけているようにも見えるユニークさが爆発的拡散の要因と見られる。「江戸走り」は筋力に頼らず膝にも優しいことから、高齢者や運動初心者にも向くとされ、実用性や文化的価値といった正当な理由でも、もちろん注目されている。大場氏は東海道を走破する実験も計画しており、今後さらなる話題になるかもしれない。
【参考URL】
https://news.yahoo.co.jp/articles/11b5236fa6300b354d0c421e49d722e074bed522
No. 3211
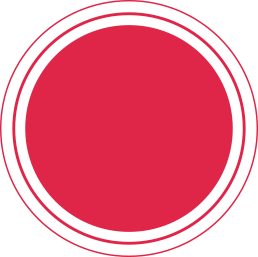
s="white">米ドルなどの法定通貨や金などの資産と連動することで価格の安定を図った仮想通貨が『ステーブルコイン』だ。暗号資産として当初注目を浴びたビットコインなどが抱える価格変動が大きすぎるという問題点があり、その点を軽減したステーブルコインは実生活での決済手段や資産の避難先などとして利用が拡大している。しかし、まだ完全な安全性があるという段階ではなく、ステーブルコインの1つであり米ドルと連動する「TerraUSD」が、米ドルとの連動を失い暴落するという出来事もあった。そこから世界各国ではステーブルコイン規制強化の動きもあり、今後安全な資産の一形態や決済方法として確立するかの過渡期に立っていると言えそうだ。
No. 3210
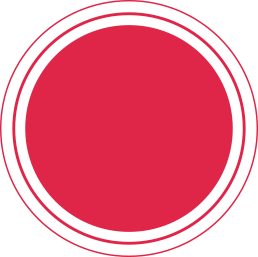
黒い装いに白い仮面。ホラー作家でありYouTuberの『雨穴(うけつ)』は、その強烈なビジュアルだけでなく、「じわじわ怖い」作風で多くの読者を引きつけている。著書の『変な家』や『変な絵』が幅広い年齢層から支持を集める理由は、血や叫びといった直接的な恐怖ではなく、日常の延長線上にある違和感にある。本人いわく、「怖がらせようとしすぎないこと」を意識しているという。極限状態にある人の心情や行動を丁寧に想像することで、「派手ではないが、後から効いてくる恐怖」を生み出しているようだ。また、小説に図解を多く取り入れる構成も特徴的。ウェブメディア出身ならではの視点で、読者に余計なストレスを与えない読みやすさを重視する。何気ない日常に飽きた夜、雨穴の“ぞっとするリアル”な世界に迷い込んでみるのも一興だ。
【参考URL】
https://ananweb.jp/categories/entertainment/20879
No. 3209
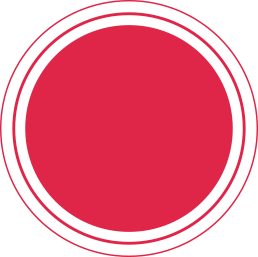
『アスレジャー』とは、「Athletic(運動)」と「Leisure(余暇)」を掛け合わせた言葉で、スポーツウェアの快適さや機能性を日常の装いに取り入れるファッションを指す。海外セレブをきっかけに広まったこのスタイルは、日本でもリモートワークの普及や健康志向の高まりを背景に、定番として浸透しつつある。一方で、賛否があるのも事実だ。レギンスやスポーツブラなど体に密着するアイテムを中心とした装いには、「露出が過激」「体のラインが出すぎる」といった戸惑いの声も少なくない。ただ近年は、そうした批判を踏まえ、シルエットや素材感をアップテートした大人向けアイテムが増加。快適さときちんと感、そのバランスをどう取るかを意識する人も増えている。楽なスタイルだからこそ、質の良いアイテム選びが着こなしを左右すると言えるだろう。
【参考URL】
https://diamond.jp/articles/-/379448
No. 3208
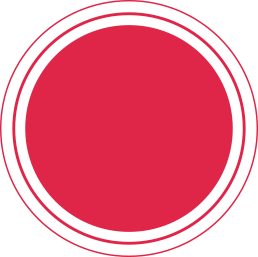
ユネスコの『世界の記憶』(旧称・世界記憶遺産)の国際登録候補として、世阿弥の能楽論『風姿花伝』が日本政府から推薦されることになった。世界の記憶は、書物や文書、映像など“人類の記憶”を後世に残すことを目的とした制度で、建造物を対象とする世界遺産とは異なる位置づけだ。今回対象となったのは、観世宗家に伝わる3冊の写本で、うち2冊は世阿弥の直筆本。現存する演劇論としては世界最古級とされ、芸の本質を「花」にたとえた思想は、600年を経た今も表現論として読み継がれている。申請書は近く提出され、登録の可否は2027年春のユネスコ執行委員会で審議される予定。舞台芸術の理論が「記憶」として評価される今回の推薦は、日本文化の奥行きを世界に示す機会になりそうだ。
【参考URL】
https://www.jiji.com/jc/article?k=2025041701074&g=tha"
No. 3207
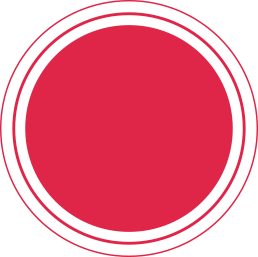
少額投資非課税制度(NISA)をめぐり、政府・与党は18歳未満を対象とする『こどもNISA』の創設に向け、制度設計の詰めの議論を進めている。対象は新NISAの「つみたて投資枠」に限定し、年齢制限を撤廃して0歳から口座開設を可能とする方向だ。非課税の投資上限は「年間60万円・総額600万円」とする案が軸となっており、現在この水準を念頭に最終的な調整が行われている。現行NISA(年120万円)より抑えることで、家庭の収入差による過度な資産格差を防ぐ狙いがある。また、利用が伸びなかった旧ジュニアNISAの反省を踏まえ、子どもの同意を条件に12歳から資金を引き出せる仕組みも検討中。教育費や進学準備など現実的な使い道を想定しつつ、早くから「お金を育てる」経験を促す制度として注目されている。
【参考URL】
https://news.yahoo.co.jp/articles/6a11c0d7ee5f348e903a0fe8c9eb7c6121e3f7ac
No. 3206
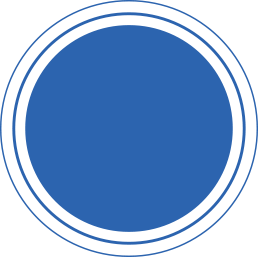
トヨタ自動車が箱根駅伝(東京箱根間往復大学駅伝競走)のオフィシャルスポンサーとして提供する大会車両が、2026年大会から大きく変わる。これまで選手のすぐそばを走る運営車両はガソリン車やハイブリッド車が中心で、排気ガスを吸い込みながら走る選手への負担や環境負荷が課題とされてきた。そこでトヨタは、大会本部車から医務車までを電気自動車(BEV)と燃料電池車(FCEV)へ全面的に切り替え、医務車や緊急対応車には自動運転EV『e-Palette』を投入する。電動化により、大会のCO₂排出量は約1.4トンから約0.5トンへと約6割削減される見込み。実際にe-Paletteを使った試走も完了し、充電切れなど大会進行の支障はないと確認されている。トヨタが挑む箱根駅伝の電動化は、選手と環境の双方に配慮した新しい大会運営の一歩になりそうだ。
【参考URL】
https://driver-web.jp/articles/detail/41456
No. 3205
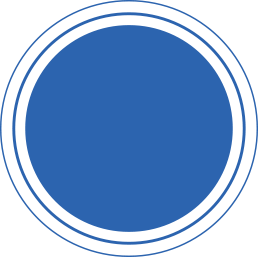
Z世代の間で、同性の友人関係がこれまで以上に重視されている。背景にあるのは、「気を遣わずにいられる相手」を求める心理的安全性のニーズだ。恋愛や異性との関係には誤解や配慮のハードルがあり、“コンプライアンス意識”が会話の自由度を下げてしまう。だからこそ、同性の友人が本音を話せる『コンプラ解放区』となり、深い絆が生まれやすいという。SNSで昔の友人とつながり続けられる環境や、中高一貫校の増加も、少人数・高密度の友情を後押ししている。こうした状況をマーケティングの視点で読み解くと、若者に選ばれるブランドの鍵は“安心・共感・誠実さ”にあると考えられる。Z世代に「このブランドなら信頼できる」と感じてもらうには、仲間と参加しやすいコミュニティづくりや透明性の高い情報発信を行っていく必要がありそうだ。
【参考URL】
https://www.countand1.com/2025/04/gen-z-relationships-values-with-psychological-safety-and-low-risk-implication-for-marketing.html
No. 3204
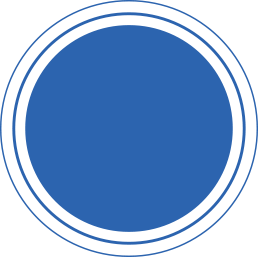
プラスチックごみが海に流れ込み、マイクロプラスチックとして残り続ける問題が深刻化するなか、理化学研究所などの研究チームが開発したのが、『塩で溶けるプラスチック』だ。水中で2種類のイオン性モノマー(プラスチックを構成する最小の単位)を混ぜるだけで生成される超分子プラスチックで、塩水に触れると簡単に原料へ戻り、自然界に長期残存しないのが最大の特徴だ。従来の超分子ポリマーは「柔らかくて実用に向かない」とされてきたが、今回の素材は耐熱性や硬度、成形性など、一般的なプラスチックと遜色ない性能を獲得。しかも回収したモノマーを再利用できるため、完全循環型の素材として期待が高まっている。海に流れれば分解し、土に置けば自然に還る。そんな“使い捨てないプラスチック”が現実味を帯びてきた。
【参考URL】
https://www.tv-tokyo.co.jp/plus/business/entry/202510/17726.html
No. 3203
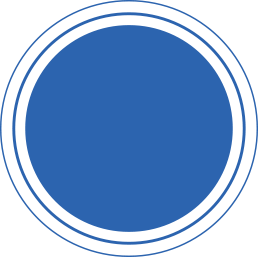
政府が、国内外の情報収集・分析を一元的に担う新組織『国家情報局』の創設に向け調整を進めている。高市首相が検討を指示したもので、現在は内閣情報調査室(内調)や警察公安部門、外務省、防衛省などが個別に担うインテリジェンス機能を集約し、日本版の「情報司令塔」を整備する狙いがある。新組織は内調を格上げし、関係閣僚による「国家情報会議」の事務局も担う方針。警察庁や外務省、防衛省から出向者を集め、各省庁の情報を横断的に束ねる。トップとなる「国家情報局長」は国家安全保障局長と同格とし、首相・官房長官の直轄で指揮を執る体制だ。自民党と日本維新の会の連立合意にも創設が明記されており、来年の通常国会で法案提出を目指す。主要国と比べ脆弱とされてきた日本のインテリジェンス体制が、ようやく本格強化へ動き出した。
【参考URL】
https://news.tv-asahi.co.jp/news_politics/articles/000466565.html
No. 3202
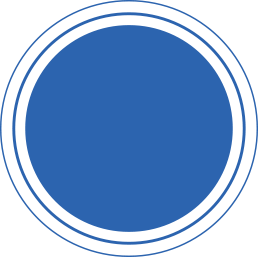
年末が近づくと毎年やっていてついつい買ってしまうセール。『ブラックフライデー』にそんなイメージはないだろうか?ブラックフライデーはアメリカの感謝祭(11月第四木曜日)の翌日に行われる大規模な安売りのことで、日本では感謝祭を祝う習慣がないためセールが唐突に感じるという現象が発生している。
そんな日本でブラックフライデーが盛り上がるのは、消費低迷期である11月の「購買動機」創出を求める企業側と、年末商戦前にお得に商品を手に入れたい消費者側の利害の一致があると言われている。小売だけでなく旅行や交通機関などブラックフライデーへの参加業種は次々と広がっており、今後も国民的行事として定着しそうだ。
【参考URL】
https://news.yahoo.co.jp/expert/articles/fb365129b4b0d6af9cde7b43445b5b6435bb673c
No. 3201
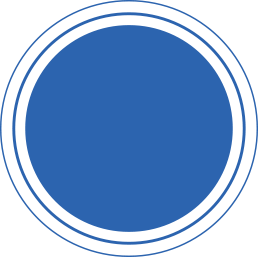
TBSの火曜ドラマ「じゃあ、あんたが作ってみろよ」で登場する、古風で亭主関白な性格だが恋愛では素直になれない不器用な一面を持つ男性「勝男」で話題になった『化石系男子』。プライドが高く、自分が常に優位でいたいと考えがちで、相性が良いのは包容力があり尽くすことが好きな女性と言われる。
肉食系男子・草食系男子というネーミングから一般化された◯◯系男子の一種だが、最近のSNSではこういった古い価値観を持つ傾向がある人物を、「昭和」と批判的に称することも増えてきているとか。価値観の移り変わる速度は上がる一方の昨今、中年だけでなく若い人たちにとっても、明日は我が身となりそうだ。
【参考URL】
https://woman.mynavi.jp/article/211012-27/
No. 3200
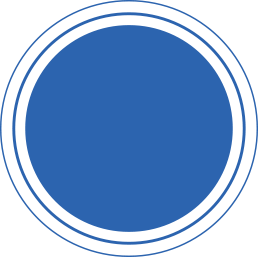
AIによる画像生成の急激な精度向上に驚いてはや数年。最近では動画生成の性能も飛躍的に高まり、実用レベルも近いと言われている。そんな中、オンラインコンテンツの信頼性を守るために注目されているのが、AIが生成するコンテンツに目に見えない情報を付与して判別できるようにする『電子透かし』だ。動画系SNSを中心としたAI動画による存在しない、または誤った情報の発信と拡散への対応は喫緊の課題となっている。動画だけでなく画像や文章、音声などAIで生成されるコンテンツ全般に適応可能な「電子透かし」技術は、誤情報の氾濫だけでなく著作権の保護にもつながるものとして世界的な取り組みが進みそうだ。
【参考URL】
https://www.nhk.or.jp/strl/publica/giken_dayori/36/4.html
No. 3199
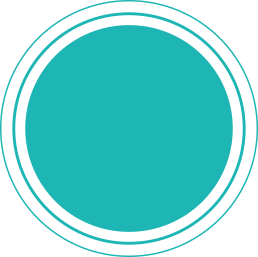
弁護士や会計士などが本業のスキルを活かして、無償で非営利団体を支援する社会貢献活動が『プロボノ(Pro Bono Publico)』だ。米英の弁護士が社会的弱者の無償支援から発展した活動で、アメリカの一部州では活動が義務化されている。日本でも東日本大震災以降注目度を増し、通常のボランティアとは専門性を活かした課題解決という点で差別化される。冒頭の士業だけでなく、ITやデザイナー、経営コンサルなど専門分野が制限されることはない。支援を受ける側は専門家の介入による課題の解決、支援をする側にとっても社会貢献だけでなくスキルアップ、人脈の拡大、ブランディングなどのメリットが望める。代替可能なボランティアだけでなく、専門性を持ったプロボノまで支援が広がることは社会を豊かにするキーとなりそうだ。
【参考URL】
https://corp.miidas.jp/assessment/14285/
No. 3198
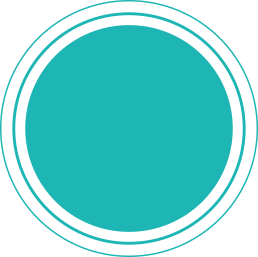
選挙区の区割りを恣意的に変更することで自党に有利な状況を生み出す戦略『ゲリマンダー』が、アメリカで連日報道される大きな話題となっている。トランプ大統領は2026年の中間選挙で共和党が勝つためにゲリマンダーを進めようとしているが、「禁じ手」とも言われる手法にメディアからの批判が高まっている。既にテキサス州議会は変更案を可決し、民主党支持層が多い都市部を分断することで共和党が5議席増える見通しだ。しかし、すべての州で共和党有利の変更が行われるのではなく、民主党支持層が強いカリフォルニアなどでは民主党有利の変更が予定されるなど、選挙前の制度面での攻防が激化している。日本でも議員定数削減を名目とした比例枠削減の話があるが、制度変更による票の価値のコントロールは民主主義の根幹に関わるため、慎重かつ深い議論が求められる。
【参考URL】
https://news.yahoo.co.jp/expert/articles/3b2fef0092cd4986c8a26eae57a80d1d9c2f2ca5
No. 3197
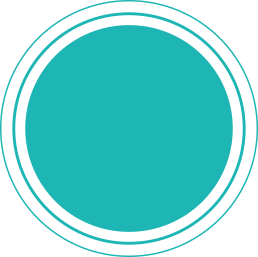
男性には少し馴染みが無いかもしれないが、昔流行した「シール交換」がリバイバルブームを起こしており、その牽引役となっているのがぷっくりと立体的に膨らんだ『ボンボンドロップシール』だ。サンスター文具から発売されている人気シリーズ。特徴は何といっても、“ぷっくり・ツヤツヤ・透明感のある立体感”。まるでキャンディのような見た目から「ドロップ」という名前がついている。2024年3月に発売された低年齢層向け商品だが、平成レトロやSNSでの拡散を追い風に大人の女性にも人気が拡大している。シール帳にしてコレクション・交換するだけでなく、立体感がスマホや鏡のデコレーションなどにもマッチ。現在ではキャラクタータイアップの商品展開も増えさらに人気を後押しするなど、この人気はしばらく続きそうだ。
【参考URL】
https://dime.jp/genre/2027508/
No. 3196
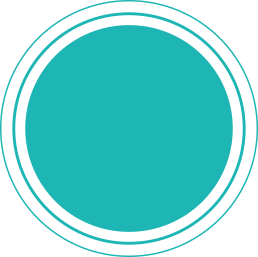
コテもカーラーも使わず、靴下だけでゆるふわヘアができると、おしゃれな女性たちの間で話題になっているのが、『靴下カール』だ。やり方は簡単。夜、髪を洗って軽く乾かしたあと、清潔な靴下で髪をくるくる巻いて寝るだけ。これだけで、朝ほどけば自然なウェーブが完成するという。熱を使わないため髪が傷みにくく、毛が細い子どもでも安心というメリットもある。さらに、靴下を輪っか状にした「ソックバン」でお団子ヘアを作り、ほどけば大人っぽいカールになるという上級者テクニックも動画で話題だ。忙しい朝に手軽にスタイリングできるうえ、道具いらずでエコな点も人気の理由。ヘアアレンジテクニックの新定番「靴下カール」で、ナチュラルな巻き髪を楽しんでみては。
【参考URL】
https://kinarino.jp/cat5/10689
No. 3195
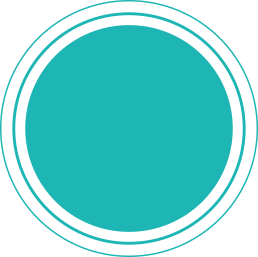
株式会社ディー・エヌ・エー(DeNA)が、社員のAIスキルを可視化する独自指標『DeNA DARSスコア』を今年8月に導入した。正式名称は「DeNA AI Readiness Score」で、従業員や組織ごとのAI活用レベルを数値化し、AIネイティブな企業文化の定着を目指すという。指標は個人と組織の2軸で構成され、AIの知識や活用度合いを5段階で評価。半期ごとに目標を設定し、スキル向上を促す。人事評価には直結しないが、AIを前提とした働き方の推進に大きな一歩となる。背景には、全社を挙げた「AIオールイン」宣言があり、AIを成長と変革の軸に、生産性の向上や新規事業を創出するのが狙いだ。今後は、DeNAのようにAIリテラシーを定量評価する企業が増えていく可能性も高い。AIの使いこなしが、個人と組織の競争力を左右する時代が、すぐそこまで来ている。
【参考URL】
https://dena.com/jp/news/5279/
No. 3194
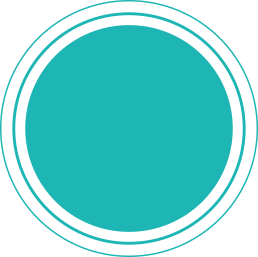
従来の健康保険証は2024年12月2日から新規発行が終了し、マイナンバーカードに保険証機能を登録した「マイナ保険証」へ移行した。経過措置として2025年12月1日までは使用できるが、期限を過ぎたものは無効となる。この移行期に、マイナ保険証を使わない人のために発行されるのが『資格確認書』だ。申請をしなくても自動的に交付されるのは、マイナンバーカードを持たない人や、保険証利用の登録をしていない人など。一方で、高齢や障害などの理由でカード利用が難しい人、または紛失や更新中の人も、申請すれば交付を受けられる。発行元や有効期限は保険者ごとに異なるため、詳細は加入している医療保険者の案内を確認しよう。問い合わせも所属保険者が窓口となるため、疑問や手続きの不安があれば早めの確認を。
【参考URL】
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45470.html
No. 3193
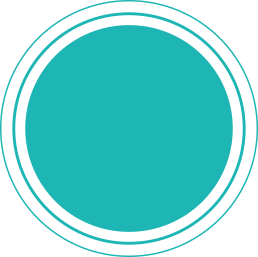
お尻から酸素を含ませた液体を送り込み、肺の代わりに腸で“呼吸”させる。そんな未来的な治療法の研究が進んでいる。東京科学大学の武部貴則教授らのグループは、酸素を含ませた特殊な液体を腸に送り込み、肺の代わりに酸素を吸収させる「腸呼吸」の仕組みを開発中だ。ブタの実験で症状の改善に成功し、昨年はユーモラスな科学研究に贈られるイグ・ノーベル賞を受賞した。直近の臨床試験では、健康な男性27人を対象に試験を実施し、酸素を含まない液体を投与して安全性を確認。軽い腹痛はあったが臓器への影響はなく、体内に吸収されず排出されたという。人工呼吸器に頼らず酸素を届ける新しい手段として、重症の呼吸不全などへの応用が期待される。
【参考URL】
https://news.web.nhk/newsweb/na/na-k10014970201000
No. 3192
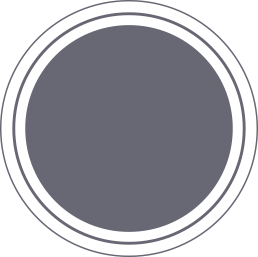
子どものためを思う気持ちが、時に成長の機会を奪ってしまうことがある。そんな親を指す言葉が『カーリングペアレント』だ。氷上でストーンの進路を磨き、障害を取り除くカーリング競技になぞらえ、子どもがつまずかないよう先回りして困難を取り除く親の姿勢を指す。似た言葉に「ヘリコプターペアレント」があるが、こちらは問題が起きた時に駆けつけるのに対し、カーリングペアレントは“起こる前”に手を打つのが特徴。愛情ゆえの場合もあるが、失敗や葛藤を経験できない子どもは、自分で考えたり立ち直ったりする力が育ちにくく、挑戦を避けるようになることもある。親の役割は、道をならすことではなく、転んだ時にそっと支えること。「失敗しても大丈夫」と伝えることこそ、子どもの自立を育てる最良のサポートだろう。
【参考URL】
https://chanto.jp.net/articles/-/1000693?display=b
No. 3191
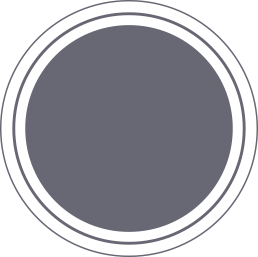
2023年、ゼンショーホールディングスがロッテリアを買収したことをきっかけに誕生した新ブランド『ゼッテリア』。1号店のオープンから2年で全国60店舗に拡大し、ロッテリアが減少する一方で、新業態として勢いを増している。看板メニューは「ワンコインモーニング」。中でも人気のソーセージマフィンセット(490円)は、厚みのある黄身色のマフィンに、スパイス香る生ソーセージとホクホクのハッシュポテトを組み合わせた満足度の高い一品だ。マフィンのバンズはゼッテリア独自の開発で、ふわふわの食感が特徴。さらに、コーヒーはフェアトレード豆をハンバーガーに合うブレンドで提供しており、味にもこだわりが光る。ロッテリアの延長線ではなく、“令和仕様”のアップデートブランドとして、ゼッテリアは新しい朝の外食文化を切り拓いている。
【参考URL】
https://toyokeizai.net/articles/-/885872
No. 3190
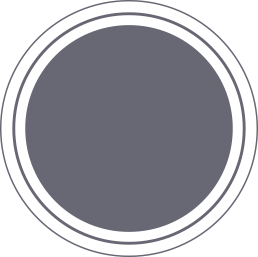
10月から大阪市立美術館で開幕した「天空のアトラス イタリア館の至宝」は、大阪・関西万博で話題を集めたイタリア館の展示を引き継ぐ、いわば『イタリア館特別展』。古代彫刻「ファルネーゼのアトラス」とペルジーノの「正義の旗」、そしてレオナルド・ダ・ヴィンチの手稿(紙葉2枚)など、万博でも注目を浴びた作品を各展示室に一点ずつ配し、静かな空間でゆっくり鑑賞できる構成が魅力だ。さらに、日伊親善の象徴である天正遣欧少年使節の主席正使・伊東マンショにも光を当て、会期途中からはドメニコ・ティントレットによる「伊東マンショの肖像」の複製画も展示予定という。一方で、事前予約は開始2日で全日程が完売。当日券販売は停止され、現在は日時指定者のみが入場可能だ。万博で生まれたアートへの熱気は、閉幕後もなお冷めることがない。
【参考URL】
https://www.sankei.com/article/20251022-QWHY33TZOZNTHMDFIGFSEC7YII/?outputType=theme_oriconnews
No. 3189
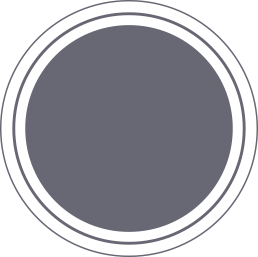
米国スタートアップのSavorが、二酸化炭素・水素・酸素・熱を使って脂肪をつくる独自技術を確立し、今春ついに『CO₂バター』こと「Savorバター」を発売した。風味は本物のバターに近く、乳製品フリーなのにコクがあると話題だ。サンフランシスコやニューヨークのレストランで提供が始まり、年内にはベーカリーや高級レストランにも広がる予定。生産拠点はイリノイ州の旧油脂工場を再生した「SavorWorks1」。週100キロ規模の生産をめざし、将来的にはパーム油や乳脂肪の代替としても市場展開を進めている。微生物を使わず、土地や水の使用を抑えてつくるSavorの脂肪は、従来のパーム油に比べて温室効果ガス排出量をおよそ半分以下に削減できるという。おいしさと環境へのやさしさを両立した「未来のバター」の登場だ。
【参考URL】
https://foodtech-japan.com/2025/05/24/savor/
No. 3188
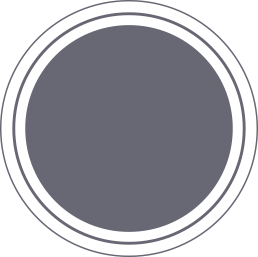
三菱UFJフィナンシャル・グループが国立競技場のネーミングライツを取得し、2026年1月より『MUFGスタジアム』が新呼称と決定。MUFGは国立競技場の運営会社である「JNSE」とパートナー契約を結び、競技場の価値向上と社会課題解決の両立を目指す方針を掲げている。名称はあくまで通称となり、正式名は国立競技場が維持される。
今後はICT技術の導入や新産業の支援、地域との連携による活用案の実現、文化継承・次世代育成など多岐にわたる競技場の活用を推進していく予定だ。さらに収益性強化のために他企業とのパートナー契約や施設内の命名権販売も進められる。大規模競技場はその維持費が問題となるケースも多く、解決のモデルケースとなるか注目だ。
【参考URL】
https://jns-e.com/mufgstadium/
No. 3187
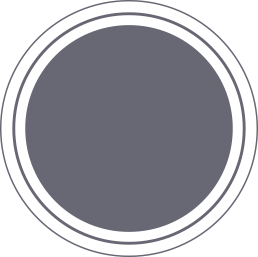
『推し広告』とは、自らの応援するアイドルやアーティストの誕生日などに街頭ビジョンや交通広告にファンが自費で出す文化で、韓国発祥のセンイル(韓国語で誕生日)広告が起源と言われている。
広告を出す動機としては、推しの誕生日を祝いたい、有名になってほしい、広告を見てほしいなどの声が多く、広告を通じて推しの成功を自分事のように喜び、ファン同士のつながりも強まるなど、新しい「つながり」の形として注目されている。SNSによる情報の民主化は広告の領域まで来たようだ。
【参考URL】
https://prtimes.jp/story/detail/px1NW9U03lr
No. 3186
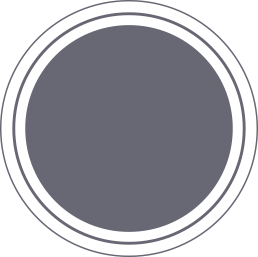
10月にセブン-イレブンが東京都限定で新商品「もち明太子チーズもんじゃ」を発売。東京名物のもんじゃ焼きを手軽に味わえる『コンビニもんじゃ』として注目を集めている。電子レンジで温めれば食べられる手軽さと、129kcalで間食でも罪悪感のない低カロリーがポイント。
さらに、味の面でもシャキシャキとしたキャベツ、伸びるチーズ、もちの食感、明太子のピリ辛が絶妙にマッチし、もんじゃのおいしさがしっかりと再現されている。SNSでも好意的な投稿が多く発信されており、コンビニグルメの懐の深さがさらに増していきそうだ。
【参考URL】
https://news.yahoo.co.jp/expert/articles/c5fade00aa86dc819d2d564b85413b4c70e8ed09