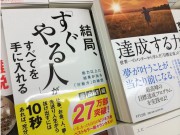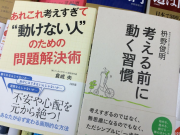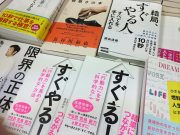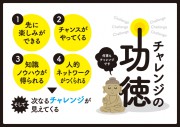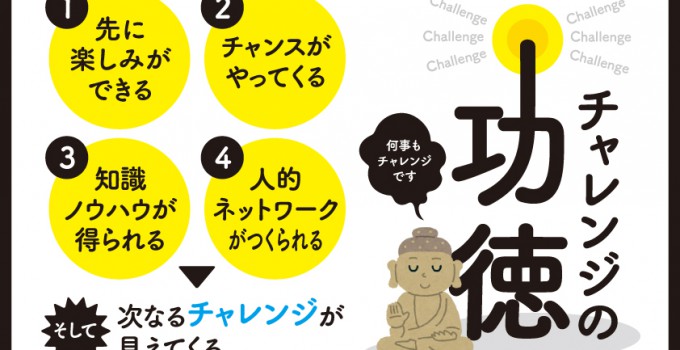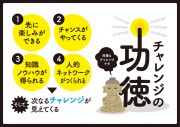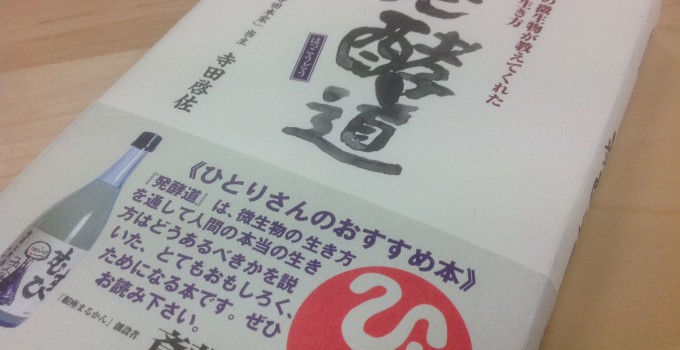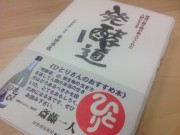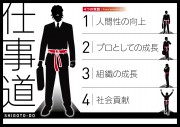08/22
2016
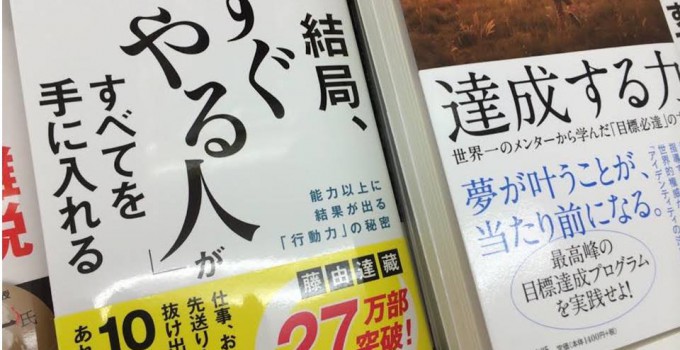
チャレンジの功徳がシナジー
やっぱり、人は「行動力」なのだろうか?
書店に行ってみると、
「行動力」についての本がちらほらと目につく。
例えば、ベストセラーにもなった
『結局、「すぐやる人」がすべてを手に入れる』という本。
サブタイトルは、
「能力以上に結果が出る行動力の秘密」ということで、
いかに行動力が大切かを説いている。
さらに、『考える前に動く習慣』というタイトルの本。
こちらは禅宗の考え方をもとに、
行動・体・心の順で自分を変えていこうという内容だ。
行動を起こすには、頭ではなく、
体から動かすのが良いということ。
『あれこれ考えすぎて“動けない人”のための問題解決術』
という本もあった。
要するに動かない状態が良くないし、
行動力が上がると人生が変わるということを訴えている。
最近は行動力を身につけるための
セミナーもたくさん開催されており、
インターネットでも注目されているようだ。
こうした例を挙げたうえで私が言いたいのは、
成功する人としない人の差は、学歴や頭の良さではない。
「行動力の差」なのだ。
先日のビジ達で書いた「チャレンジの功徳」も、
今回と同じく行動力の話だ。
中島流では、行動力=チャレンジである。
すなわち、「チャレンジは相乗効果をもたらし、
成功に導く」ということ。
では、チャレンジしない人はどうなるのかというと…?
1、チャレンジしないから、チャンスに出会えない
2、チャレンジしないから、チャンスを活かせない
3、チャレンジしないから、いい仲間と出会えない
4、チャレンジしないから、行動力が身につかない
5、チャレンジしないから、相乗効果が得られない
6、チャレンジしないから、知識やノウハウが得られない
7、チャレンジしないから、次なるチャレンジが見えてこない
こうしてリスト化してみると、デメリットの多いこと!
何もしないから何も起こらないし、成長もできないのだ。
皆さんご存知だと思うが、私ももちろん行動派。
あれこれと不安に駆られて考える前に、
「とりあえず行ってみよう」「やってみよう」の精神で
チャレンジを重ねてきた。
「覚悟」を持ってチャレンジすることが最善だが、
もし不安でも「スケジュールに入れてしまえ」ば、
やらざるを得なくなるだろう。
そうして行動力に磨きをかけて来たのだ。
「下手な考え休むに似たり」という言葉があるように、
考えているだけでは何も進展しない。
チャレンジこそが人を成長させ、成功に導くのだ!