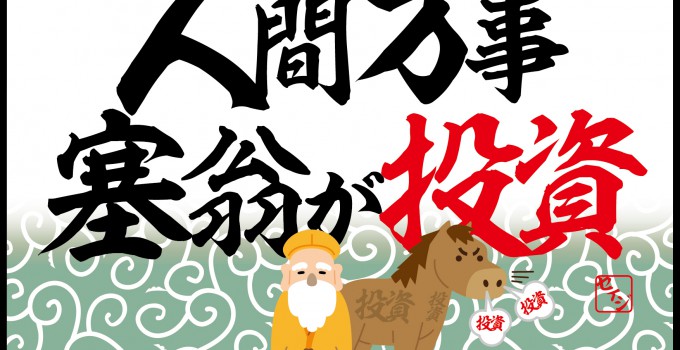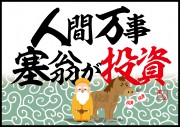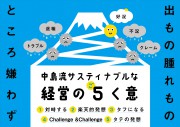04/04
2016

“経営の質”が見えてくる三段論法
AはBである。
BはCである。
よって、AはCである。
こういった理論を三段論法というのだが、
みなさんも学校で習った記憶があるだろう。
今回はこの三段論法により、
経営のあり方について語ってみたいと思う。
私は4年ほど、あるフィットネスクラブに通っていたのだが、
先日ついに、別のクラブへ入会することを決断した。
それまで通っていたクラブは自宅からも会社からも近く、
機具もメニューもある程度は揃っていたのだが…。
実は入会当時から不満に思っていたことがあったのだ。
(ま~積もり積もっての決断だったということ。)
その決断のポイントは、“お客様の質”。
柔軟体操用のマットのところで
長い間ぺちゃくちゃ会話する常連客たち。
耐え難い臭いのウェアでトレーニングに励む客。
ウォーキングマシンで大きな足音を立てながら
走り続ける客など…。
行くたびに不満を抱えながらトレーニングをしていたのだ。
実際のところ、客のマナーで気になる点はもっともっとあった。
それに加え、スタッフの
気のきかない対応にも不満を抱えていた。
客のマナーが悪くても、
それをきちんと注意してくれないのだ。
そして、常連客とかなりくだけた会話をするスタッフもいて、
施設全体のサービスレベルが高くなかったのだ。
はっきり言えば、レベルは低いということ。
そこで私は前述の三段論法になぞらえ、
中島流のこんな論法を考えたのだ。
経営はスタッフの質をつくる。
そのスタッフは客の質をつくる。
よって、経営の質は客の質をつくる。
その事業の理念を伝え
(しっかりした理念がない場合は論外だが。)
良い教育を受けたスタッフは、当然良い対応ができるもの。
(だめなスタッフを採用していた場合は別。)
そして、良い対応と良い気遣いを受けた客は、
節度ある振る舞いをしてくれる。
ところが経営の理念や方針がしっかり伝わっていないと、
スタッフもきちんとした気遣いや
対応をすることができないということ。
以前、人生の先輩方に教えてもらったのだが、
この論法を有効活用した、こんな言葉がある。
「銀座で良いクラブを見つけたければ、
一度は店に行って、相手をしてくれる女性ではなく、
客を観察しろ」というものだ。
すなわち、“その店の質は客で決まる”ということ。
どんな客がいて、その客がどういう振る舞いをしているかで
その店の質、スタッフの質まで見えてくる。
これは今回のフィットネスクラブや夜のお店だけの話ではなく、
私たちのビジネスにおいても同じことが言える。
経営の理念が明確で
しっかり教育されていれば社員の質も良くなり、
商品やサービスも上質となる。
ひいては購入してくださるお客様の質も良くなるということ。
逆に考えれば、客層を見るだけで経営の質も見えてくるのだ。
「あそこは良いお客様ばかりだね。」
そんな風に言ってもらえる企業を目指したいものだ。