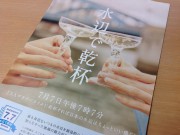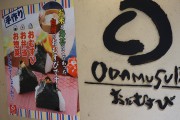08/03
2015

“九神ファーム”の存在意義
両手にゴム手袋をつけ、右手にはピーラー。
畑でとれたじゃがいもを次から次へと剥いていく。
彼らは、就労継続支援A型事業所の
“九神ファーム”で働く障がいを持った青年たちだ。
働きぶりだけを見たら健常者となんら変らず、
一日に25箱のコンテナを剥いたじゃがいもで
いっぱいにしてしまうという。
この九神ファームは、クックチャムという
惣菜販売の会社が運営している野菜加工の事務所。
ここで働く16人の従業員のうち
14名が障がいを持った人たちなのだ。
今回訪問させていただいて驚いたことは、
朝礼で会社の理念を唱和し、
その日の担当者が理念をひとつ取り上げて
自分の考えを語り始める。
そして、それに対して別の人が
コメントをする。
この形式の朝礼はこれまで視察で訪れた
多くの企業となんら変わりはらない。
つまり、“九神ファーム”には障がいの有無にかかわらず、
仕事に対して高い意識を持って臨む風土が整っているのだ。
あるとき、従業員が障がいを持つ仲間に
「今日は調子どう?」と聞くと、
「ちょっとおなかが痛い。
でも僕がいないとみんなが困るから大丈夫」と答えたという。
彼らはすでに自分の存在理由をそこに見出しているのだ。
毎日、同僚と肩を並べて仕事をしていくなかで、
仕事へのやりがいや切磋琢磨する気持ちが
確立されているということ。
これはとても大きな意味を持つ。
今までは、障がい者の立場は、
一方的に支援を受ける側だった。
しかし、彼らのように自ら仕事に向かう場合は違う。
家族に必要以上の助けを借りなくて済むし、
彼らの暮らす町の社会に貢献していることになるのだ。
これまでも、このビジ達では、
チョークの製造会社として有名な日本理化学工業や
ワインの製造・販売を手がける
ココ・ファーム・ワイナリーを紹介してきた。
日本理化学工業では、
いまや従業員81名中60名が障がい者だという。
ココ・ファーム・ワイナリーも、
ぶどうづくりやワイン製造に励み、
多くの人に愛される大人気のワインを生み出している。
“九神ファーム”を含め、それぞれの事業所に共通することは、
障がい者が高い意識を持って働ける場を提供しているということ。
そして、企業側も彼らを同じ志を持つ社員として扱っていること。
このように、障がい者たちが
自分の存在理由を見つけられる仕事を持つことで、
社会にとっても、大きな相乗効果を生むきっかけになるのだろう。