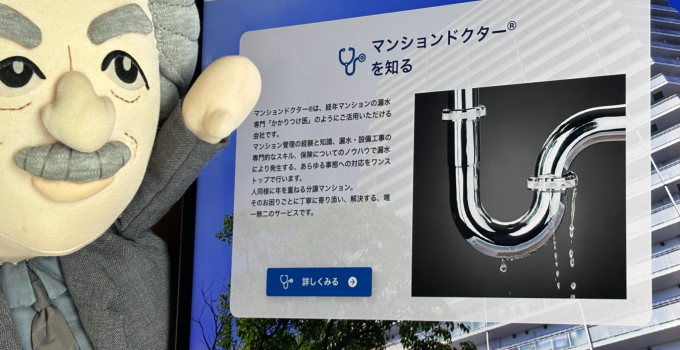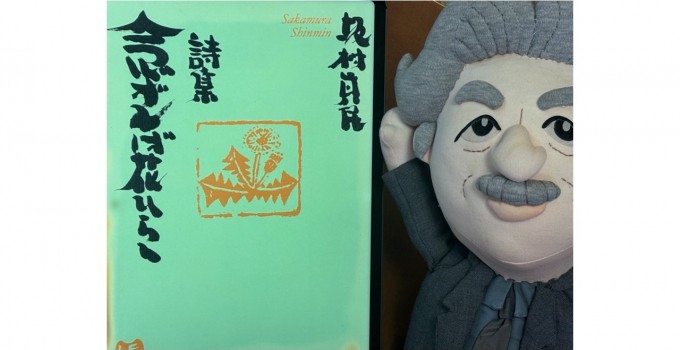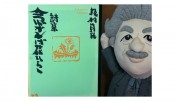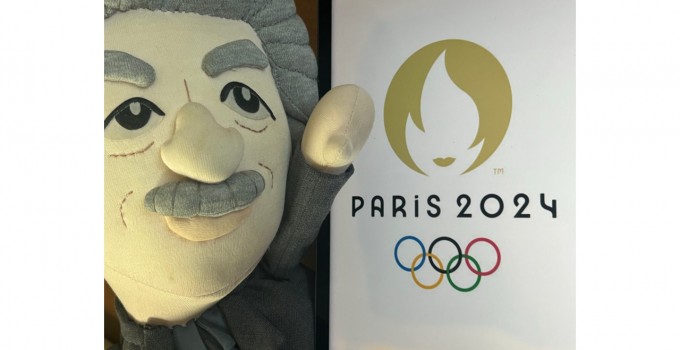10/28
2024

人気の“寿司チェーン店”から学ぶ これからの効率化と新サービス
先日もある“回転寿司店”で、
寿司だけでなくさまざまな料理とお酒を
美味しくいただいたわけだが…
その注文の仕方がどんどん進化していることに驚いた。
あのiPadのようなものからの注文だけでなく、
商品レーンの下に、メニュー紹介のようなカタチで
常に動いているデジタルサイネージの帯があり、
そのメニュー商品をタッチしても注文ができたのだ。
(おースゴ〜い!これでも注文できるんだ!)
このところの“回り寿司店”は、どんどん進化している。
寿司店だったのに、天ぷらありラーメンあり、デザートもある。
そしてあれこれ起きた事件により、
寿司はもう皿に乗って回らない状況になってしまい
店の人も皿の枚数を数えないでよくなっていたのだ。
もしかしたらどの業界よりも早くから
DX化に取り組み、そして進化してきたのかもしれない。
このお寿司屋さんのDX化は、1958年からだという。
大阪で創業された“元禄寿司”が、回り寿司のパイオニア。
当時は、より多くの人々に手軽に
寿司を楽しんでもらうための発明だったのだ。
そしてその回り寿司文化は、
60余年の間に紆余曲折しながらも時代の流れと共に進化し、
日本中に存在する文化となったのだ。
(あれっ、今は海外でも回っている?!)
【寿司チェーン店上位は、過去最高を達成!】
飲食店市場に逆風が吹き荒れるなか、
寿司チェーンの上位数社は、過去最高を達成したという。
人手不足の解消などを目的に開発してきた
DXによる超効率化策が、
非接触が求められるwithコロナ時代に実を結んだといえる。
2024年7月の寿司チェーン店の店舗数はなんと4164店。
もちろんこれら寿司チェーン店は
もう回ってないところも多いわけだが…
上位はみなさんもお馴染みの
「スシロー」で「くら寿司」で「はま寿司」。
DX化の流れも伴って、もっと美味しく
そしてスマートに進化した姿となり、
多くの人々に受け入れられるようになった。
(先日も店の前のエレベーターホールには、多くの人垣が…)
いまどき“寿司”というと、日本ではDX化された
この寿司チェーン店が当たり前になろうとしている。
そのくらい美味しくもあり、寿司だけでなく
さまざまな料理を効率的に食べることができるということ。
↓ ↓ ↓
寿司チェーン業界は、他の業界に先んじてDX化を進め、
その過程で競争と革新が相まって
新しいサービスを取り入れた飲食店として進化した。
この人手不足の到来と新たなサービスへの需要を考えると
この寿司チェーン業界の進化は、
私たちが見習うべきところがたくさんあるのかも?!