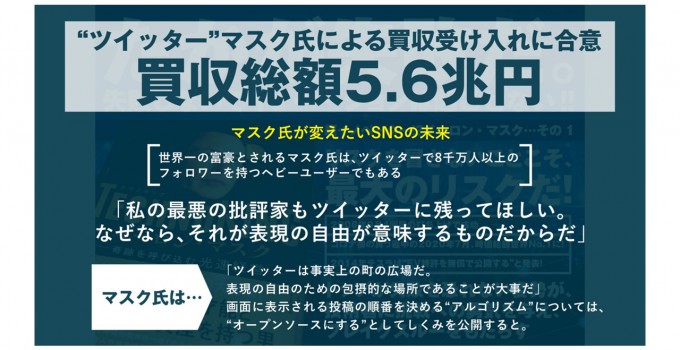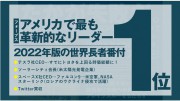08/01
2022

石坂典子流“しなやか経営”へ
~“しなやか経営デザイン研究所”を設立へ!?~
一時は存続すら危ぶまれていた石坂産業を再生し、
日本では無くてはならない存在につくりあげた
石坂産業の石坂典子社長がその実績とノウハウを生かし、
新たに“しなやか経営デザイン研究所”を設立した。
→これはビジ達流フェイクニュースだ!
というのも、先日のリーダーズセミナーで
石坂産業を訪問した際に、石坂社長との
トークセッションの時に私のアタマに浮かんだ発想。
石坂社長は、クリエイティビティやデザイン性も
非常に高く、哲学的であり、挑戦的かつ戦略的で
素晴らしい感性をもっているということを改めて感じた。
このノウハウや感性を、全国の中小企業に対して指南する
“しなやか経営デザイン研究所”を設立してほしいという
私の願望からの、フェイクニュースだ。
石坂典子社長は、約20年前に
代表権のない社長に就任したわけだが、
“父の想いの可視化”をテーマに
産業廃棄物処理の仕事をどう知ってもらい、
地域に安全安心の会社であることを発信できるか
ということに注力したそうだ。
この時期にはNHKやテレビ東京など
色々なテレビに出演し、能動的に発信した結果、
多くの人に興味を持ってもうことができたということだ。
また、経営者としても大胆にチャレンジして
素晴らしい成果をもたらしている。
例えば、15億円かけて造った、出来て間もない焼却炉を捨て、
40億円をかけて、焼却炉のない新しいプラントを設立。
さらに追加で2億円をかけて見学通路を設置し、
視察研修の受け入れを始めた。
今までの「産業廃棄物は見せられない業界」
というイメージを払しょくし“どう見せ、どう魅せていくか”
ということに力を注いだ。
他にも、雑木林の清掃整備をし、里山の再生に尽力した他、
森の整備や公園、神社の設置から、
レストランとして皆さんが集まれる場所として
“くぬぎの森交流プラザ”の開設など、
多くの人が興味をもち、集まってくれる施策を
いつも展開している。
そして現在は温泉を掘り、温泉施設の建設を計画しているが
ここにも戦略的なものがあると聞いている。
石坂社長の言う、“経営はデザインするもの”
という概念を実践しているわけだ。
どんどん変化する令和の時代では
人のモノの見方や、業界への見方の変化にも敏感になり
自分たちの存在理由も常にシフトしていかないといけないということ。
“しなやか”であるということが経営にとって
重要なキーワードになることは間違いないだろう。