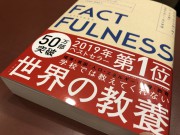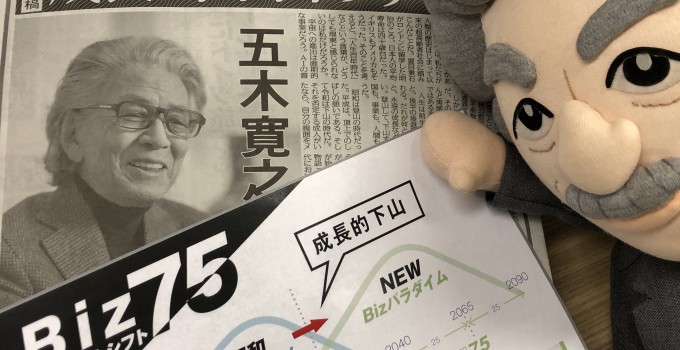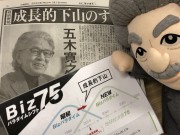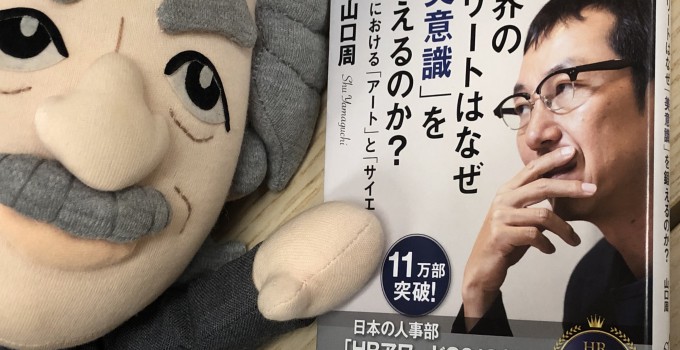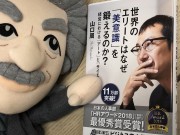01/27
2020
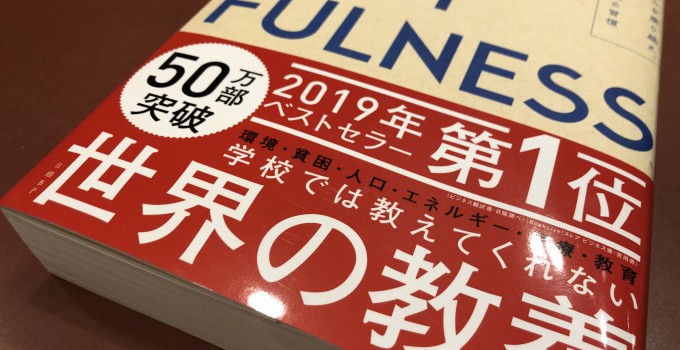
FACTFULNESSとは?
今先日もビジ達モバイルで紹介したFACTFULNESS。
これは2019年ベストセラー第一位の注目の書籍だ。
ハンス・ロスリング、その子どものオーラ・ロスリング、
その伴侶のアンナ・ロスリング・ロンランド、3人の共著だ。
残念ながらハンスさんはベストセラーになる途中で他界してしまっている。
この本のイントロダクションにあったクイズ13問のうち
4問を紹介するので答えてみてほしい。
質問 1 世界で最も多くの人が住んでいるのは?
a.低所得国
b.中所得国
c. 高所得国
質問 2 世界の人口のうち、極度の貧困にあたる人の割合は
過去20年でどう変わったか?
a.約2倍になった
b.あまり変わっていない
c.半分になった
質問 3 自然災害で亡くなる人の数は過去100年でどう変化したでしょう?
a.約2倍以上になった
b.あまり変わっていない
c. 半分になった
質問 4 世界中の一歳児の中でなんらかの病気に対して
予防接種を受けている子どもはどのくらいでしょうか?
a. 20%
b. 50%
c. 80%
ちなみに質問2に対しての答えだがアメリカで
正解率が5%で日本は10%, 世界平均では7%とのことだ。
これはオンラインで14カ国のエリートに対して質問をした結果だ。
さて答えだが・・・、
質問1から順に b c c c だ。
平均の正解数は、なんと12問中(事情があり1問はなかったことにして)
2問だ。
なぜ正解率が低いのかというと、人間のもっている「思い込み」本能に
起因しているという。すなわち、
分断本能 ・・・ 世界は分断されているという“思い込み”
ネガティブ本能 ・・・ 世界はどんどん悪くなっているという“思い込み”
直線本能 ・・・ 世界の人口はひたすら増え続けるという“思い込み”
恐怖本能 ・・・ 危険でないことを恐ろしいと考えてしまう“思い込み”
(書籍にはもっといろいろな本能が書かれていたが・・・)
これらの“思い込み”が人間の思考に大きく影響をしているという。
結論として著者が言いたいことは、
この思い込みを払拭しない限り、正しい判断ができないということだ。
少し前に“超マクロ思考マトリクス”をビジ達で発信した。
このマトリクスの活用も、これらのように“思い込み”があっては
将来通用する再構築プランはできない。
正しいデータで判断しないと間違った答えを導いてしまうということ。
それにしても、私もかなりの“思い込み”があったのだ。
やっぱり、メディアのニュースに囚われていては正しい判断はできない。
もっともっとデータに裏付けされた判断をしなければ!