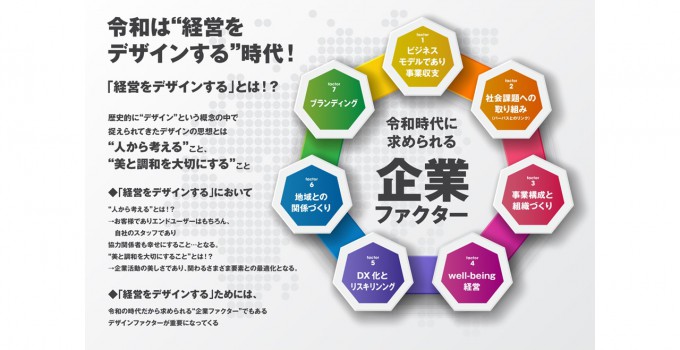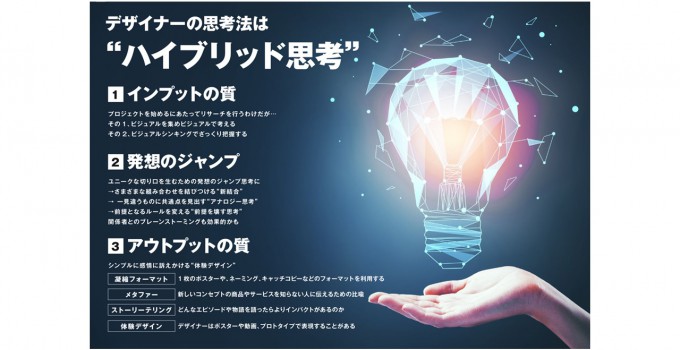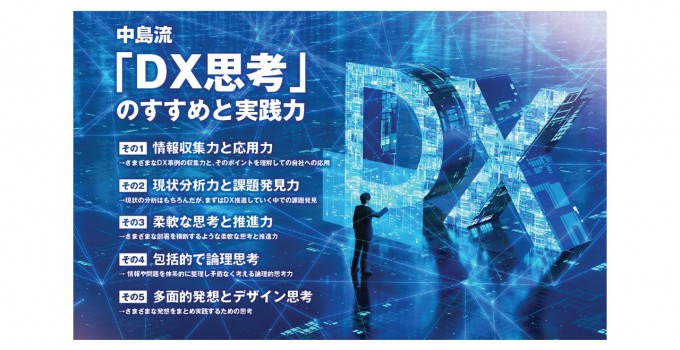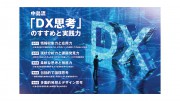01/30
2023

人事もパーソナライゼーション時代に! だから“ピープルマネジメント”
「時代はタテのリーダーシップからヨコのリーダーシップへ!
だからミーティングとティーチングとコーチングの
“3チング”が重要に!」とビジ達で発信してから
もう3~4年経っただろうか。
この時はマネジメントとキャリアディベロップメントに照準を当て、
“コーチング”を導入し、成果やスタッフの成長にも
貢献できる展開として紹介した。
「コンピテンシー・マネジメント」と銘打ち、
コーチングを活かすことでパーソナルな特性を活かしての
マネジメント手法として画期的発信だったと自負している。
ところが、その後も世の中はどんどん進化し、
人事はついに“パーソナライゼーション”領域へ!
だから今後はもっと人材を活かし経済的価値を高めるための
一人ひとりの人材に投資する“ピープルマネジメント”になるという。
【なぜ“パーソナライゼーション”に向かっているのか? 】
新卒一括採用に代表された同質性重視の従来型人事は、
すでに転換期を迎えている。
いまや国籍、文化や雇用形態、置かれているライフステージや仕事観、
保有スキル、入社時期などの異なる社内の多様な人材に対して、
それぞれに最適な働く環境や成長の機会を提供することが、
“人材マネジメント”の使命と言ってもいいだろう。
人事のパーソナライゼーションとは、
これまでの“全員一律人事”から“個別社員最適人事”への
シフトでもあるのだ。
【ピープルマネジメントとは!? 】
実は私自身、この“ピープルマネジメント”という言葉を
ほとんど使っていなかったのが実際。
あれこれ手にした書籍で、ついに行き着いたわけだ。
ピープルマネジメントとは、
従業員一人ひとりに向き合い、
仕事におけるパフォーマンス、
モチベーション、エンゲージメント、キャリアなどを含め、
その一人ひとりの成功や成長にコミットするマネジメント。
従来の人材領域のマネジメントは“タレントマネジメント”。
“タレント(従業員)”の持つスキルや経験を最大限に活かすために、
人材配置や人材育成を戦略的に行うマネジメント手法。
対してピープルマネジメントは、
人から場(チーム)に着目し、 タレントマネジメントで扱うような
人事データではなく、さまざまな動機や価値観、
意欲や働き方、キャリアを持った“チーム“を、
その中の人と併せてマネジメントするという。
【堂安選手の投入もピープルマネジメント発想】
昨年末日本でも盛り上がったサッカーW杯では、
“オレしかいない”発言の堂安選手を投入する際、
堂安選手の持ち味を最大限活かし
得点に結びつく連携が可能な人材を同時に投入した展開も
私的には、タレントマネジメントではなく“ピープルマネジメント”が
功を奏したと結果と言っていいだろう。
これからのマネジメントの在り方として、
一人ひとりにコミットする
“ピープルマネジメント”に スポットをあて、
あれこれ試行錯誤して欲しい。
とにかく時代は、人事も含めパーソナライゼーションに
向かっているのは間違いないようだ。
マネージャーは、もっともっと頑張らないとねぇ~。