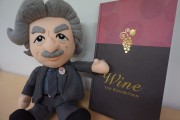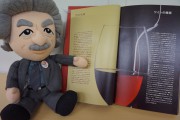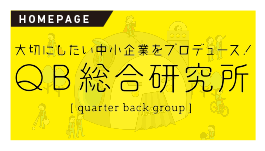02/01
2016

日本を救う“里山道”
“仕事道”をいろいろと語ってきたが、
今回のテーマは、“里山道”…?
“道”が多いな~、なんて思われたらちょっと残念。
中国哲学では、人やものがあるべきところ、
物事の本来あるべき姿、普遍的法則を指して、道=“タオ”という。
道家や儒家によって説かれた道によって、
多くの人があるべき姿に導かれていったのだ。
つまり、“仕事道”なら仕事の本来持っている
可能性を引き出し、活かすということ。
それはお金儲けのことだけではなく、
そこで働く人たちを育むということにも繋がる。
それこそが、本来の仕事のあり方だという
心意気を込めての“仕事道”なのだ。
そんな“仕事道”の価値観を持ちつつ、
この度私が十勝に立ち上げた「十勝里山デザイン研究所」では、
里山を十分に活かし、共に生きる“里山道”を掲げ、追求している。
私の思う“里山道”とは、以下の5つだ。
1.その里山をよく知る
一口に里山と言っても、地域ごとに違うもの。
その個性をよく理解することが、“里山道”を深めることにつながる。
2.里山との共生
利用価値のある里山を、利用するだけなんてもってのほか。
里山を活かし活かされる関係。そこに生きる生き物との共生が大切だ。
3.里山のパワーを引き出し、活かす
里山に秘められた無限のパワーは、そのままにしていては眠ったまま。
人の知恵をプラスして、潜在的パワーを活かしていくのが“里山道”。
4.里山の維持・継続
サステイナブル(持続可能)でなければ、意味がないということ。
次世代へ里山をつなげていく展開が大切だ。
5.里山をみんなで活かすまちづくり
限られた人たちだけではなく、
そのまちにいるみんなで里山を活かしていけば、
“まちづくり”はうまくいくはずだ。
人と自然が溶け合う里山という発想は、日本ならではのもの。
日本固有の文化として茶道、華道、柔道があるように、
“里山道”があるのは当然ではないだろうか。
今後、日本は経済優先の考え方から、
里山を中心にした社会・生活へ移行していくだろう。
さらに注目されていくことになる里山のために、
“里山道”を理解し推し進めていくことが重要なのだ。
さて、ここでわたしからの提案。
自分の業種業態に“道”をつけてみてはどうだろうか?
建築業の人は“建築道”、販売業の人は“販売道”より“商人道”かな?
“デザイン道”は、ちょっと厳しいかもしれないが…。
このように考えてみると、それぞれにあるべき姿が見えてくる。
今後の日本を救う“里山道”。
あなたの“道”は、一体どんな道だろうか!?