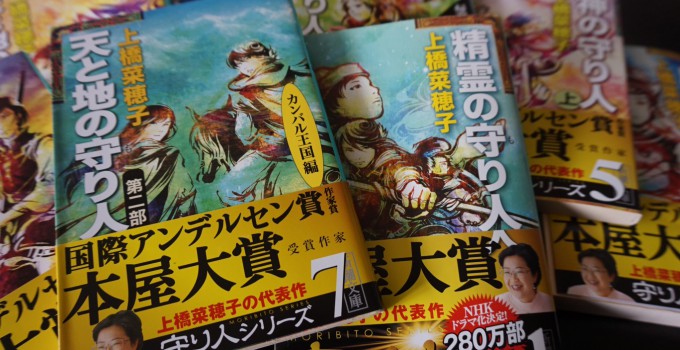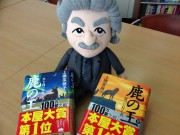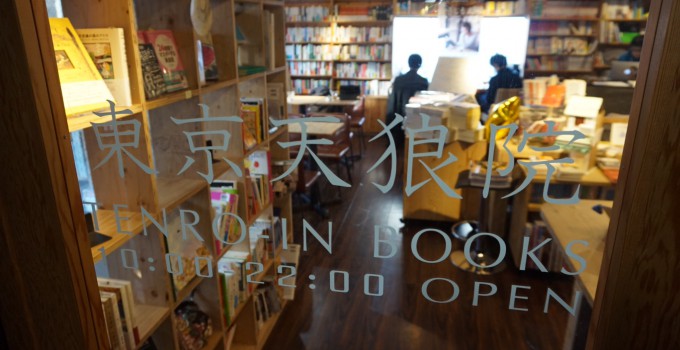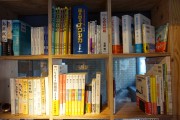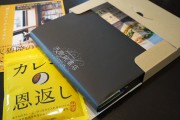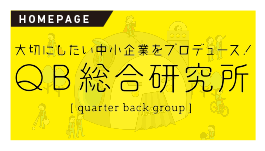11/16
2015

Japan Beautyの創造
“Japan Beauty”と聞いて何を想像するだろうか。
日本の美しい街並み?
掃除されていてゴミが落ちていない道?
いやいや、私にとってこの言葉は、
地方の色々な作物が作られている
田畑やその脇にあるあぜ道、
防風林や四季がめぐる農村…といった
日本の里山を想起させるものなのだ。
いま、少子高齢化による第一次産業の
担い手の減少が問題になっている。
これにより、耕作放棄地が増え、
山林は手入れされなくなり、
良い作物づくりも難しい…という
悪循環に陥っているといっていいだろう。
そんな今だからこそ、
「里山を活用し、地域活性につなげるビジネス」
が求められているのだ。
中島流に言えば
“里山をデザインする”ビジネスということだ。
ではどうやって里山をデザインするか。
そのヒントとなるいくつかの事例をご紹介しよう。
まずは、ビジ達でも何度かご紹介した
小林史麿(ふみまろ)会長が活躍する
「産直市場グリーンファーム」。
ここでは、その地域の農産物や
里山の幸を活かした産直の市場が大盛況だという。
この市場での交流は、
高齢化が進む地域全体の活性化につながっている。
さらに、この産直市場でイキイキとする高齢者を見て、
その家族が後継者になるなど、
地域にソリューションをももたらしている。
また玉村豊男氏が長野県東御市で展開する
「ヴィラデスト ガーデンファーム アンド ワイナリー」。
ここにはワインだけでなく、
その土地の産物を活かしたレストランなどもあり、
連日遠方から多くの観光客が足を運んでいるという。
また、玉村氏は千曲川ワインバレー構想を実践するべく、
千曲川の流域にたくさんのぶどう畑と
ワイナリーをつくることを計画している。
農業と自然の産物が持つ集客力を活かして、
地域の活力にするために奮闘しているのだ。
このように、今の時代だからこその
“里山のデザイン”を実践している
ビジネスはあちこちに存在する。
そのどれもが地域に相乗効果を生み出し、
活性化に貢献している。
まさに、美しい里山を守りながら
地域全体に良い循環を生む、
“Japan Beauty”の演出と言っていいだろう
(う~ん、いいフレーズだ!)。
そこで! このような
“Japan Beauty”の更なる創造につなげるため、
私はある応援部隊を発足しようと考えている。
その名も「日本の美しい里山応援協議会」だ。
“里山のデザイン”をテーマに
地域の活性化を手助けする団体だ。
これにより、日本本来の美しい里山を守ると共に
地域経済の活性化にも貢献することになるだろう。
日本が持つ美しい里山は、
活用することで現代の日本が持つ
様々な課題の解決につながる。
そのためには企業の協力による
“里山のデザイン”が大切なのだ。
“Japan Beauty”の創造は、
日本ならではの魅力の発信にもつながるのだ。