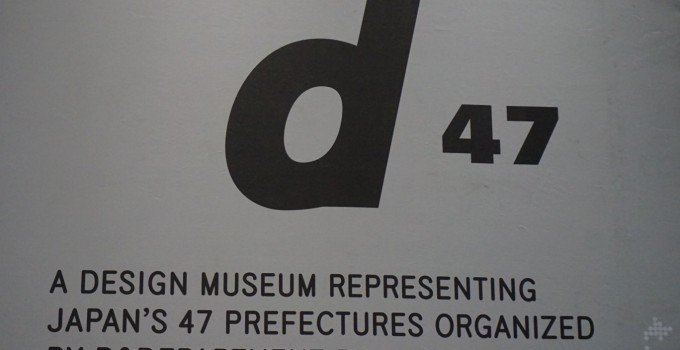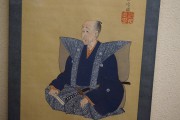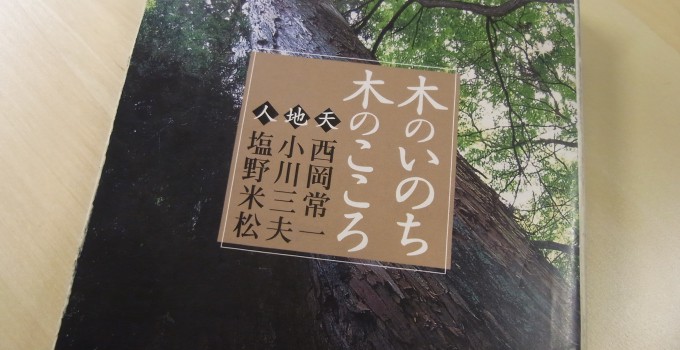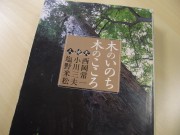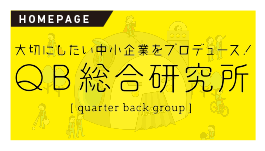10/13
2015

いまどきのソリューションビジネス
最近のビジ達でもたびたびご紹介している、
ソリューションビジネス。
ソリューション(solution)とは、課題解決という意味。
近年、日本では儲けるためのビジネスより、
時代の移り変わりによって浮き彫りとなった問題や
困っている人々の課題の解決に向けたビジネスが増えてきている。
今回はそんな“いまどき”の
ソリューションビジネスをご紹介したい!
新聞を読んでいたときに見かけた、
「不満買い取ります」という文字
(買ってどうするの? と思ってしまった)。
その名も「不満買い取りサービス」!
これは製品やサービスについての不満を顧客から集め、
データ解析を行った上で、その内容を
調査レポートとして対象の企業に販売するというもの。
専用のスマートフォンアプリで不満を集め、
不満の内容は製品にまつわることから接客のことまでさまざまだ。
そして不満を投稿してくれた人には、
Amazonでの買い物に使えるお得なポイントをあげるというもの。
企業と生活者、どちらにも利点のあるサービスとなっている。
ふたつ目のソリューション事例としてご紹介するのは、
「まごころサポートMIKAWAYA21」。
全国に数多くある新聞販売店のうちの約300店舗や、
地域密着ビジネスを行う会社を拠点に、
いま日本が迎えている超高齢化社会のためのサービスを展開している。
例えば、足腰を悪くして切れた電球を取り替えられない、
近所への買い物もままならないなど、シニア層が抱える
生活の中の「ちょっと困ったこと」を手助けしてくれるサービスだ。
新聞購読者が年々減り続ける現代では、
新聞販売店にとっても、これまでのネットワークが
活かせるビジネスとして期待ができるだろう。
そして、よくビジ達でもご紹介している株式会社マイファーム。
ここでは、農業体験ができるレンタルファームや、
週末農学ビジネススクールなど、
農業に興味のある人に向けてのサービスが展開されている。
ソリューションビジネスの鍵となるのは、
耕作放棄地の再生と有効活用の追求で、
これからの日本が抱える問題解決に向けて、
必要な技術を学ぶことができるのだ。
最後にご紹介するのは、
山形県鶴岡市にあるスパイバー株式会社。
世界的にもビッグニュースとなった、
「クモ糸タンパク質」の人工合成と
量産化技術の開発に成功した企業だ。
自然界においても、クモの糸というのは
強さと柔らかさを兼ね備える究極の素材であるが、
この高強度繊維を人工的に作り出し、
我々の生活に役立てることが期待されている。
このスパイバーについては、
改めてこのビジ達で詳しくご紹介する予定なので、乞うご期待!
このように、現在では多方面で
ソリューションビジネスが展開されている。
解決策をビジネスとして社会に提供する企業は、
これからも増えていくかもしれない!