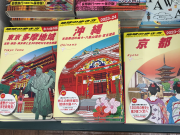12/19
2022

薬物やアルコールの依存症を断つための施設 “ナルコノン・ジャパン”を掃除で支援!!
「ナルコノンに掃除に行く?」
ん?鳴子のん…?(宮城県の鳴子温泉かな)
そんなお誘いがあり、掃除の会のメンバーと向かった先は、
「一般社団法人 ナルコノン・ジャパン」。
千葉県市原市の山の中にある薬物やアルコールの依存症を
断つためのリハビリテーション施設だ。
掃除の会のメンバーなら、当然協力したくなる社会性ある施設なのだ。
https://narcononjapan.or.jp/
薬物依存症からの回復をサポートする“ダルク”は知っていたが
“ナルコノン・ジャパン”は初めて耳にした名前だった。
(→ ナルコノン・インターナショナル(Narconon International)は、
サイエントロジーの創始者であるL・ロン・ハバード氏によって開発された
薬物乱用の治療プログラム)
今回が初めての掃除人の人たちには、代表者の神野正啓氏が
直々にこの施設について動画を交えて説明してくれた。
以下がその内容だった。
(私の質問に答えてくれたことも含めて)
↓ ↓ ↓
神野さんは、大学の薬学部を卒業し、薬剤師として勤務。
多くの依存症の人に向け、薬を処方して渡すのだが、
一向に改善に向かっているようには見えなかったという。
そして薬物に頼らないリハビリを求めている知人から
多数の相談を受けることに。
そこで何とかしたいと探し回り、“ナルコノン”に行き着いた。
しかし、残念ながら日本には存在してなかったのだ。
当然、諦めていろいろと試行錯誤するわけだが、
再び“ナルコノン”に行き着き、“それならば自分がやるしかない”と決断!
ナルコノンの施設を日本に設立することになったという。
当然だが、“決断”さえすれば施設が出来るわけではなく…
その資金含めクリアしなければならないことは盛り沢山。
とにかく大変なことばかりだったというが、
遂に2021年4月にオープンに漕ぎ着けたのだ。
そして神野代表は
「薬物依存から抜け出し、正しい知識を持つ人を増やすことで
日本の未来を変えたいと思っています」と話した。
◆薬物リハビリテーション施設の4つのテーマ
【1】ウィズドロー(薬断ち)
→代替薬物を用いない”薬物離脱”
【2】デトックス(薬物を体から抜く)
→ビタミン、運動、サウナで体内の薬物を全部出す
→1日5時間サウナに入る
【3】行動療法
→周りの人や物とコミュニケーションを取る演習
→意識と感覚の安定を目指す
【4】人生の技能を学ぶ
→人生を送る上で必要となる人間関係などの知識を学び
今後の人生をどう生きるか計画を立てる
↓ ↓ ↓
日曜日の朝は7時20分船橋市の“日本企画”に集合と早朝だったが、
“ナルコノン・ジャパン“に着く頃には時計は既に9時を指していた。
(房総半島の真ん中くらいの山の中だった)
掃除人はみんなで20人弱。
今回の私の役割は、施設の外側の窓拭き担当だった。
落ち着いたブラウンで、少しオシャレさも備えた木造の建物を
11時半頃まで集中して磨き込んだわけだ。
実はこの施設の木造の解放感とオシャレさも、リハビリテーション施設として
選ばれる大きな理由になるという。
そして掃除により清潔感を演出する私たちの存在も、
実はかなりお役に立てていると言ってくれていた。
“また、掃除させていただきます! ”