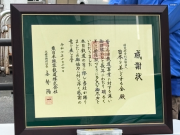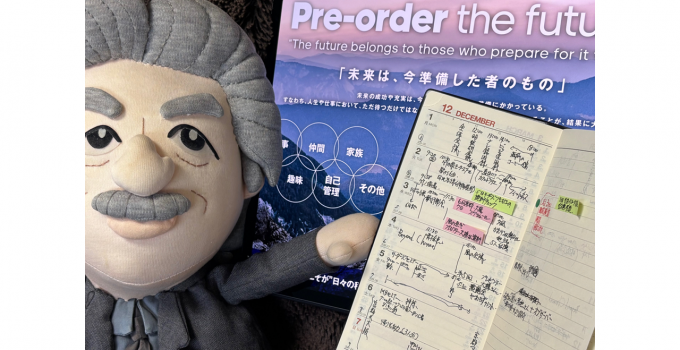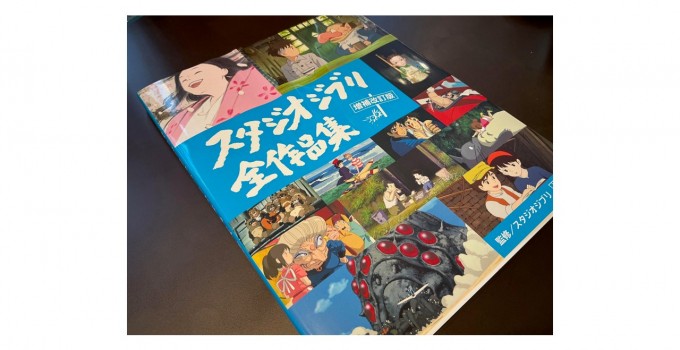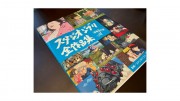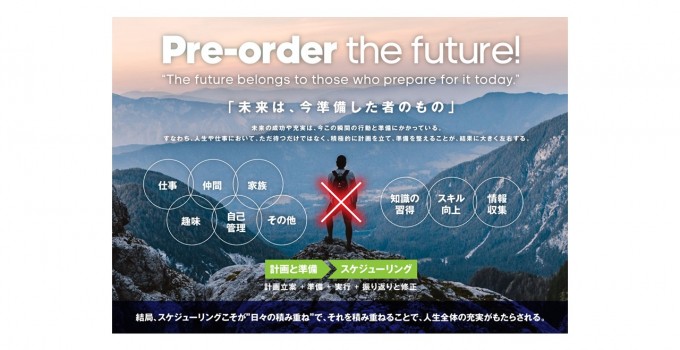01/13
2026

鍵山秀三郎相談役から学ぶ-part 4 掃除から始まる繁栄の輪!
鍵山秀三郎『凡事徹底』
テーマ/『繁栄』
「きれいな国家は栄える。きれいな会社も繁栄する」
と言われます。
きれいにすることが繁栄につながるのは、
そこに身を置く人の気持ちが前向きになり、
やる気につながるからです。
汚くて雑然とした環境では、
何から手をつけていいのかわかりません。
まず生活環境をきれいにして、仕事がやりやすいように整える。
このことが、繁栄するための第一歩です。
(鍵山秀三郎著『凡事徹底』「一日一話」PHP研究所刊)
鍵山相談役は、“きれいにすることは、
そこに身を置く人の気持ちが前向きになり、
やる気につながるから”と語っている。
雑然とした汚い環境では、人の心も荒み、
何から手をつけて良いか分からず、思考が停止してしまう。
一方で、掃き清められ、整理整頓された空間は、
人の心に静寂と規律をもたらすという。
“さあ、やろう”という前向きな活力が自然と湧いてくるのだ。
つまり、生活環境を整えることは、
単なる美化活動ではなく、
私たちの内面にある“やる気”や“善意”を引き出す
スイッチとなり、それが仕事の効率化や質の向上、
ひいては組織の繁栄へとつながる一歩となる。
【JR東日本の代表取締役社長より、感謝状をいただく!】
“日本を美しくする会”が、
東日本旅客鉄道株式会社 代表取締役社長より
2025年10月に感謝状をいただいた。
「みなさんは、鉄道事業に対する深い理解のもと
長年にわたり、明るく美しい新宿の駅づくりに
多大な尽力をいただきました。
本日鉄道の日に際し、
当社が賜りましたご協力に対し、
深く感謝の意を表します」
(素晴らしい!)
【 継続がもたらした信頼と共鳴、そして伝播へ】
この鍵山相談役の言葉でありその信念の証明とも言える出来事が、
このJR東日本社長よりの感謝状。
長年にわたり、“明るく美しい新宿の駅づくりに多大な尽力を…”
という感謝の言葉は、黙々と拾い続けられた一つひとつのゴミが、
確実に社会からの信頼を積み上げてきた証ということ。
さらに近年、JR東日本の駅員や駅長さんもが
この清掃活動に加わってくれているという事実。
鍵山相談役が常々語っていた“凡事徹底”の姿勢が、
周囲の人々の心を動かし、新たな行動の輪を広げている。
駅がきれいになれば利用者の心も和み、
街全体の空気が変わることにつながる。
このところの多くのインバウンドの方々も
この日本の駅やその周辺のキレイで整った空間と
電車のリアルタイムの発着を、必ずや喜んでくれているはず。
◆「ひとつ拾えば、ひとつだけきれいになる」
鍵山秀三郎相談役の言葉だが、
一人の手から始まった掃除が、企業の枠を超え、
働く人と街を行き交う人の心を結びつける。
これこそが、鍵山相談役が伝えたかった
“繁栄”の真の姿なのかもしれない。
足元のゴミを拾うという小さな行為が、
やがて大きな信頼と共鳴を生み出し、
社会全体を豊かにしていくのだ。