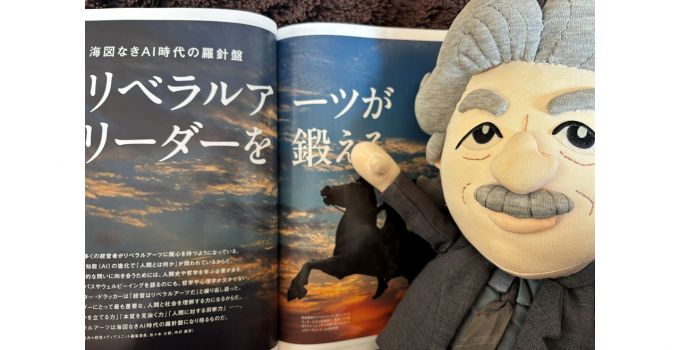02/16
2026

「見えるものを磨けば、心も磨かれる」 松下政経塾による“掃除”というリーダー教育
先日の“日本を美しくする会”総会では、
“松下政経塾”元常務理事の上甲 晃(じょうこうあきら)氏が
ゲスト講師として話をしてくれた。
ー「世界に冠たる指導者になるには、誰よりも朝早く起きて、
目の前の掃除をすること」というのが、
松下幸之助氏の言葉だったんですよ。
どんな特別なことを教えてもらえるのかと思ったら、
早起きして掃除してくれと!
彼らが「はい、わかりました。明日から頑張ります」と言ったら、
僕は鍵山秀三郎相談役に出会うこともなかったし、
この“掃除に学ぶ会”でこうして話をすることもなかったんです。
残念ながら、塾のみなさん、やらないんですよ。
偏差値の高い人ほど…
“そんな雑用してる場合じゃない”って言うんですよー
(→84歳とは思えない溌剌とした話だった)
これが上甲氏の冒頭の話。
この2月の衆議院選挙では、“ゼロ打ち”当確の高市総理も含め
松下政経塾出身の候補者がなんと40名もいたという。
彼らが学ぶ政経塾において、
なぜ“掃除”がこれほど重視されるのか。
そこには、当時副塾長であった上甲晃氏が
長い試行錯誤の末に辿り着いた、ある確信があった。
上甲氏は経営の本質を
【1】将来像の提示
【2】実現段取りの明示
【3】具体的実行開始
の三要件にあると説く。
これは国家経営も人生経営も同様。
しかし、どれほど立派なビジョンを描いても、
それを実行する人間に“心”が伴っていなければ、
絵に描いた餅になってしまう。
政経塾では当初、語学や政策論などのエリート教育が期待されたが、
松下幸之助塾長が求めたのは
「早起きして掃除をする」という“凡事徹底”だったのだ。
【松下政経塾が辿り着いた、“掃除”というリーダー教育】
しかし、人を育てるのは容易ではない。
上甲氏は当初、塾生たちに掃除をさせるため、自ら率先垂範を実行。
ところが、“俺がやっているんだからお前たちもやれ”
という下心が見える行動は、
かえって塾生たちの心を冷めさせてしまったという。
管理や理屈でカタチだけ整えても、内発的な動機づけには至らない。
“やらせる”教育の限界だった。
そんな模索するタイミングで出会えたのが、
イエローハット創業者の鍵山秀三郎氏。
上甲氏は鍵山氏を講師に招くことを決断。
一代で優良企業を築き上げた経営者の言葉には、
圧倒的な説得力があったという。
「見えるものを磨けば、見えない心も磨かれる」。
この鍵山氏の実践哲学に触れ、
エリート意識を持っていた塾生たちは、
初めて掃除の真意を理解していった。
それは単なる美化活動ではなく、傲慢になりがちな心を整え、
指導者に不可欠な“情や愛嬌”そして“運の強さ”といった
非定量的な魅力を育む修行そのものだったという。
↓ ↓ ↓
政経塾出身の政治家たちが、地盤や看板、
そして金に頼らずとも道を切り拓いていけるのは、
この“掃除”という原点を通じ、
理屈ではない“人間の機微”を学んだからなのだろう。
凡事を徹底して磨き上げた心こそが、
混迷する時代を導くリーダーの羅針盤となるという。
結果として、政経塾出身の塾生が何人当選したか分からないが…
とにかく、この混迷するVUCA時代の
リーダーとなってくれることを期待する。