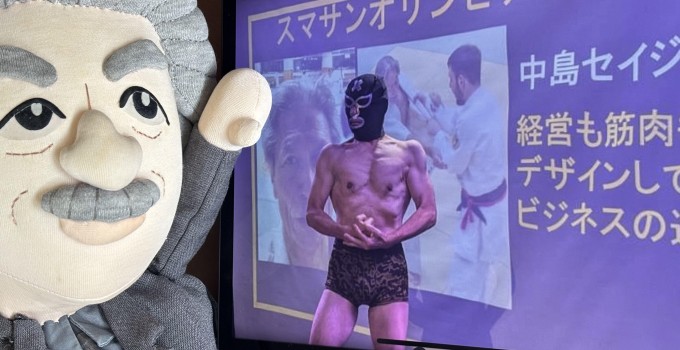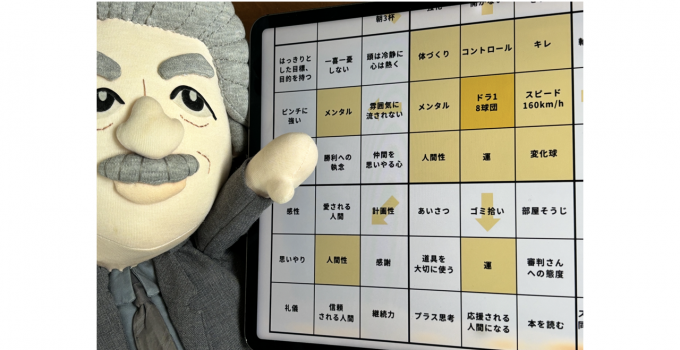10/20
2025

J-ROCKやJ-POPの名曲と約20,000発の花火がシンクロ!
うんうん、素晴らしい!
見応え、聴き応えありの“ロッキン・スター・カーニバル”
体験させていただきました。
(期待を上回るイベントだった!)
大きな花火大会の2万発の醍醐味に加え
J-ROCKやJ-POPの名曲の世界観と
レーザー演出まで加えての音楽花火イベント。
(残念ながら、楽曲については詳しくは語れないが…)
20,000人を超える人たちが茨城・ひたちなか市の
“国営ひたち海浜公園”に集まった。
舞台近くのエリアは、音楽フェスさながらの
常時立ちながら、腕振りながらの若者が集う。
(暗くなってからのトイレは、要注意!
暗い中、20,000人の中でどう仲間の居場所に戻るか?!)
このイベント、日本最大の音楽フェスティバル
“ロック・イン・ジャパン・フェスティバル”などの
音楽フェスで知られる“ロッキング・オン”が手がける
全く新しい音楽花火イベント。
そしてさまざまな音楽フェスでクロージングDJを務める
“DJ和”が選曲と進行を担当した。
(私にとっては知らない世界の人だが…)
そして関わった花火師たちも、
曲も意識して花火を仕込んだと聞く。
【このフェスティバルをプロデュースし、奔走した人がいる!】
“ロッキン・スター・カーニバル”の成功は、
既存のそれぞれの人気要素とその相性のよさを
上手く活かしたことで新たな価値を創出した。
すなわちプロデュース力がそこにある。
いまや我々のビジネスも、さまざまななビジネスに
AIでありテクノロジーの融合を通じて、
新しいサービスやプロダクトを
どうプロデュースするかが求められている。
ちなみに私の元々の仕事は、このプロデュース的仕事が多かった。
→料理やワインの著名人に着目して、その業界のノウハウを
別業界のツールやイベントに活かして顧客開拓に繋げるとか。
→さまざまな業界の著名人を招聘して
経営者向けのイベントや情報誌に展開するとか。
この別業界のものであったり新たなテクノロジーを
その相性も含め“プロデュースする力”がいま求められている。
“ロッキング・オン”のこの花火フェスティバルを計画、
プロデュースした人のプロデュース力に着目したい。
すでに“ロッキング・オン”には、音楽フェスによる
多くの音楽ファン(顧客)がいた。
その多くの音楽ファンは、それぞれ趣味を持ち
それぞれの日常を送っている。
その音楽ファンたちの“日常のプラスアルファ”に
アプローチしたということ。
【今のビジネスへの、テクノロジーの融合がポイント!】
これからはAIの活かし方であり、さまざまなテクノロジーを
既存ビジネスにどう応用して、
新たな差別化あるビジネスをプロデュースするかである。
例えば、AIによるデータ解析と
マーケティング技術の組み合わせで、消費者ニーズの予測を行い、
新たな市場を開拓することが考えられる。
また、AIがもたらす自動化技術によって、
効率的な業務プロセスを構築し……
あーまたいつもの令和時代の
新たなビジネスづくりの話になっていってしまった。
ところで、これだけの音楽ファンを抱えている
“ロッキング・オン”は、
この花火イベントの次は、何処へ向かって行くのだろう?!
来年もこの“ロッキン・スター・カーニバル”へは
ぜひ出向き楽しみたいけど…