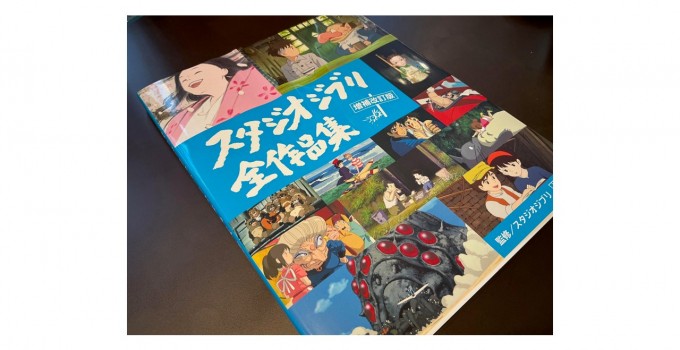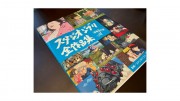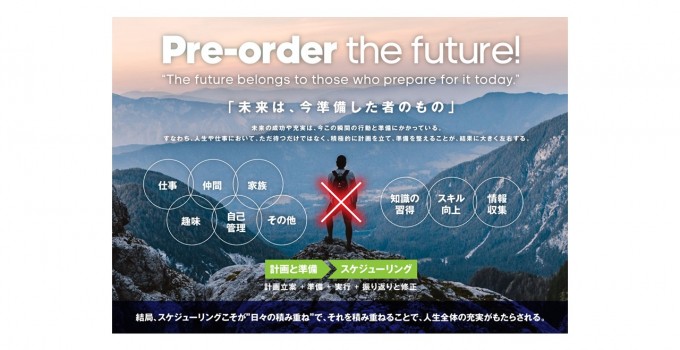12/08
2025
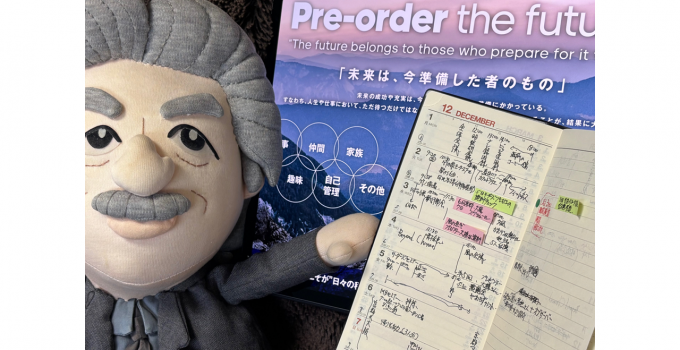
人生をデザインするスケジュール術-part2 “ビジョン&スケジューリング”
先日、リーダーズセミナー1年間のフィナーレとしての
“V&Tプレゼンテーション”を開催したわけだが、
V&Tは、Vision & Tomorrow。
すなわち、未来ビジョンを語り、
明日からどう実現していくかをプレゼンするわけだ。
もっと言えば、未来の在り方(Vision)を
どうこれからの日々に“スケジューリング”するかということ。
「手帳は覚えている。
たとえあなたが忘れても。
今日の喜びや、葛藤や、風景を。
対話できる過去がある。
それはきっと、
明日へ踏み出す力になる。
書いて、考えて、振り返る。
今を積み重ねることでしか
つくれない未来を、ノルティとともに。」
これは私が使っている日本能率協会の“NOLTYウィック7”に
差し込まれていたカードに書かれていた言葉。
→もっと未来に向けたメッセージにして欲しいが…
できれば、先の“ビジ達“で紹介した以下の名言も
このカードに入れて欲しい!
“The future belongs to those who prepare for it today.”
「未来は、今準備した者のもの」
【ビジョンに沿ったスケジュールと未来がそこに!】
私の場合は…
自分のビジョンに合わせて、考えて、書込み、
その時が来て実行する。
そして振り返る。
この積み重ねが、ビジョンに沿った未来を創り出すことに!
もちろんGoogleカレンダーも使っているのだが
このNOLTYの“週で見開き”の手帳がいい。
過去も振り返りやすいが、これからの予定も見やすいのだ。
例えば…この1~2年は、“筋トレ&ランニング”を
平均で週2回のトレーニングを実践できているのだ。
(これも実践してのポチシールが貼ってあるから一目瞭然)
1回のフィットネスジムで課せている筋トレ他は以下 ↓
1.胸筋マシントレ(負荷2000kg以上)
2.鉄アレイによる腕筋トレ(左右7kg×150回)
3.左右揺さ振り腹筋(50回)
4.ランニング(時速10キロ平均で3km)
5.腕立て伏せ70回(or懸垂10回)
→これを実践して、ポチシールを貼るときもワクワクする。
【未来ビジョンを見据えた“スケジューリング”が設計図となる!】
この“ビジ達”コンテンツを週に2本、すなわち月に8本創り、
写真や概念図も用意することが、
結果としてYouTube“ビジ達7”の材料にもなるし、
定例セミナーでの発信コンテンツにもなる。
また、年間36回開催される経営者会議“三尺三寸箸会議”の
アドバイスの質にも反映するということ。
先にも発信したが、手帳に書き込むスケジュールは、
単なる予定管理のためのものではない。
私がNOLTYに書き込む予定は、私の未来を演出する設計図。
すなわち、これからの仕事の質であり、
人生の質をも高めるための行為なのだ。
(古稀を迎えて私の未来を語るのは、少し恥ずかしいが…)
だからこそ、私たちは“どんな未来をつくりたいか”から
スケジューリングするべきなのだろう。
理想のあり方を言語化し、
週単位・日単位の予定にまで落とし込む。
そのプロセス自体が、迷いを減らし、行動の精度を高め、
結果としてビジョンと現実をゆっくりと重ね合わせていく。
→手帳をひらくとは、自分の未来と対話する時間なのだ。