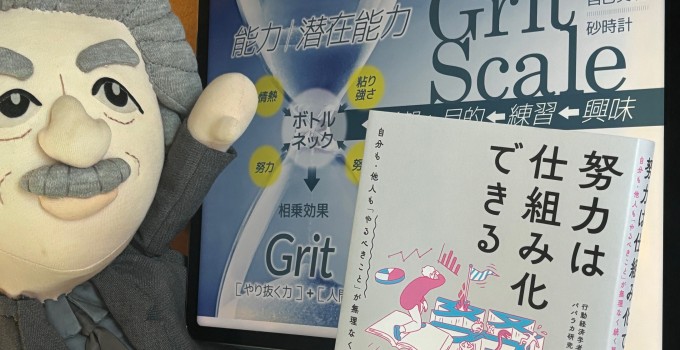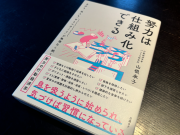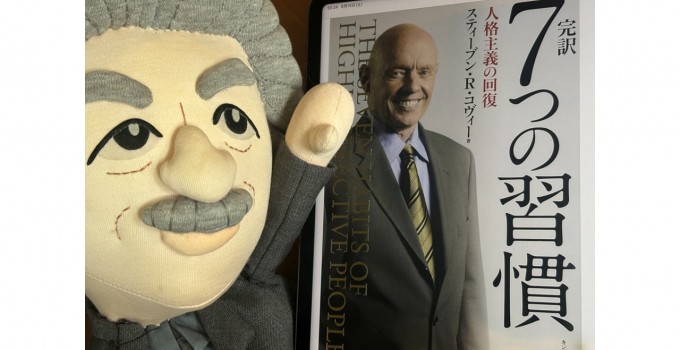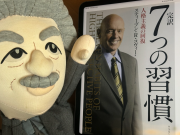10/15
2024
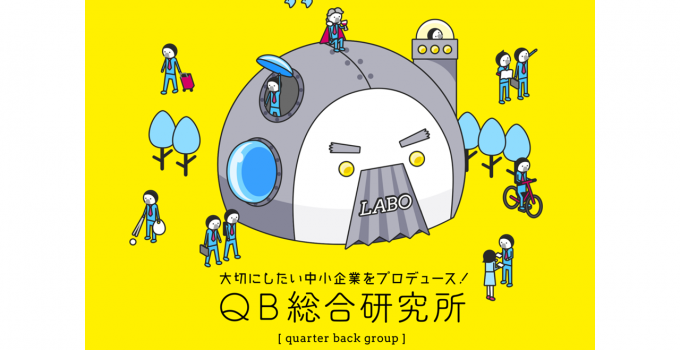
“三尺三寸箸会議”から学ぶ、 ファシリテーションの意義
私が企業戦略研究会“アルファクラブ”を開設してから31年。
そのクラブメンバーで“三尺三寸箸会議”を
スタート(2012年?)させてからは、すでに12年が経つ。
お陰さまで、銀の会議、プラチナ会議、宙の会議、星の会議の
4つの会議が結成10年を過ぎているが、
どの会議も定期的に充実したBRT会議を開催し続けられている。
(参加経営者のみなさん、ありがとうございます)
基本的に経営者によるBRT(ビジネスラウンドテーブル)会議を
そのルールに基づいて、結構厳密に展開しているわけだが、
みなさんこの会議の意味とその価値を理解して
参加してくれているということ。
ここまでいいカタチでこの“三尺三寸箸会議”を
継続してこられたのは、メンバーのみなさんが
自覚ある経営者であることと、BRT会議ルールに基づいた
“ファシリテーション”にあると思うのだ。
BRT会議では、このファシリテーションを“モデレーター”が
展開するわけだが、この“三尺三寸箸会議”では
私がその役割を引き受けている。
ここではこのモデレーターの役割であり、
そのファシリテーションの重要性を発信したい。
【ファシリテーションは、みんなで問題を解決するための技術】
ファシリテーションとは、みんなで協力して
問題を解決するための技術である。
このBRT会議のモデレーターによるファシリテーションは、
参加経営者の意見を引き出し、議論を活発化させることで、
互いに経営者として、このすべてが加速する時代にあっても
よりよい判断ができる自分づくりを可能とする。
そこでこの会議のファシリテーションにおける
三つの大きなメリットを紹介しよう。
【まず一つ目は…】
メンバー同士の協力によって
高い成果を生み出すことができるところ。
いろいろな経験や知識を持った経営者が集まって話し合うと、
個々では気づかない解決策を見つけることができる。
内密性を条件にしたファシリテーションは、
みんなが安心して意見を発信できる場となるので、
独自の視点や意外なアイデアが生まれやすくなる。
これにより、通常では考えつかないような画期的な解決策が
見つかることがある。
【次に二つ目の利点は…】
経営者にとっての課題解決に向けた意見や提案に耳を傾け、
互いに尊重、そして共鳴感を持つことで、
メンバー経営者同士の信頼づくりにも貢献できる。
またどの経営者にとっても、課題解決に向けたプロセスに
関与することは、自社であり我が身になぞらえての判断となり、
今後の課題解決に向けたよい参考事例ともなる。
【三つ目の利点として…】
経営者にとっての学びのスピードを速めることができる。
企業が変化の激しい現代で生き残るためには、
素早く行動し、そこで得たことを次の行動に活かすことが重要。
ファシリテーションは、多くのメンバー経営者の経験や知識を
効率よくまとめることで、迅速な意思決定を可能にし、
問題解決のスピードを向上させることができる。
このようにファシリテーションは、経営者会議に限らず
関係者の納得感を高め、学びのスピードを速めることによって、
私たちの仕事や生活をより良くしてくれる技術。
変化の激しい今の時代において、
その重要性はますます高まっているのだ。
多様な考えを結集し、新しい価値を創造するための
ファシリテーションは、私たちが未来に向かって進むための
強力なツールとなるだろう。