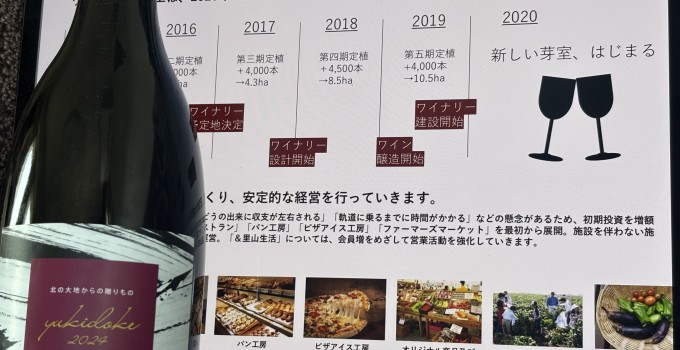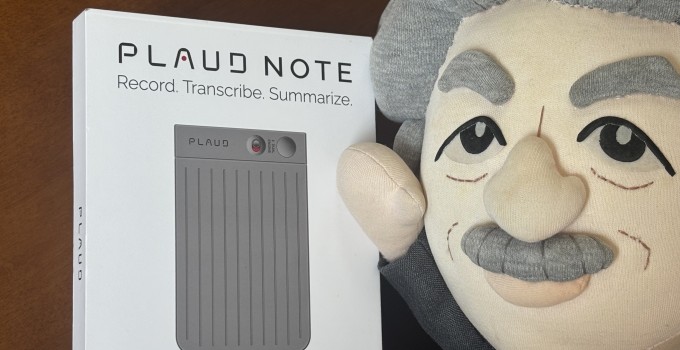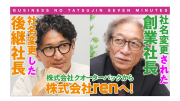08/18
2025
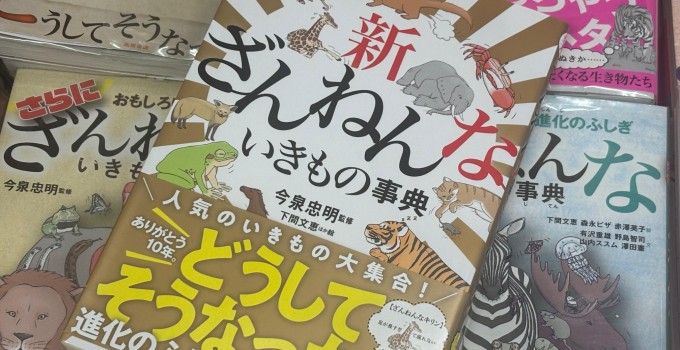
どのページを開いても、面白い! 『ざんねんないきもの事典』の狙い。
→本はどのページから開かれても面白くなければならない
→子供(読者)と親(購入者)の両方にアピールする
→子供が不完全に覚えても書店で見つけられるタイトルを目指す
(さすがのマーケティング!)
毎日電車に乗っていると、その見かけも行動も
ちょっと“ざんねんな人”と思うことも多いが…
今回は『ざんねんないきもの事典』の話。
【ざんねんなゾウ→大きすぎて毛を失う】
「地上最大の動物であるゾウ。
その巨体で、ライオンも追いはらえます。
でも、そのために多くのものを失いました。
まず毛。
大きいほど体に熱がこもりやすくなります。
そのため体温が上がり過ぎないように、全身つるっぱげです」
先日、あるテレビ番組で『ざんねんないきもの事典』シリーズや
『わけあって絶滅しました。』シリーズなど
ユニークな切り口で話題の書籍を手掛ける編集者
金井弓子さんの話を聴いたのだ。
この人気シリーズ、出版されてからもう10年になるというが、
そのタイトル含め、読者の心を掴む“面白い”を追求し、
本の隅々まで意図を込めて、
理論的に説明できる本づくりをしてきたという。
まさにマーケティングをしっかり考えての
必然的大ヒットだったのだ。
読者の心を掴む“面白い”の追求であり、
本の隅々まで意図を込めての詳細を以下に紹介してみた!
【金井弓子流ヒット本の法則】
その1 ◆どのページも面白くする
→本はどのページから開かれても面白くなければならない
子供は本を真ん中から突然開くことが多いため、
開いたページが面白くないとすぐに興味を失ってしまう。
そのため、どこを切っても同じ絵柄が出る“金太郎飴”のように、
どのページにもインパクトを持たせることが重要。
その2 ◆“面白い”と“ためになる”の両立
→子供(読者)と親(購入者)の両方にアピールする
子供向けの本は、読む子供と購入する親が
異なる特殊なジャンルである。
そのため、子供が“面白そう”と感じる要素と、
親が“子供のためになりそう”と感じる実用的な情報の
両方を盛り込む必要がある。
例えば、子供が惹かれるような面白いタイトルをつけつつ、
帯には“身近ななぜが全部わかる”といった
親向けのコピーを入れるなど、
常に両者の視点を意識してバランスを取っている。
その3 ◆記憶に残るタイトル
→子供が不完全に覚えても書店で見つけられるタイトルを目指す
子供が友達の本を欲しがる際、
正確なタイトルを覚えていないことが多い。
“命の図鑑”や“身の回りの不思議の本”のように、
内容の特徴を捉えた覚えやすいタイトルにすることで、
親が書店で探しやすくなり、販売機会を逃さない。
書店員がキーワードから本を特定できるような
タイトルが理想的である。
↓ ↓ ↓
うんうん、素晴らしい!
顧客のニーズやウォンツはもちろん、
そのプロセスにおける“選ばれる理由”も
もっと徹底して考え抜かなければならないわけだ。
このくらい細やかで戦略的なマーケティングでなければ
他を出し抜いてのヒットは生まれないということ。
令和時代のマーケティングはもっと複雑になりそうだ!