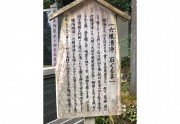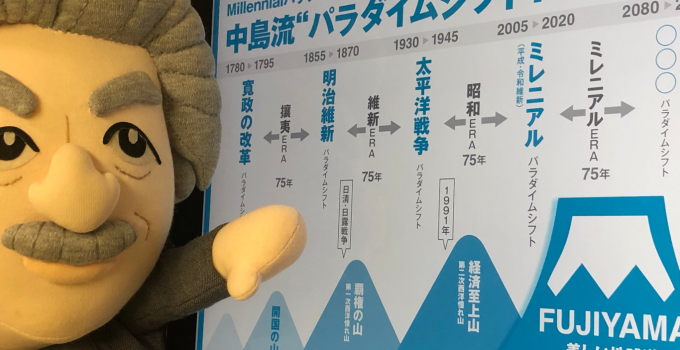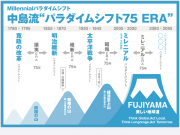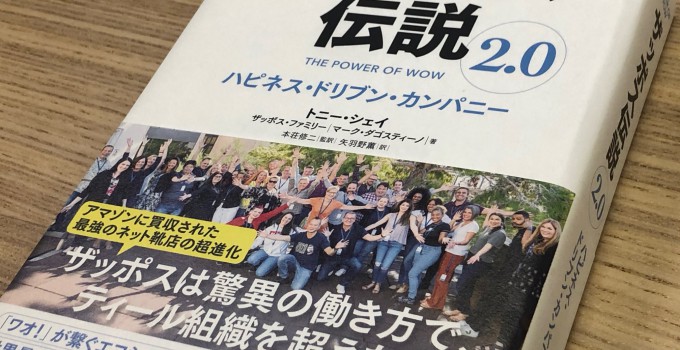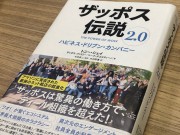11/24
2020

やっぱり“六根清浄”スポット、高尾山!?
また向かってしまった高尾山。
この光はパワースポット高尾山薬王院からの後光なのか!?
それともウルトラマンのスペシューム光線か!?
ハハハハ、そんなわけはないのは分かってはいるのだが
何かこの光が神々しいと思うのは私だけ!?
とにかく、紅葉の季節の高尾山は、
またひときわ気持ちのいいスポットなのである。
もしかしたら、日々の社会生活で俗っぽく染まっていた私たちを
あの自然の中を頂上を目指し一歩一歩前に進むうちに
いつの間にか身も心も清浄にしてくれているのかもしれない。
そういえばあちこちに六根清浄(ろっこんしょうじょう)の文字が
石に彫られていた。
ということで、調べてみると…
そう六根清浄とは…人間に備わった六根を清らかにすること。
五感に加えて、意識の根幹である“意根”も加えている。
眼根、耳根、鼻根、舌根、身根、意根の六つ。
この“認識”の根幹が、日々の生活で我欲などの執着に
次第にまみれていくのだという。
(うんうん、確かに)
そこでパワースポットでもある高尾山は(薬王院?)は
執着を断ち心を清めるスポットなのだと。
そうか、私がいつの間にか高尾山に足が向くのは
そろそろ執着にまみれ俗っぽくなったということの証なのかもしれない。
(結構頻繁に行きたくなるということは…)
これで私たちがこの高尾山であり、そのパワースポットに
なぜ惹かれるかが分かった次第。
私の好きな稲荷コースは特にコンクリートの道もなく、
常に自然と向き合えるコース。
(頂上を前にしての最後の約250段の階段がとにかくきついが…)
このコロナ禍には自然も満喫でき、最高のスポットということ。
登りながら“六根清浄”を念仏のように繰り返し唱えると
より効果があるという。
(本当だろうか!?)
そして稲荷コースは人とすれ違う度に
「こんにちわ」が飛び交うコースでもある。
これが山登りの“袖振り合うも他生の縁”である。
えっ!?“六根清浄”が“どっこいしょ”の語源でもあるって!?
てことは…
よし、次回は“どっこいしょ”を唱えてみよう!