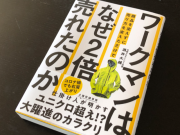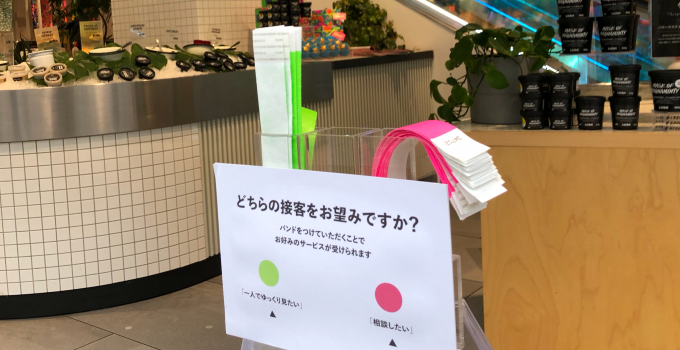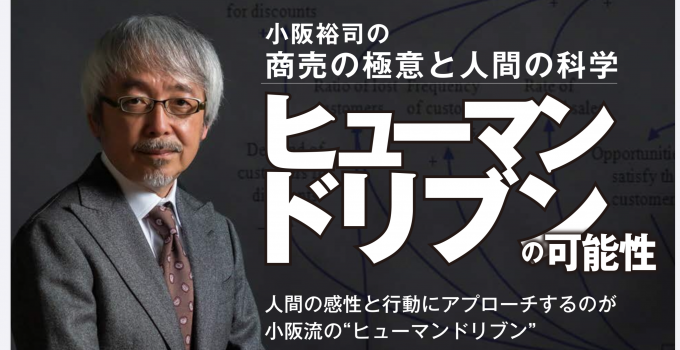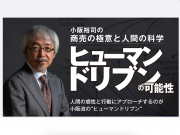10/26
2020

満を持して、“#ワークマン女子”OPEN
“#ワークマン女子”がこの10月に
1号店がオープンした。
ブランドに#がついているのも、“今時の女子向け”ということ。
9月に“ワークマンプラス”をビジ達で紹介したばかり。
それから一月も立たずして、“#ワークマン女子”が
横浜桜木町“コレットマーレ”にオープンしたので、
早速行ってきた。
その日はオープンして2~3日目だったのだが、
残念ながらお店の中には入れなかった・・・。
“女子向け”だから私は入れてもらえないのか?と思ったら、
そうではなく、コロナ禍で密にならないために
予約制をとっていたのだった。
“予約制”にするほど、注目の的ということだ。
実は“ワークマンプラス”にも女性客が半分ほどいる。
だが、“女子”を意識するほどの品揃えではなく、
ディスプレイも“女子”を意識していない。
そういう意味で、“#ワークマン女子”は
女子が入りやすく、サイズ構成も女子に合わせた
店舗なのだ。
書籍『ワークマンがなぜ2倍売れたのか』を読み
ワークマンプラスの1号店に行ったのだが、
この本の中に、女性専門のお店の展開についても
触れられていた。
“満を持して”とタイトルに入れたのはそういう理由からだ。
ワークマンのこだわりは“とにかく競争したくない”そうだ。
アパレルの中でも、作業服に特化してきた40年間。
作業服は、どちらかというと低価格帯、普及価格帯ながらも
高機能、すなわち、雨風にも強く、毎日洗濯しても丈夫で、
様々な便利な機能を付加することを求められてきていた。
このような商品を提供しつづけたワークマンは、
今まで競争せずとも拡がっていったのだ。
この技術は他社では真似のできないもので、
40年間の蓄積されたノウハウを、今注目のアウトドア用品や
スポーツアパレルに応用しているというわけ。
“ユニクロ”、“ZARA”、“H&M”、“GAP”などは
デザイン重視のアパレルブランド。
アウトドアアパレルは、“スノーピーク”や“モンベル”。
そして、スポーツブランドもたくさんあるが
どちらかというと高価格帯だ。
作業服専門店から発したワークマンはこれらと
“競争せずに安くて高機能”な商品を展開していくということ。
(“とにかく競争したくない”を実践しているわけ)
市場の隙間をみつけて、競争せずに
徹底的に攻め込んでいく戦略・発想は面白い。
それでいて、前回紹介したようにデータドリブンを
取り入れているので欲しいときに欲しいものが
あるということ。
そして、“ワークマンシューズ”の店舗展開も
見据えているという。
これまで培ったノウハウが活かされる
ワークマンの今後の展開に注目していきたい。
そんなことで、思わず・・・株を買ってしまった!!