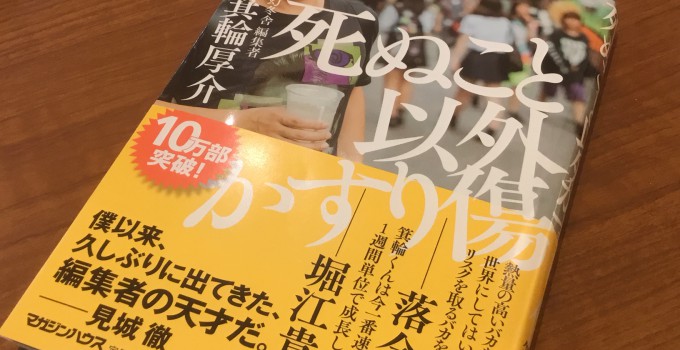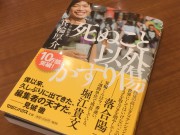02/25
2019

ペーシングクエスチョンの妙
「はい、目をつぶってください。
今から聞くことに当てはまる人は、2秒以内に手を挙げてください。
学校が好きな人?
勉強が好きな人?
部活が好きな人?
YouTubeが好きな人?
整理整頓が好きな人?
掃除が好きな人! ・・・いくつ手を挙げましたかね?」
のっけから「学校」って…何十年前の話!?
と思われた方、すいません。
実はこれ、先日私が『掃除の会』の広報担当として、
とある中学校でお話をさせていただいたときの冒頭部分。
1・2年生合わせて200人ほどの中学生を前に、
掃除をすることの意義や、
掃除の会が実際に行っている活動を紹介した。
中学生にしてみれば、知らないオジサンが突然表れて、
面倒くさい掃除(案外掃除が好きな人!で
手を挙げてくれた子も多かったけれど)
の功徳を説くのだから、ただ話しても仕方ない。
こんな時私がよく行うのが、
冒頭に挙げたような質問「ペーシングクエスチョン」だ。
ここで演者と聴く側の呼吸を合わせ、「聴くだけ」ではなく
「参加者」の意識を持たせる=ペーシングすることが、
その後の本題をきちんと聞いてもらうために大切だということ。
今回で言えば、出だしは中学生全員にとっての共通時候
「学校」で始めて、最後は本題の「掃除」に持っていく。
こうすることで、最後の質問の頃には
自分たちの思う“掃除”のイメージを
頭の中に描いてもらうことができるのだ。
この手法を私はよく取り入れていて、
経営者相手のセミナーや勉強会でも
「時流度チェック」という10問くらいの
ペーシングクエスチョンを冒頭に行うことが多い。
その時々の時流を取り入れつつ
(今なら「落合陽一」とか
「時価総額の高いプラットフォーマーは」とか・・・)、
セミナーの参加者全員が同じ土俵に上がれる質問をすることで、
セミナーの主題が自分ごと化される。
だから、中学生相手には中学生の目線に合った質問が必要だし、
経営者相手であっても、
参加者の世代とか業種業態によって
質問内容の調整が必要だろう。
「私は今のところ講演の予定がないから、関係ない」?
いやいや、これは実はプレゼンテーションの場や
ちょっとした打ち合わせでも使えるワザなのだ。
その場にいる人の意識をより能動的なものとし、
意味ある時間の演出とする「ペーシングクエスチョン」、
あなたも今日から使ってみては?