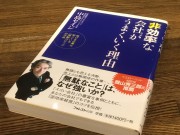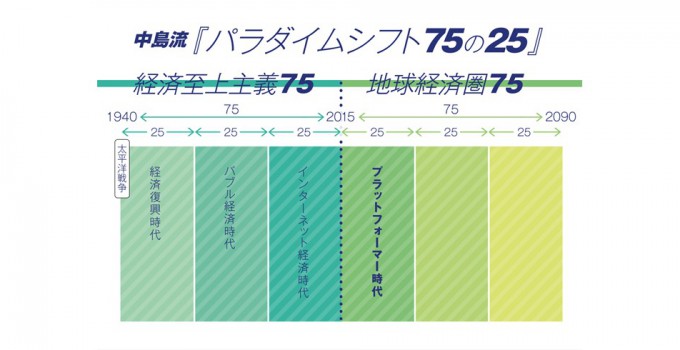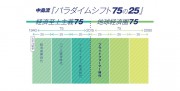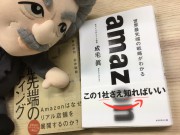10/15
2018

TGC北九州での“動中の工夫”
TGCとは何かご存知だろうか。
そう、若者たちから絶大な支持を集める
「東京ガールズコレクション」だ。
さる10月6日、今年が4度目となる
北九州開催のTGCを訪れてきた。
運悪く台風の影響で嵐の様相だったものの、
1万2千人もの若者たちが来場したという。
さて、無論ガールズでもなければ、
還暦すら超えたこの私が
なぜ突然TGCに行こうと思ったのか。
きっかけは、経営者仲間から誘われたことや、
実行委員長である村上社長との縁である。
そして「一度は見てみたい!行こう!」と
即座に決断した。
この「行く」という決断こそが大切なのだ。
これこそ、ビジ達でもよく取り上げる
キーワード“動中の工夫”だ。
この言葉は、私が敬愛する
鍵山秀三郎氏が発信する
“動中の工夫は、静中の工夫に勝ること
幾千億倍”からだが…(元々は白隠禅師の言葉)。
それはすなわち「論理的に理解しないと
行動に移せない者は、何も為し得ることが
できない」。
机上で考えるのではなく、行動するからこそ
次なる工夫が生まれ、本来の目的に向け
前進していけるということ。
この言葉の通り、TGC参加を決めたからこそ
私は3つのことを得ることができた。
ひとつは、TGCのその熱量を
直に体験できたこと。
なぜこのイベントは多くの若者たちを
惹きつけるのか、それはこの熱量が理由なのだ。
輝きを放つカリスマたちと、憧れる若者たち。
双方の熱量が相乗効果を生み、魅力的な場に
なっているのだと肌で感じることができた。
二つめは、会場に足を運んだからこそ、
さまざまな人と出会うことができたこと。
運営に関わる人たち、招待された経営者など、
今後のビジネスに関わるキーパーソンとの
出会いは足を運んだからこそであろう。
三つめは、道中の小倉で10年ぶりの
再会があったことだ。
ふと思い出し、以前お世話になった「卵家」の笠田社長を訪問してみた。
そこで運良く再会でき、貴重な話をできたのは
九州へ行くという決断をしたからこそである。
どうしても人は、損得を考えて行動してしまう。
だが、「動く」ということを決断することが、
学ぶことや得ることにつながるのだ。
動く決断をすることこそが、
さまざまなシナジーを生むということ。
ビジネスはとにかく“動中の工夫”!