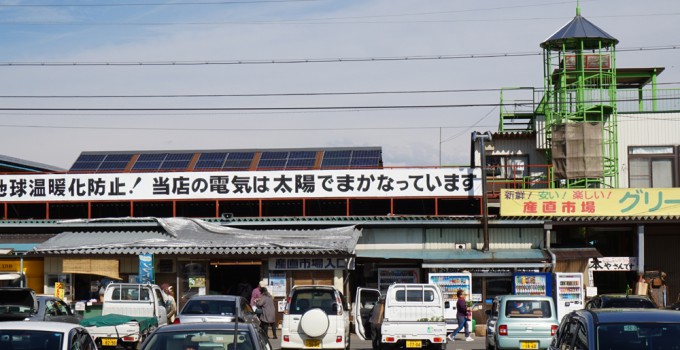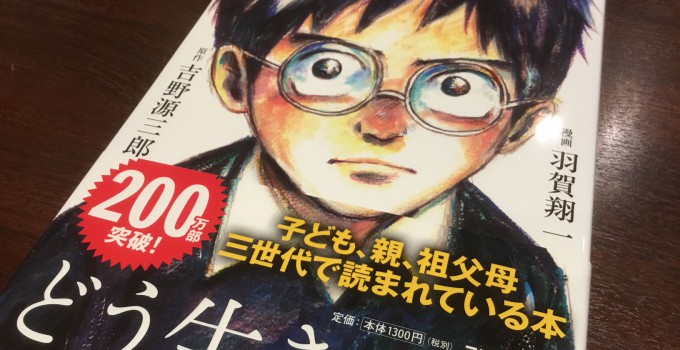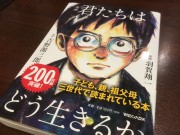07/09
2018

海外ツアーの副産物“difference”
“Our People Make The Difference.”
これは、海外ツアーで行ったウォルマートで、
スタッフのTシャツに書いてあったメッセージである。
(私は実にユニークなメッセージとして記憶したのだが…)
20年以上海外ツアーを続けていると、
思わぬところで国ごとの「違い」が見えてくるものだ。
今回のツアーでは、スペインのサン・セバスチャンとバルセロナへ足を運んだ。
フランスのシャルル・ド・ゴール空港を経由して
スペインへ行ったのだが、
この空港には2016年の海外ツアーで欠航トラブルに巻き込まれた苦い思い出がある。
今回も予定していた飛行機が1時間半(いや、2時間近く?!)も遅れ、
後ろの予定をリカバリーする必要があった。
どうにかして問題なくスペインに着いたものの、
これは今回の飛行機トラブルの始まりにすぎなかったのだ…!
問題は、美食の街サン・セバスチャンからバルセロナへ向かう日だった。
余裕を持って空港に着けるようホテルを早朝に出発した。
そして余裕を持って私たち11人は搭乗手続きの開始を待っていたわけだが…
電光掲示板にはまさかの「キャンセル」の文字が!
もちろん飛行機は欠航という意味なのだが、
キャンセルの文字だけで航空会社からのアナウンスはない。
カウンターへ詰めかけるも、
詳細を話せるスタッフはいない状態。
しばらくして、航空会社からリカバリーの提案があるのかと思ったのだが、
そこで言われたのは
「バスで向かうか、明日のこの時間の飛行機に乗るか」(何という究極の選択…)であった。
私も長年経営をしている身であるから、
その会社が掲げる理念が違えば、
働く人が大切にする価値観も大きく異なるということは理解している。
さらに国が違えば、文化的背景も合間って、
自分たちの「当たり前」が通用しないということも承知の上である。
しかし、今回利用したエア・フランスもイベリア航空も、
欠航のアナウンスが不十分で、そのリカバリーも利用者が納得しにくいお粗末な提案だったのだ。
冒頭で紹介した、ウォルマートの“difference”は、
「良い意味での違い」だが、
今回の「違い」は私たち日本人の価値観との大きなギャップなのだ。
これは、国の文化の違いでは済まされない“difference”ということ。
地球規模でとらえると、
当たり前だと思っていた価値観が、全く違うこともある。
このことを、身をもって学べたのだから、これぞまさに海外ツアーの副産物である。
私もまだまだ勉強中…!
これからもっと多くの“difference”に出会うことだろう!
(それにしても、日本人の美学や価値観は、
これからの地球における人類の継続に重要な役割を担っているのではないかと…)