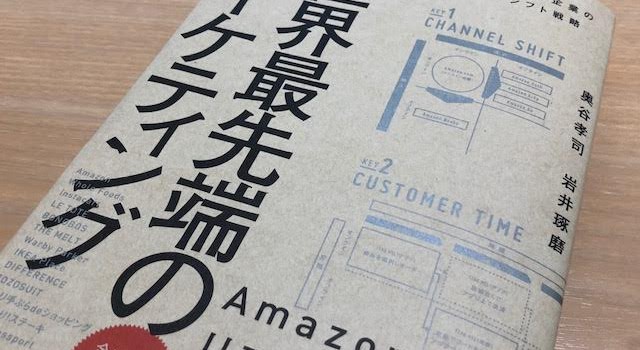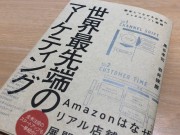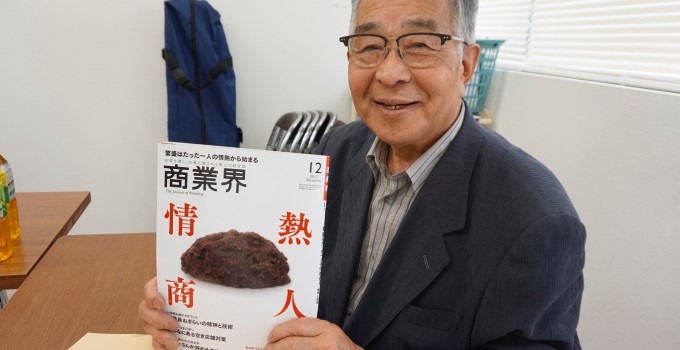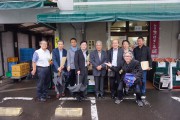06/25
2018

交流人口拡大と“秋保の活躍”
今、日本中の街や市が抱えている問題の一つに、
人口減が上げられる。
どこの自治体も、住民を増やすことだけではなく、
その地域の交流人口の拡大こそ課題だと認識している。
先日のビジ達でもご紹介した、
全国的に有名な“おはぎ”を販売している「さいち」。
その発祥の地である仙台市秋保地域は、
まさに交流人口拡大に向け良いモデルケースだと思うのだ。
私が進めているMemuroワインヴァレー構想は、
北海道十勝エリアである。
そこには帯広を中心に、さまざまな街や村があるが、
どんなに観光の中心地となる都市が頑張っても、
その周りの街が、なんらかの観光資源を持ち、
交流人口を拡大に向け展開していかなければ、
地域全体の盛り上がりは難しい、と感じている。
そこで先日お邪魔した、
仙台という100万都市を中心に、その可能性を考えてみた。
仙台から北へ30分のところには塩竈市があり、
その隣には風光明媚な松島という観光資源が。
そして秋保地区には、おはぎの「さいち」はもちろんだが、
すでにこの地域なればこその観光資源があれこれとあった。
「秋保ワイナリー」はその一つ。
私たち経営者の仲間である毛利社長が、
震災からどうやって地域の復活を牽引していこうかと考え、
立ち上げたワイナリーだ。
オープンして4年目ということもあり、
多くの人たちが訪れるスポットとなっていた。
また、ワイナリーから数分で移動できる秋保ヴィレッジも素晴らしかった。
元々は仙台で有名なお茶屋さんだったが、
結果的に農産物の直売所がありカフェがあり、
ガーデンを楽しむこともでき、さらにオリジナル商品も展開している。
このように、
秋保温泉という平安時代から続くエリアに、
新たな観光資源が生まれ、
交流人口拡大の大切な資源として活躍し始めている。
まさに、仙台を中心に、
衛星都市的に観光資源が周りに点在することが、
私の思う「これからの街づくり」の重要な要素なのである。
私自身はMemuroワインヴァレー構想を通して、
北海道帯広を中心にした周辺の町に、
新たな観光資源を増やし、
交流人口拡大に務めていこうと考えている。