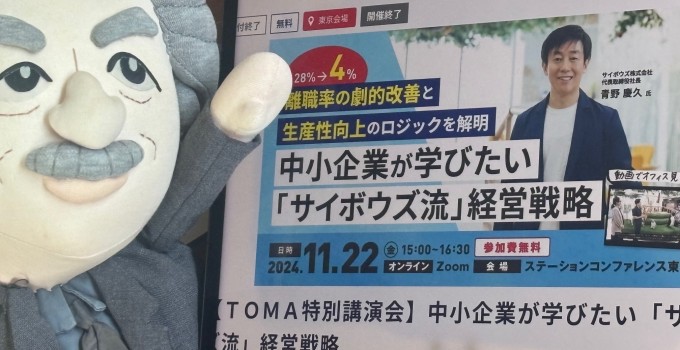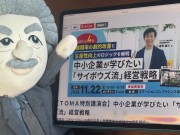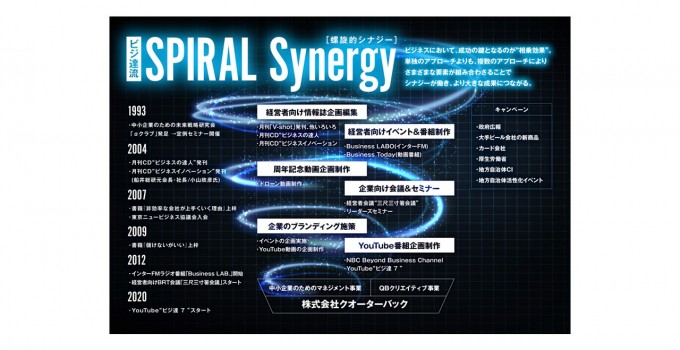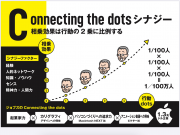12/09
2024

令和時代のリーダーを創る。 17年目の“リーダーズセミナー”
2024年度リーダーズセミナーが
恒例のフィナーレを迎えた。
この先週末の金曜日に、その“V&Tプレゼンテーション”は
リーダーズメンバーはもちろん
多くの経営者たちを迎えて開催された。
会場は今年も(株)フォーカスシステムズのセミナールーム。
(いつもご協力、ありがとうございます)
そしてリーダーズの“V&Tプレゼンテーション”のレベルが
毎年上がっているのは間違いない。
それを継続して見てくれている経営者の人たちも
それを語ってくれていた。
また、参加者同士の関係もより親密になっているようだ。
その後にその関係が続いてくれることを祈っている。
【このセミナーのポリシーは“体験とディスカッション”】
改めてこのセミナーが、いい結果に結びついている理由について
振り返ってみたいのだが。
なんといっても、“参加者みんなが主役”として捉え
互いに切磋琢磨できる環境をつくっているということだろう。
もう17年目を迎えた“リーダーズセミナー”なわけだが
実は、毎年進化している。
その進化を支えるポリシーは“体験とディスカッション”。
1年間で計9回の丸1日セミナーが受講でき、
その訪問先のユニークさと体験の面白さがポイント。
そしてみんなで繰り返すディスカッションに意味があるのだ。
これまでもこの“ビジ達”では紹介してきた体験だが…
◆石坂産業の視察と石坂典子社長の話を聴いて
1)何に注目したか
2)気づきは何か
3)どう日々に活かせるか
◆靖國神社境内のトイレを掃除して
1)何に注目したか
2)気づきは何か
3)どう日々に活かせるか
◆林香寺での坐禅と19代目和尚 川野泰周先生の
マインドフルネスセミナーを聴いて
1)何に注目したか
↓ ↓
◆日本でナンバーワンの道化師“クラウンK”の
パフォーマンスを観て体験して
1)何に注目したか
↓ ↓
そして「コーチング体験」や
「高尾山登頂体験」等も用意されている。
という“体験とディスカッション”が、
相乗効果も手伝って、
参加するリーダーズたちを成長させてくれているということ。
その1…コミュニケーション力が高くなる
その2…自分で考え行動するようになる
その3…プレゼンテーション力がつく
その4…ビジョンを語りその実現に向け行動できるようになる
その5…部下のことチームのことを考えれるようになる
そしてその6として、
多くのかけがえのない仲間ができるのだ。
すなわち、このセミナーの真価は、
体験を通して得られる実践的な成果と、
リーダーズ同士の濃密なディスカッションによる気づきにある。
令和時代を担うリーダーに必要な
知恵と人間力をも育んでいるということ。
ということで…
◆2025年度リーダーズセミナー参加メンバーを募集します!
経営者のみなさん、よろしくお願いします。