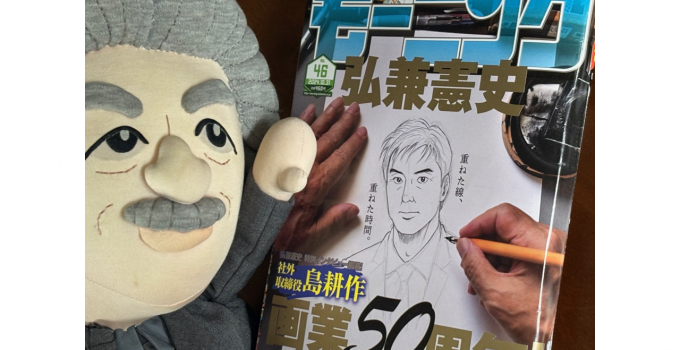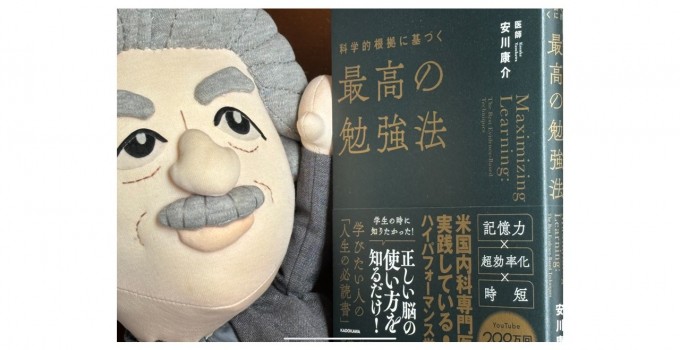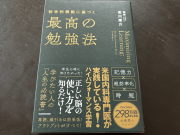11/05
2024

スマホが演出する、変革の16年。 その流れは、次なるステージへと!
えっ、忘れ物スマホ…1日600台!!
“紛失した”と持ち主が届け出た携帯電話の数は、21万9761点。
1日あたり600台余りに上るという。
(スゴ~い!)
一方、拾得物として警察に届けられたのは14万2450点。
“落とし主”の元には最終的に、
半数以上の12万222点が戻っているという。
(それもスゴい!)
みなさんもご存知と思うが、
アップルからiPhoneが発売されたのは2007年。
その5カ月前に、多くの記者たちの前で
“スマートフォン革命”のきっかけとなるプレゼンテーションを
あの“スティーブ・ジョブズ”がしてみせた。
(ちなみにスティーブ・ジョブズと私の誕生日は
1カ月しか違わない同年代である)
そして2007年6月29日に初代iPhoneが登場!
ただ残念ながら日本でのiPhoneの発売は翌年の2008年。
その発売から16年経ったわけだが…
1人2台持つ人も多く、とにかく多くのスマホが出回り
そこで1日600台も紛失することになっている。
果たしてこのiPhoneでありスマホの存在により、
私たちの生活は、そしてビジネスはどう変わったのだろう?!
【スマホによるトランスフォーメーション!】
2007年の登場以降、その普及速度と技術の進歩は
目覚ましいものがあり、
日本国内では全世帯の80%以上がスマートフォンを保有。
コミュニケーションや情報収集、
ビジネスのスタイルまでも刷新している。
今日、スマホを使えば、いつでもどこでも瞬時に
情報にアクセス可能。
この利便性であり効率化の追求は、
今も私たちの行動様式を改革し続けている。
まさにスマホによる“トランスフォーメーション”?!
いや、“パラダイムシフト”なのかもしれない!
その1 ◆スマホの普及と影響
スマホの爆発的な普及は、
私たちの生活やビジネスプロセスを変革することに。
その持ち運び可能なデバイスは、
一昔前には考えられなかった速さで情報にアクセスし、
通信手段としての役割を果たしている。
その2 ◆デジタル化とコミュニケーションの進化
デジタル化の進展により、映像、音楽、書籍などの
提供の仕方も、売り方も大きく変わることに。
この変化に伴い、ソーシャルメディアの普及も急速に進行し、
コミュニケーションの枠組みが大きく変わることに。
その3 ◆新たな決済方法とクラウドの役割
電子決済の普及により、
スマホは支払い手段としても地位を確立。
キャッシュレス化の進展とクラウド技術の進化は、
私たちの生活をさらに便利で快適なものに導いている。
クラウドはデータ管理の負担を軽減し、
柔軟なビジネスモデルをも可能にしている。
とにかく、私たちのライフスタイルもビジネスも
大きく変えたのは間違いない。
しかし、この便利さは一方で新たな課題も生み出している。
匿名性により誹謗中傷が増え、
さまざまなトラブルであり事件も起きているのだ。
便利なもの、効率の良いものは、
易学で言うところの“陰と陽”の関係ということだろうか?!
次なる便利さ、効率化を生み出してくれる注目の“AI“も
メリット・デメリットを合わせ持っている。
私たちがそれを踏まえてどう活かすかということなのだろう。
(この“陰と陽”については、改めてこの“ビジ達”で語ることに!)