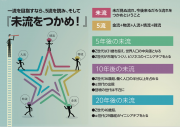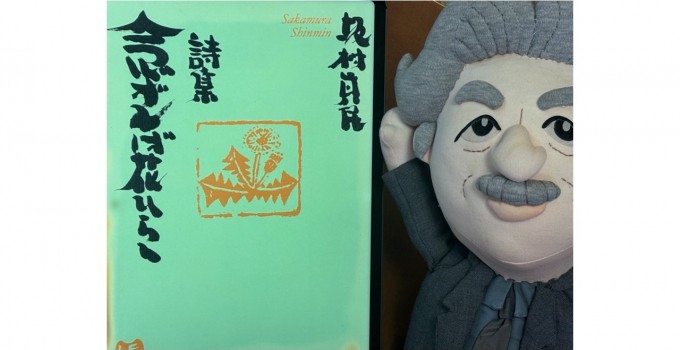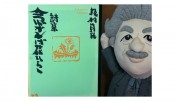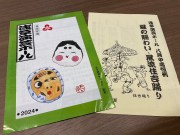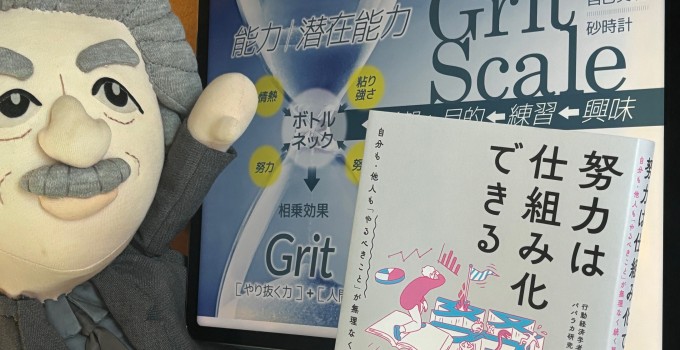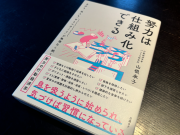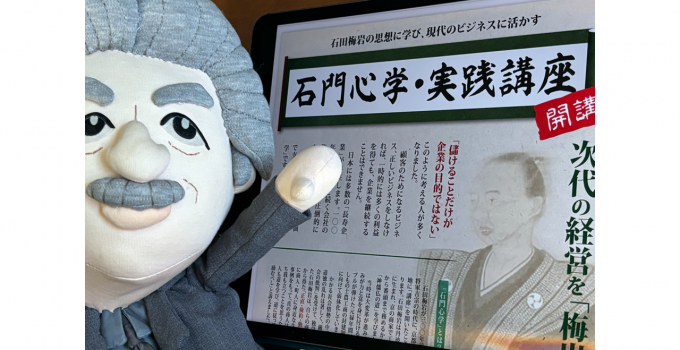08/26
2024
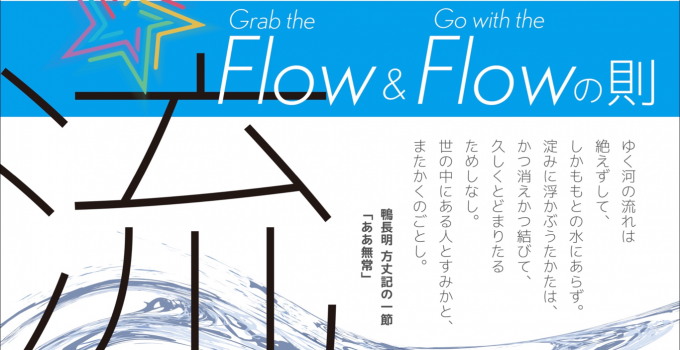
VUCA時代のリーダーシップ “Grab the Flow,Go with the Flow!”
このところの“時流観測所”で紹介された
時流のキーワードを紹介しよう。
このキーワードをあなたはいくつ説明できるだろうか?!
【1】石丸構文(石丸伸二という人を説明できればOK)
【2】親子留学
【3】JREバンク
【4】洗濯のアライさん
【5】ローリングストック
【6】ハラカド
【7】ラピダス
(→解説は後半に)
近年“VUCAの時代”という言葉を耳にすることが多くなった。
この言葉も時流のキーワードとして
紹介したことがあったと記憶するが…
その意味は、将来に対して予想が困難で不確実性が高く、
先が見通しづらい時代であることを語っている。
とはいえ、先が見通しづらいから何もしない人はまずいないはず。
何らかの動きはしなければならないわけだ。
そこでリーダーたるもの“Grab the Flow,Go with the Flow”。
「流れをつかみ、流れに乗れ!」
すなわち、時流をつかみ、時流に乗れ!ってこと。
いかにその“時流”をビジネスに反映させるかである。
ドラッカーも「すでに起こった未来」という表現で
“重大な変化は、価値観の変化、認識の変化、目的の変化など
予測不能なものの変化によってもたらされる”と。
(私は“すでに起こっている未来”と発信しているが…)
【“時流観測所”を参考にして、流れを察知しよう!】
“ビジネスの達人”webサイトトップページの右袖に
冒頭に紹介した“時代の流れを定点観測-時流観測所”がある。
2週に1回の更新で、毎回7個の時流のキーワードを紹介している。
これを参考にして“すでに起こっている未来”を
先取りしようではないか。
↓ “時流観測所”はこちらから
https://bt.q-b.co.jp/trendcheck/#/home
時代の流れを定点観測 時流観測所
ということで、冒頭に紹介した7つのキーワードの解説。
【1】石丸構文
→都知事選に出馬した元安芸高田市長の石丸伸二氏と
コメンテーターとの噛み合わないやり取りに注目
(20代30代の投票では石丸氏がトップだった)
【2】親子留学
→留学も海外体験・英語教育の定番の取り組みの一つだが、
子ども一人ではなく親子で一緒に海外へ行く展開が多い
【3】JREバンク
→申し込みが殺到して金融関係者をも驚かせたのが
JR東日本のデジタル金融サービス
(残念ながら、私は口座開設に失敗している)
【4】洗濯のアライさん
→ついに住友商事が洗濯代行サービス“洗濯のアライさん”を開始
前日にLINEで予約し洗濯物を玄関に置いておけば、
その日のうちに洗って畳んで返却されるという
【5】ローリングストック
→食の防災対策として、普段食べている消費期限が長めの食品を
多めに準備し、食べた分だけ買い足すという展開
【6】ハラカド
→原宿にオープンした“ハラカド”は、新たな文化発信拠点となれるのか?!
【7】ラピダス
→“日の丸半導体の復活”を掲げて、約1兆円の税金が投入され
2022年11月に設立された日本の半導体企業。
世界最先端となる“2ナノ”世代の半導体量産を目指す国策企業だ
この令和時代の私たちのビジネスにおいて大切なことは、
将来どんなイノベーションが起き、
どんな社会生活の“当たり前”が創り出されるのか…
という仮説(将来予測)に基づき、いま何をすべきか意思決定すること。
この仮説をより確かなものとするためには、
“すでに起こっている未来”を察知し、いかに“時流”を捉えるかである。
“Grab the Flow,Go with the Flow!”
そういえば…
私は「一流を目指すなら、5流を読み、そして“未流をつかめ!”」
まで発信していたことを思い出した!