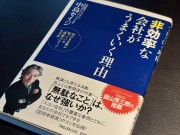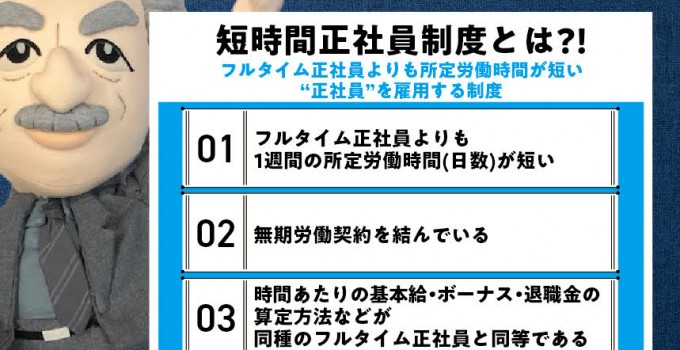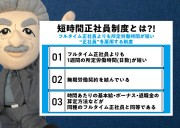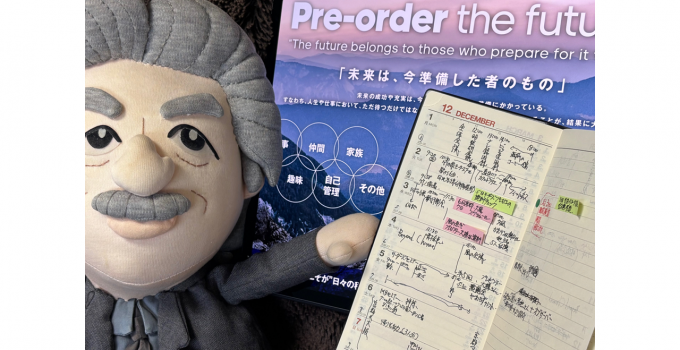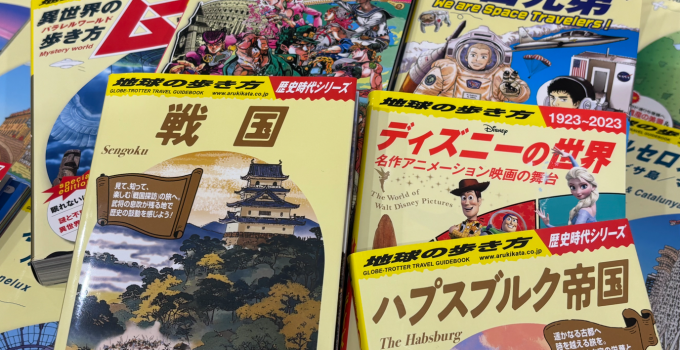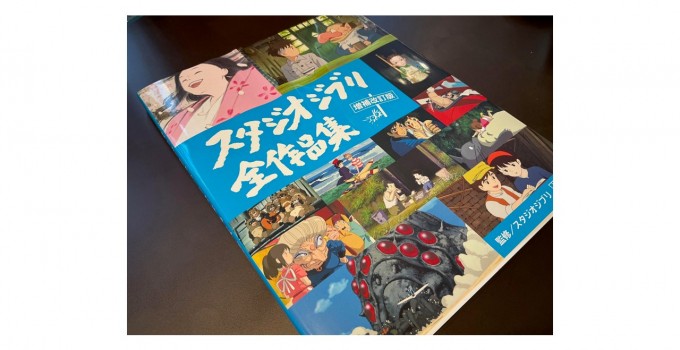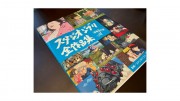12/15
2025

鍵山秀三郎相談役から学ぶ-part 3 「掃除には、意義と効用がある!」
鍵山秀三郎『凡事徹底』
テーマ/『掃除の意義と効用』
「掃除にはさまざまな意義と効用があります。
そのなかで、とくに私が感じるのは次の三つです。
(1)掃除は自己を確立することができる。
目の前の問題を受け止め、自分で考えて行動するようになる。
(2)掃除は周囲の人に配慮して、
いつも先のことを考えるようになる。
(3)掃除は人と時間・行動を共にするため、
目標と価値観を共有できる。」
(鍵山秀三郎著『凡事徹底』「一日一話」PHP研究所刊)
改めて鍵山相談役の発信してきたことを、
この『凡事徹底』を材料に振り返っているわけだが…
以下、拙著『非効率の会社がうまくいく理由』より
「私一人で始めた社内の掃除も、少しずつ協力する社員が現れ、
イエローハットになってからは、大きな変化が出始めました。
まず社風がよくなったのです。
掃除は普通、共同作業で行います。
ゴミを掃くのも、それをゴミ袋に入れるのも
そのあとを片付けるなども
みんなと連携して行うことで連帯感と協調性が生まれ、
社内の人間関係がとてもよくなったのです。
社員一人ひとりの表情が明るくなり、
人によっては見違えるほど人相がよくなった人もいます。
当然、家族や周囲の人にも
やさしい気遣いができるようになります。
こうした変化はお客様や取引先への対応にも現れました。
私がそれに気づき始めてから当社の業績も
目に見えて上がっていきました」
【鍵山相談役がたった一人で始めた“掃除”は…】
20年を過ぎた頃、イエローハット全体に広がり、
“掃除をする社風”が取引先やお客様からも
評価されるようになった。
その頃になると、社外の直接仕事とは関係のない人までが
鍵山氏の元に“トイレ掃除の方法を教えてほしい”と
訪ねてくるようになったという。
そしてフランチャイズのお客様を見つけるのに、
広告を掲載したり、営業活動を行うことはなく、
すべて“イエローハットと取引をしたい”と希望する顧客や
すでに取引している会社からの紹介だけで
ビジネスが成り立ったというのだ。
↓ ↓ ↓
“日本を美しくする会”には、「なぜトイレ掃除なのか?!」の
以下の5つのバリューがある。
01◆謙虚な人になれる
どんなに才能があっても、放慢な人は
人を幸せにすることはできない。
02◆気づく人になれる
世の中で成果をあげる人とそうでない人との差は、
無駄があるか、ないか。
無駄をなくすためには、気づく人になることが大切。
03◆感動の心を育む
感動こそ人生。
できれば人を感動させるような生き方をしたい。
そのためには自分自身が感動しやすい人間になることが第一。
04◆感謝の心が芽生える
人は幸せだから感謝するのではない。
感謝するから幸せになれる。
05◆心を磨く
心を取り出して磨くわけにいかないので、
目の前に見えるものを磨く。
特に、人の嫌がるトイレをきれいにすると、心も美しくなる。