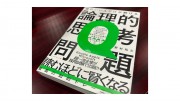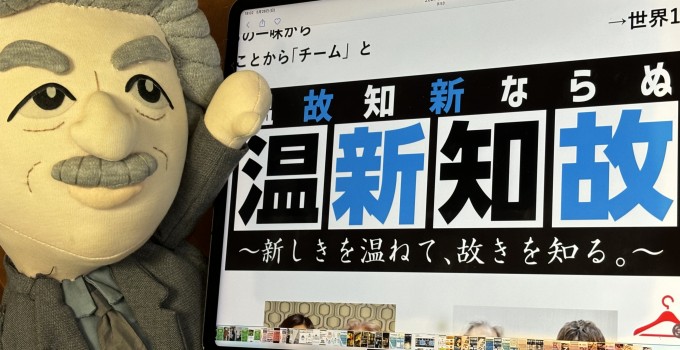06/10
2024
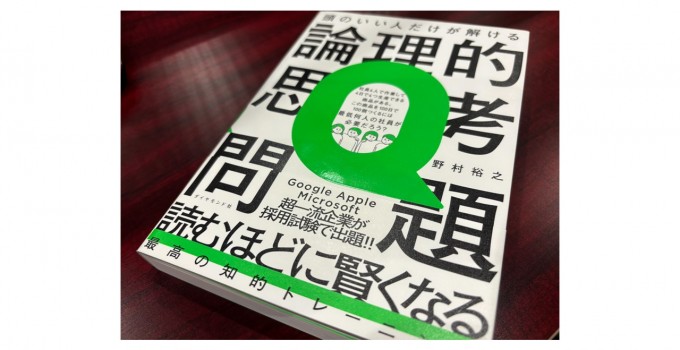
『頭のいい人だけが解ける論理的思考問題』 野村裕之著
「論理的思考問題」のタイトルに惹かれ手にとった書籍。
すべてが加速する時代にあっては、
それまでの常識であり考え方は通用せず、論理的思考により
次なる可能性を自分なりに考え発想し、決断する必要がある。
中島流の「“いい経営者”のマンダラチャート」にも
8つのサブテーマの一つとして“ロジカルシンキング”が登場している。
これからの時代における経営でありビジネスには、
必要不可欠な要素であることは間違いない。
この本の“はじめに”にあたるところから…
「あなたは論理的な思考ができる人でしょうか?」とし、
「ハーバード大学やイェール大学といった
世界的超名門校の大学生ですら全問正解は17%しかいませんでした。
あなたはわかるでしょうか?」
という私たちを刺激する投げかけも。
【以下の3問、それぞれ5秒で答えてください】
→1問目
ボールペンと消しゴムは合わせて110円。
ボールペンは消しゴムより100円高い。
では、消しゴムの値段は?
(あれっ、これってあの経済行動学でもあった問題?!)
→2問目
社員4人で作業して、4日で4つ生産される商品がある。
この商品を100日で100個つくるには、
最低何人の社員が必要?
→3問目
あるイベントで、開始時は観客が1人だったが、
1分ごとに2倍に増え、12分で会場が満員になった。
観客が会場のちょうど半分を占めたのは、
開始から何分後?
これら3つの問題は、「論理的思考問題」とも呼ばれている。
特別な知識を必要とせず、
問題文を読んで論理的に考えれば答えが導けるという。
要するに“考える力”さえあれば誰でも解ける問題。
知識や情報など複雑な事象を概念化し、
抽象的な考えや物事の本質を理解するためのスキル。
Google、Apple、Microsoftといった世界的企業も、
こういった問題を入社試験で出題しているとも。
(→この3問の答えは、本を読んで確認してね!)
【これら“論理的思考問題”で“5つの能力”を高められる?!】
論理的思考問題で高められる“5つの能力”として
論理的思考、批判思考、水平思考、俯瞰思考、多面的思考が
挙げられています。
【1】論理的思考
事実や情報を冷静に見抜き、順序や法則を整理して、
矛盾のない適切な判断をする力。
【2】批判思考
前提となる情報や直感に対して疑問を持って考え、本質を見抜く力。
【3】水平思考
既成概念や常識、先入観、過去の事例などにとらわれることなく、
フラットな視点で自由に発想する力。
【4】俯瞰思考
現状の視野や細部にとらわれることなく、視座を高めて物事を捉える力。
【5】多面的思考
物事に対して一つの視点からではなく、複数の立場や角度など
あらゆる側面から考える力。
これら問題にチャレンジすると…
“論理的思考が高められる!”に期待したいわけだが…果たして?!
350ページにも及ぶ本なので、多くの問題が詰まっていて
いろいろ試行錯誤していると、確かにいろいろな思考が
刺激されていることは間違いないようだ。
ちなみに、タイトルの“頭のいい人だけが解ける…”という表現は
IQ値の高くない私にとっては、
挑戦的な言葉に聴こえてならないのだが…