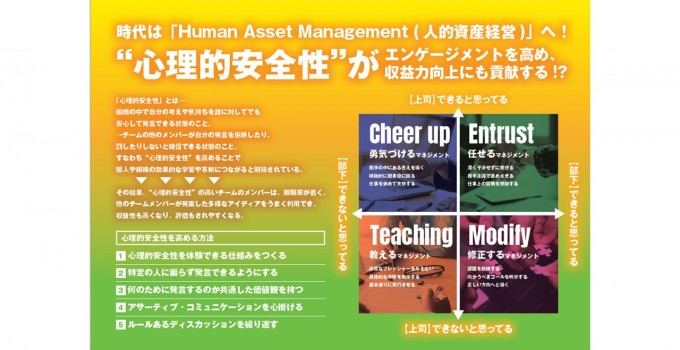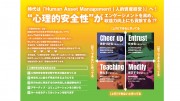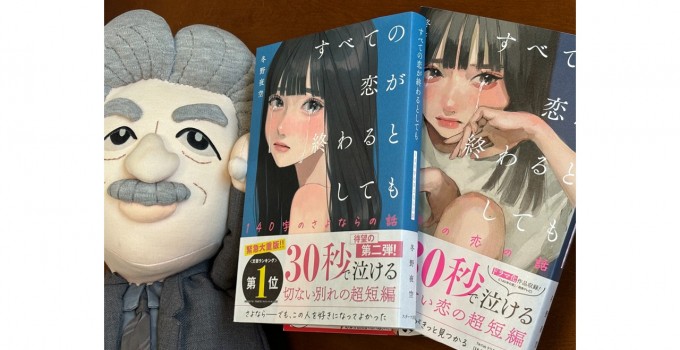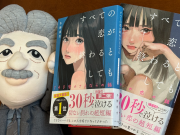01/22
2024
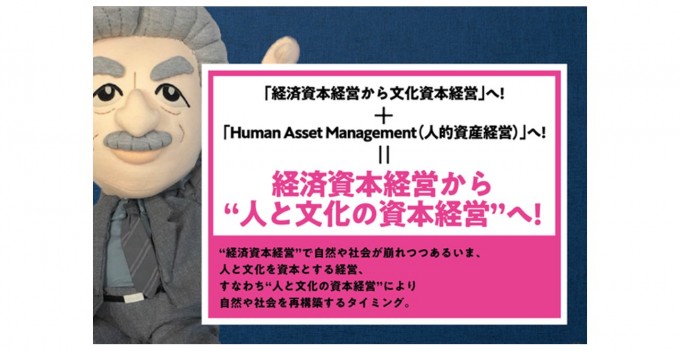
これまでの経済資本経営から “人と文化の資本経営”へ!
いつのまにか自然や社会と分離し、停滞しつつある経済。
環境問題や格差社会も、この“経済資本経営”がもたらしているに違いない。
まさに“経済資本経営”で自然や社会が崩れつつあるいま、
人と文化を資本とする経営、すなわち“人と文化の資本経営”により
自然や社会を再構築するタイミングなのでは?!
ということで今回は「人と文化の資本経営」について語りたいわけだが…
1年ほど前に「令和は経営をデザインする時代!」として、
“経営をデザインする”とはどういうことなのかを発信した。
↓ ↓ ↓
歴史的にも“デザイン”という概念の中で捉えられてきたことは、
「人から考える」こと、そして「美と調和を大切にすること」が
重要な要素とされている。
「人から考える」とは、その商品・サービスに関わる人を
想像することが求められる。
つまり、使う人、サービスを受ける人のことを常に考えるのはもちろん、
商品をつくる人、サービスを提供する人、その双方を幸せにすることを
目標にした行為…とある。
そして「美と調和を大切にすること」に関しては…
歴史の中で“美しい”とされてきたものは、
それに関わるさまざまな要素との関係性が
最適化されてきているというのだ。
さて、「経営をデザインする」において“人から考える”とは?!
お客様でありエンドユーザーはもちろん、自社のスタッフであり
協力関係者も幸せにすること…となる。
“美と調和を大切にすること”とは?!
企業活動の美しさであり、関わるさまざま要素との最適化となる。
すなわち、社会課題や地域との関係に求められる美と調和?!
ひいては、いいブランディングに通ずるというわけだ。
↓ ↓ ↓
うんうん、素晴らしい捉え方。
(自画自賛だが…)
今こそ、「人と文化の資本経営」を前提として
経営をデザインするときということ。
【豊かな“人と文化の資本”を持った企業が注目される!!】
[経済資本経営から文化資本経営へ!]
+
[Human Asset Management(人的資産経営)へ!]
=[経済資本経営から“人と文化の資本経営”へ!]
いま「“経済資本経営”から“文化資本経営”へ!」との発信を
出版物でも目にするようになり、“人的資産経営”というキーワードも
度々耳にするようになった。
(私もあちこちで発信してるわけだが…)
ということで、この二つを融合すると「人と文化の資本経営」となる。
ある書籍には、日本は成熟国として、
技術立国から文化立国へと転身すべきだとも書かれていた。
まさに日本の文化は地球規模でみても、類い稀なる文化といっていいだろう。
今回は“日本の文化資本”を言いたいのではなく、
企業における“人と文化の資本”についてのこと。
今こそ、「人と文化の資本経営」を前提として
令和の経営を再デザインするとき。
◆“人と文化の資本経営”をデザインするための7つのファクター
【その1】ビジネスモデルであり事業収支
【その2】事業構成と組織づくり
【その3】DX化とリスキリンング(生産の向上)
→ここまでの3つは経済面優先のファクター
以下は、
“人と文化の資本”を意識したファクター
【その4】社会課題への取り組み
→パーパスとのリンクも重要で、社会性ある取り組み
【その5】well-being経営
→働く人たちの肉体と精神面、さらに社会的な面でも満たされるように
組織の環境を整え、社員の意欲やエンゲージメントを高める経営
【その6】地域との関係づくり
→これからは何らかのカタチで地域にも貢献し、その関係性を上げることが、
企業としても働く人たちにとってもいい環境づくりとなる
【その7】ブランディング
→商品やサービスはもちろん、上記“人と文化の資本”を意識したブランディング
ということでこれからは、
より豊かで魅力ある“人と文化の資本”を持った企業が
注目されるのは間違いないだろう。