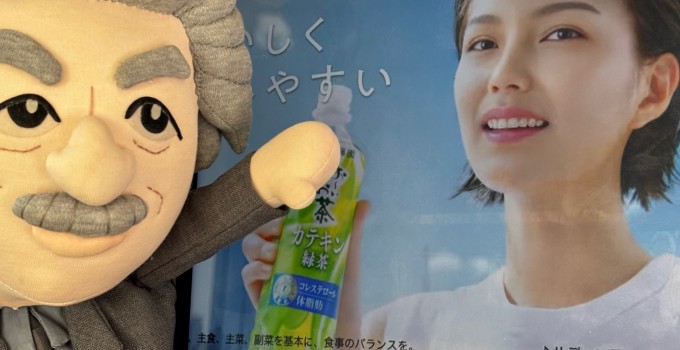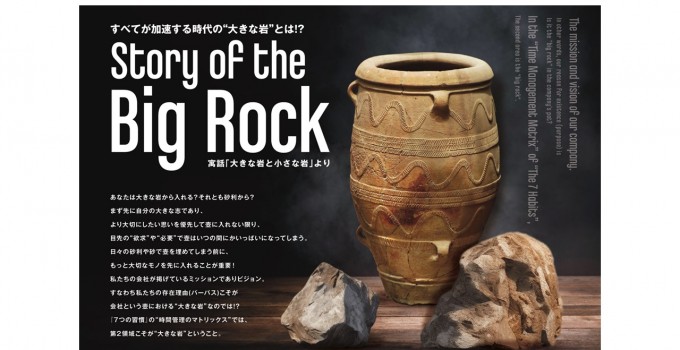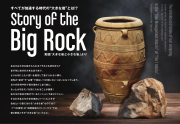12/11
2023

リーダーズの成長とその未来が見えてくる! 16年目のV&Tプレゼンテーション
2024年リーダーズセミナーV&Tプレゼンテーション優秀賞は…
御園建設、○○○さん。
そして最優秀賞は…石坂産業、○○○さん。
という結果だったのだが、私にとっては14人のプレゼンテーションは
それぞれの今にリアリティがあり、すべて良かった。
あとは絵に描いた餅にしないよう、実践して欲しいだけ。
プレゼンテーションでは、送り出してくれた経営者の方が、
それぞれのプレゼンの後にコメントをいうのだが、
みなさん嬉しそうにコメントをされていたのが印象的だった。
【経営者15人、リーダーズメンバー14人が勢揃いでフィナーレ!】
毎年恒例のリーダーズセミナーV&Tプレゼンテーションを
12月1日金曜日に、フォーカスシステムズのセミナールームで開催。
(株式会社フォーカスシステムズさんに感謝!)
第16回目の今回は経営者15人、リーダーズメンバー14人が揃っての
“V&Tプレゼンテーション”となった。
経営者の方々も、12月の忙しい中、しっかり時間をとってくれたのだ。
リーダーズのメンバーは、緊張の中にもその成果を発信しようと
そのプレゼン資料もプレゼンの仕方も、
いろいろとチャレンジングな展開をしてくれていた。
参加メンバーの初顔合わせから9カ月、
この8回のセミナーで本当にいい関係づくりをしてくれた仲間たちなのだ。
【個別カウンセリングから始まり、セミナーは毎月の8回!】
3月はまずの個別カウンセリング
4月 1)オリエンテーション& QB山田社長によるつながりのファシリテーション
5月 2)靖國神社境内のトイレ掃除研修
6月 3)19代林香寺住職によるマインドフルネスセミナー
7月 4)石坂産業視察&石坂典子社長セッションセミナー
8月 5)吉田 有コーチによる“コーチングを学ぶ”セミナー
9月 6)高尾山を登り自分を整え&コーチングのフォローセミナーも
10月 7)アフタヌーンティーBUS体験セミナー&バックキャスティング思考
11月 8)石川酒造視察と18代当主石川彌八郎セミナー
→V&Tプレゼンに向けた個別カウンセリングも
12月 9)V&Tプレゼンテーション
【同じ釜の飯を食べた仲間として…脳内ホルモンのオキシトシンが??】
実はこのところのリーダーズセミナーでは、
グループディスカッションをより多く取り入れている。
視察体験したら、セミナーで学んだら
1.何を感じたか、得たものは? 2.今後にどう活かすか
を毎回グループでディスカッション。
そして、グループでのディスカッションの内容をまとめ、
1人が代表してみんなへのシェア発表となる。
今回が16回目のリーダーズセミナーということもあり、
このディスカッションを多くのリーダーズメンバーと毎年繰り返してきた。
その結果がこのディスカッションの仕方と発表スタイルになったということ。
これが中島流の『コンピテンシー・ディスカッション』である。
→『コンピテンシー・ディスカッション』については
https://bt.q-b.co.jp/synergysp/15824/
このディスカッションの繰り返しこそが、
同じ釜の飯を食べた仲間となるわけだ。
すなわち同じ釜の飯を食べた時と同じように
脳内ホルモンのオキシトシンという物質が分泌され、このホルモンにより
相手に対する不安や疑いの心を抑制し、
信頼感を深めてくれる効果があるというわけ。
(よく言われていることを書いてみたのだが…)
これが本当かどうかは分からないが、
いい関係が築かれていることは間違いない。
このリーダーズセミナーでの毎回の体験やセミナーによる
ディスカッションの繰り返しが、何度も意見を交換し合った仲間として
互いに刺激し合い、学び合い、本当にいい関係が創られるのだ。
ぜひこの関係を今後も続けて欲しいと思うのだが…果たして?
さて来年はこのリーダーズセミナーに、何人参加してくれるだろう。
20人以上の参加者になったらどうしょう?!
2チームに分けて展開するしかないだろう。
まぁ、大体こんな心配は徒労に終わることが多いわけだが…