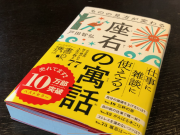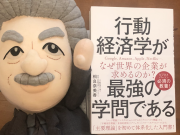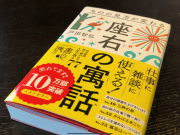11/20
2023

mont-bell(モンベル)が、小学生の“通学ブルー”を解消! “発想のジャンプ”が新たなビジネスを創造する
伝統の人工皮革・牛皮製のランドセルが、
いま、ナイロン・ポリエステル製に置き換わろうとしている。
小学生はとにかく重いランドセルを背負わされているわけだ。
今どきの子供が背負わされているランドセルの重さは、
2022年度で4.28kgに達し、半数以上が明らかに負担を感じているという。
そしてそこにiPadと水筒も持っていく生徒はなんと5~6kgだと。
ちなみに私が背負う吉田カバンのバックパックは通常7キロ以上。
かなり重い方だが、セミナーやプレゼンに使うiPad Proから
さまざまなコネクター、そしてコンテンツづくりのための書籍をも
常に持ち歩いているからだ。
とはいえ、私は大人である。
小学生にとっての5~6キロはかなりの負担であることは間違いない。
そんな中、“発想のジャンプ”と新たな組み合わせにより
課題解決ビジネスが展開されつつある。
【アウトドアメーカーのmont-bell(モンベル)が創る、多機能なランドセルの意味】
少し前にもビジ達でmont-bellの辰野会長を紹介したばかりだが、
ターゲットは違えども、さすがその道のプロがそのノウハウを活かして
提案するランドセルはこれまでとかなり違っていたようだ。
あるニュース記事に「いま総合アウトドアメーカーのmont-bellが、
新しいタイプのランドセルを制作、従来のランドセルとは違った
デザイン・コンセプトで話題を呼んでいる」と。
mont-bellが発表した通学用バックパックは「わんパック」。
2021年に富山県立山(たてやま)町からの依頼で創られた通学用バッグだが、
反響を受けて2022年12月から一般販売もスタートし、
23年度分は早々に完売したという。
なんと一般用の“わんパック”の価格は1万4850円。
(ネーミングも面白いし、保護者には手頃な価格!)
ところでなぜ総合アウトドアメーカーmont-bellが
ランドセルを作るに至ったのか?!
実は、アウトドアを楽しむフィールドが多くある立山町とは
その付き合いも長く“包括連携協定”を結んでいた。
ということからmont-bellがお手伝いすることになったようだ。
そもそも、なぜ立山町はオリジナルの通学用バッグの開発を考えたのか。
入学準備をする保護者などの経済的負担を軽減したい。
そして軽量化によって児童の身体的負担の軽減も考慮してのこと。
新入学児童に対する通学用リュックサックの無償配布についても
検討していたという。
ちなみに2022年4月入学のランドセルの平均価格はなんと5万6425円。
(ゲゲ〜高〜い!)
セイバンの“天使のはね”シリーズの売れ筋は6〜7万円。
ミキハウスの“コードバンランドセル”に至っては、なんと33万円。
55%以上の人たちが5万5000円以上のものを購入しているという。
【今こそ次なるステージへ、“発想のジャンプ”とチャレンジを!】
これからは「課題を発見し、意味を創出する」時代だと繰り返しているが、
これまでのビジネス領域であり市場にこだわっていてはその先はない。
日々の時間の使い方も、ビジネスの取り組み方も変えないことには…
今回の立山町にとってもmont-bellにとっても、
新たなチャレンジにより新たなステージがそこに生まれたわけだ。
先にビジ達で紹介した、“墓石余りのアップサイクル”の事例もそうだが…
今までは産業廃棄物として捨てていた墓石の余りをアップサイクルすることで、
墓石製造会社とは無縁だったレストランや高級旅館との取引に
辿り着いたという。
これまでにない発想と新領域へのチャレンジが、
新たなビジネスマッチングをも実現したわけだ。
まさにこの“発想のジャンプ”がないことには次なるステージは見えてこない。
この事例でも、あるビジネスコーディネーターのような人物が介在していたが、
多くの情報が集まるところに出向き、さまざまな人たちとの交流無くして
新たなチャンスも次なるステージもやってこないということは間違いない。