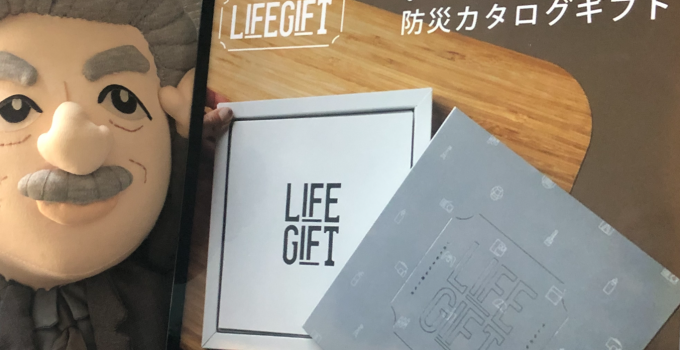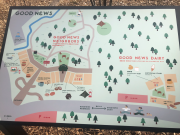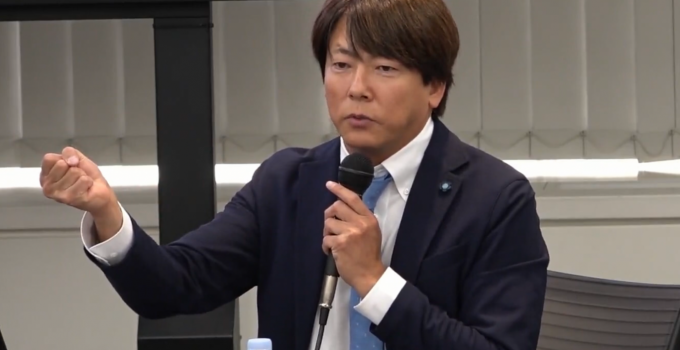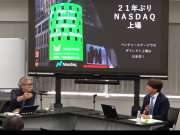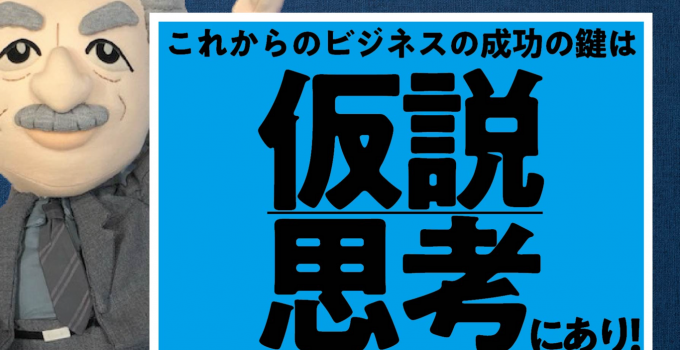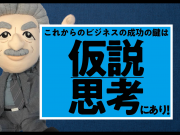07/03
2023

“運動脳”のためにもおすすめ「599高尾山」! 登らずして高尾山を知ることなかれ!?
高尾山は何度登っても飽きないし、いろいろな意味で程よい山なのだ。
自然を体感し、季節を感ずるにもいい。
程よい達成感と運動のためにもいい。
パワースポットとしてエネルギーをもらうにもいい。
仲間と共にそのプロセスを楽しみながら時間を共有するにもいい。
599メートルは、山って言うほどの山でもないかもしれないが…
その高さであり東京の中心部からの距離感がまたいいのだ。
私などは、新宿まで10分で行け、そこから1時間でもう高尾山口駅。
日曜日の朝から向かったとして、山頂でゆっくり“おだむすび”を食べ、
普通に下山して、高尾山口から電車に乗り帰路に着く。
すると日曜日の競馬中継を自宅でリアルで観れるというわけだ。
(これも時々体験しその結果を見て、間に合わない方がよかったのではと
思うことも…)
先日も少し雨降る中をいつもの高尾山稲荷山コースを登ってきたわけだが、
雨の割には思った以上に気持ちよく登ってこれた。
これまでにも何度も登ってきた高尾山なわけだが、
何度登っても飽きない高尾山であり、稲荷山コースなのだ。
(もしかしたら1年で10回以上登った時もあったかもしれない?!)
今回は9月に計画しているリーダーズセミナーの下見も兼ねての
高尾山登山ということで、予定の稲荷山コースをいろいろな視点で
確認しながらリーダーズ講師の吉田さんと登ってきた。
(吉田さん、ありがとうございます)
高尾山、それも稲荷山コースのその良さを、
改めてChatGPTに紹介してもらった。
(このところ私がプロンプトエンジニアとして、
どこまでやれるかも試してみているということ)
そして私の結論は“登らずして高尾山を知ることなかれ!”ということ。
1、健康への良い影響
高尾山稲荷山コースは、3.2キロの距離と599メートルの高さという
適度な距離と標高であり、適度な運動負荷をかけることができる。
このコースを登ることで、心肺機能を向上させたり、
筋力を鍛えたりすることができる。定期的な登山は健康促進にもバッチリ。
2、自然の美しさ
高尾山は豊かな自然が広がっており、木々や植物の種類も豊富。
登山中には美しい景色を楽しむことができる。
自然の中で過ごすことはストレス解消にもつながるし、
心身のリフレッシュに役立つ。
3、パワースポットとしての魅力
高尾山は古くからパワースポットとしても知られていて
特に高尾山稲荷山コースには、稲荷神社があり、多くの人々が訪れ、
願い事や感謝の気持ちを込めて参拝する。
4、文化と歴史の魅力
高尾山には高尾山薬王院があり、登山の終点として参拝する人が多い。
真言宗智山派の関東三大本山のひとつで、正式な寺名は高尾山薬王院有喜寺。
薬王院と参道のスギ並木は、八王子八十八景に選ばれていて
日本の伝統文化や信仰の一端をも垣間見ることができる。
5、TAKAO 599 MUSEUM
高尾山の599メートルの高さをネーミングにした“高尾599ミュージアム”が
高尾山の自然や歴史、文化に関する展示や情報を提供している。
高尾山口駅にほど近く、訪れる人々にさらなる知識や理解を深める
機会を提供している。
そう、この5つ目の“高尾599ミュージアム”なのだが、
たまたまリーダーズセミナーでの登山後のミーティングのための
程よい会議室を駅付近で探していて出会った。
かなり立派な建屋で、それなりにお金をかけたミュージアムだったのだ。
登った後にはぜひ行って欲しいおすすめのスポット。
ということで、先に紹介した『運動脳』のことを考えても、59歳を過ぎたら
この手頃で身近な高尾山がいいということ。
高尾山のその良さが伝わっただろうか?
「登らずして高尾山を知ることなかれ!」
ということで“Seeing is believing 百聞は一見に如かず”。
9月のリーダーズセミナーでは、ただ稲荷山コースを登るだけでなく、
チームごとにテーマを設定してもらい、そのプロセスにも意味を持たせながら
高尾山を満喫してもらいたい。
身近な高尾山ではあるが、されど“599高尾山”なのだ。