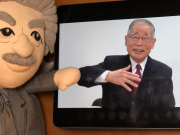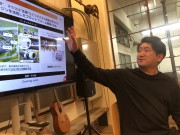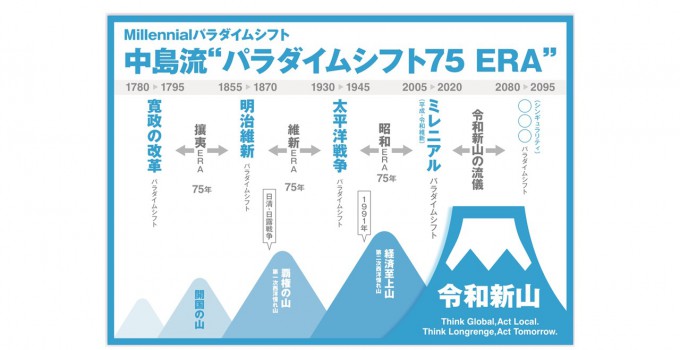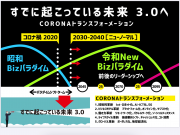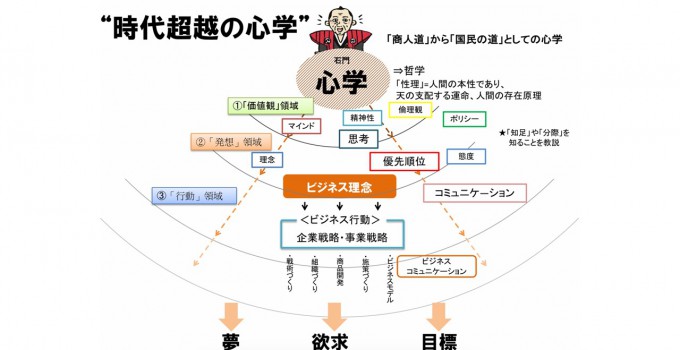11/21
2022
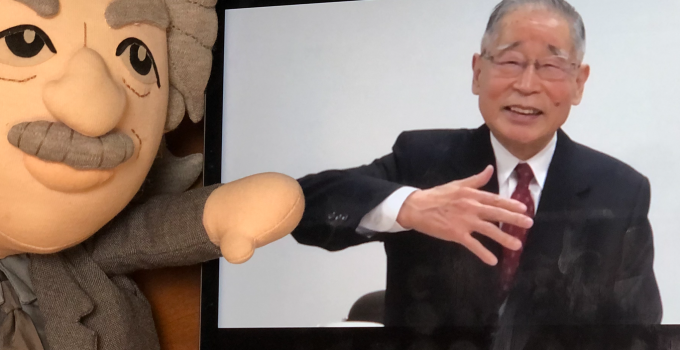
鍵山秀三郎流“自分ファーストでない”人たちの支援とは?!
「残念ながら、私の病気はよくなる見込みはありません。
普通なら現状に負け落ち込むところですが…
家族でなくて私でよかったと思うんです。
そして残念ながら方々に行くことはできませんが、
まだ私は世の中に何かを果たせることができると思ってます…」
先日iPadの動画を整理していたら、
約4年前の鍵山相談役の話に出会ったのだ。
致知出版社での月刊誌の取材(2018年)のときの動画で、
これは“日本を美しくする会”の広報担当理事としての役得でもある。
相談役が脳梗塞で倒れてから約2年後の動画だ。
もちろん私が撮影したわけだが…iPad? iPhone? か
それすら憶えてないが…
話は以下のように続いていた。
「例えば、全国で自分の身を削るように掃除を通じて
地域に貢献する人たち、または東北や災害の地に
支援に行く人たちなどへの支援です。
私が行けないわけですから…。
そしてテレビや新聞で知ったこんな人たちの支援もしています。
とんでもなく遠くの方で、苦労しながらものづくりをしている人たち。
例えば五島列島で…
真夜中に切干し大根をひっくり返すことに意義があるといい、
夫婦でやっているんですね。
また、災害地でコツコツと手間をかけてハムづくりしてるとか。
そういうのを見るとドサっと注文してしまうんです。
当然、家内はこんなにたくさん買ってどうするのといいます。
もちろん、方々に配ったりするわけです。
そして私が配った先の人たちが、また注文をしてくれるわけです。
するとものすごい数が売れたりするんです。
またこんなこともありました。
群馬県で蒟蒻芋を掘って倉庫に入れ、また土に植え
そしてまた掘り出す。
これを繰り返し5年がかりで生産する…
自分ではできない代わりに、
このような“自分ファーストでない”人たちを
経済的なチカラの及ぶ限り支えてゆきたいんですね。
“自分ファースト”の人たちが増えることは
日本が良くない方向に行くことになるんです。
ひとつ一つは些細なことでも、“自分ファーストでない”人を支えることが
日本がよくなることだと確信しています。
不自由な身体であっても使命があると思うと頑張れるわけです」
(中島による少しのリライトはありますが、こんな話でした)
自分が病気になり不自由な身になっても、まだ自分にできることがある。
掃除の人たちを支援したい。災害地で支援する人たちを支援したい。
そして“自分ファーストでない”人たちを支援したい。
まさに相談役がよく口にする“益はなくとも、意味がある”
ということの実践。
病気で不自由の身になったとしても、89歳の年齢になっても
その哲学もその生き方も変わらない鍵山相談役。
先達として私たちのこれからを導いてくれているわけだが
果たして私たちにできるだろうか。
これでも鍵山相談役に出会って、
私の生き方はかなり良くなっていると思うのだが…。
(致知出版社の皆さま、ご協力ありがとうございました)