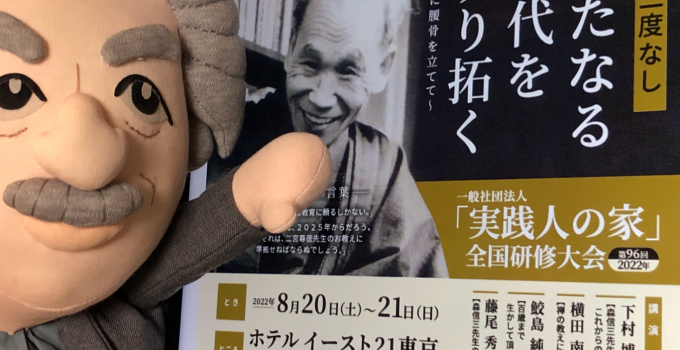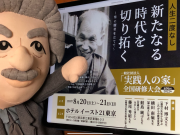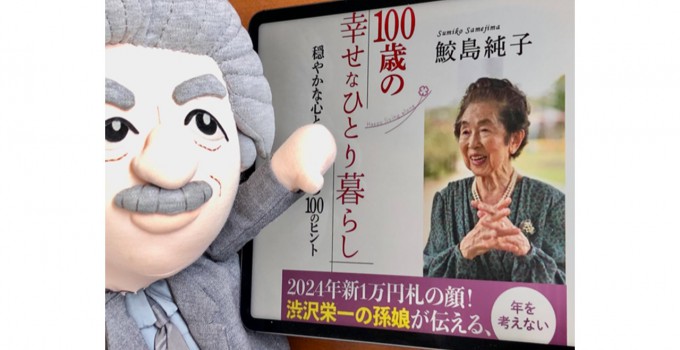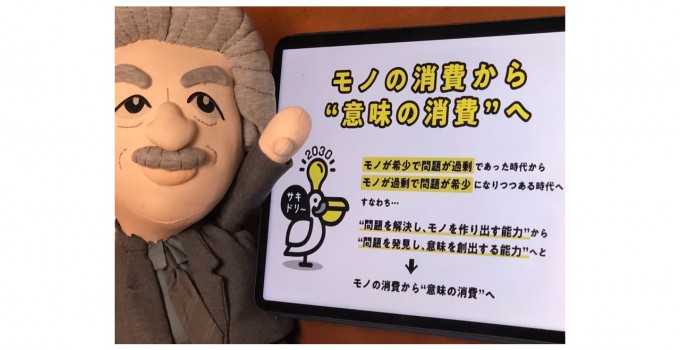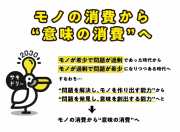09/12
2022

“すべてが加速する未来”を予測するための 令和の3つのパラダイムシフトと社会課題
今、さまざまな既存のビジネスが大きな転換期を迎えている。
これは日本だけのことではなく地球規模でのことと
言っていいだろう。
このビジ達で何度も繰り返して発信してきたが、
この大きな変化に対応し、新たなビジネスモデルを構築し
未来に選ばれるためには…、
◆“2030年全てが加速する時代に備えよ”として
AIの可能性とさまざまなテクノロジーやイノベーションを紹介
◆“GAFAMを代表とするメガプラットフォーマーの出現”
による新たなビジネスインフラ構築について
◆成熟化による“モノの消費から意味の消費へ”
など…、
これらは大きなパラダイムシフトではないか?
さらに、環境問題を含めた新たな社会課題の山積は、
あらゆる企業に関係し、それに応じた対応が
求められるようになってきた。
これらの要因に対して既存のビジネスをプラスマイナスし、
どのようにシフトして展開していくかが
“これから選ばれるビジネスとなりうるか”につながる。
そこで改めて、これからのビジネスを予測するために、
中島流、“令和の3つのパラダイムシフト”を紹介する。
[その1]
Fusion of Technology(テクノロジーの融合)
→ AIを含めたテクノロジーの融合のよるパラダイムシフト
弱いAIから強いAIへの移行は2029年だと言われている。
テクノロジーの融合が、さまざまな分野での
イノベーションになる。
これらの先進テクノロジーをしっかり押さえておく
必要がある。
[その2]
Business Platform(ビジネスプラットフォーム)
→ IT化、メガプラットフォーマーらによるパラダイムシフト
もちろんGAFAMが中心であることは間違いない。
そこにAIのプラットフォーム的なものが組み込まれると
今後のビジネスに欠くことのできない
“ビジネスインフラ”となるはず。
[その3]
New Values
→ 成熟化による価値観のパラダイムシフト
成熟化社会と共に生まれ育ってきた世代が
イニシアチブを取る社会となり、
大きな価値観の転換がされることに。
買い方、選び方、使い方が変わり、
ユーザー側の価値観の転換も大きなパラダイムシフトだ。
この“令和の3つのパラダイムシフト”を理解し、
メタバース、ナノテクノロジー、ロボティクスなど
関係する多くのテクノロジーも取り込んで
自分たちのビジネスをシフトする。
さらに関係する社会課題をも
企業の社会的責任として取り組むのだ。
時には、「お金になる仕事」と並行して
「お金にならない仕事」にも取り組む姿勢が大切。
このように、次なる時代を見据えた展開こそが、
選ばれる企業として必要条件になるといっていいだろう。
とにかく、大きな変化が起こりつつあることは間違いない!