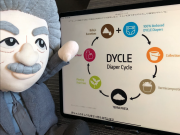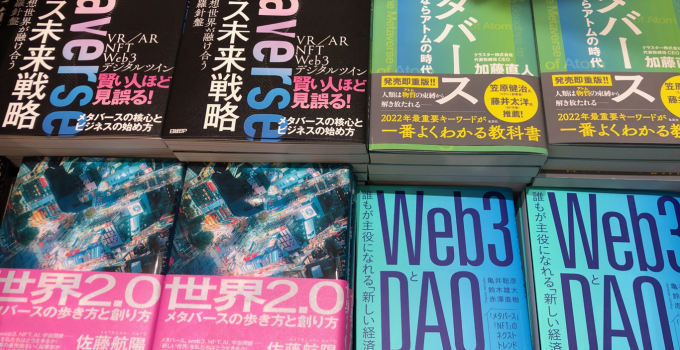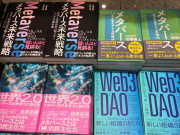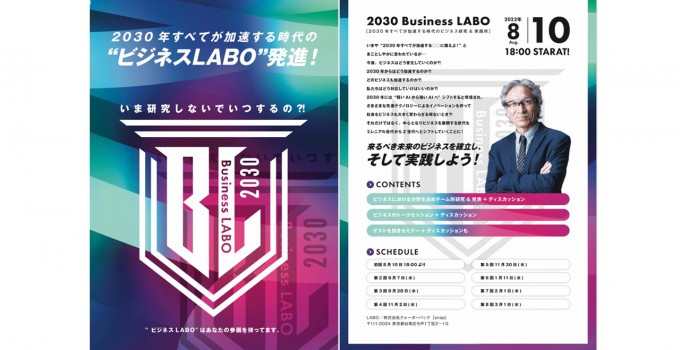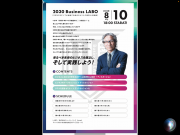08/01
2022
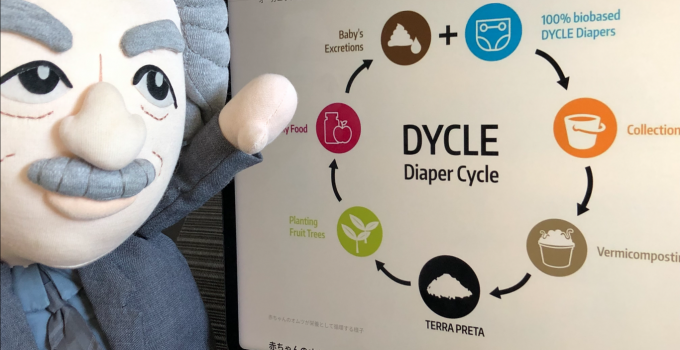
“土に還るオムツ”で、リジェネラティブを実践!
先日のNBCのオンラインセミナーにドイツから登場した
日本人美人女性経営者が開発したのは
“DYCLE(ダイクル)”という“土に還るおむつシステム”。
ドイツ国内ではすでに提供を始めているという。
この“土に還るおむつシステム”を彼女は
“リジェネラティブ・ビジネス”と呼んでいた。
“リジェネラティブ(リジェネレーション)”とは、
“再生的”“繰り返し生み出す”といった意味だが、
気候変動やサステナビリティに意識を向ける人々の間では、
地球規模の社会課題を解決するための新しい概念として
注目されている。
その女性経営者が言うには、
“それほど問題とならぬよう維持するためにしましょう”というのが
SDGsやサステナブルの概念。
翻り、“リジェネラティブ“とは問題を深く掘り下げ、
解決するよう効果ある展開をしていくという。
“サステナブル以上”の優先的な概念として発信しているそうだ。
また“サーキュラーエコノミー”と言われる
“循環経済”の考え方とも違う。
廃棄物の発生を最小限化する経済システムを回していくのが
“サーキュラーエコノミー”とすると、
課題解決にまでつなげようとするのが、
“リジェネラティブ”だ。
さて、この“DYCLE”だが…
①まず、乳幼児の便が付着したおむつを回収バケツに投入する
②ここに、微生物が入っている炭の粉を一緒に混ぜ、
嫌気性発酵を促進させると同時に消臭もする
③バケツが満杯になったら保育園へ持って行く
④その後コンポスト会社に運ぶ
⑤すると、1年後には上質な堆肥が出来上がる
⑥大量にできた堆肥は、今度は素材として苗床を
育てる会社や有機農家に運ばれ、
果物やナッツの木を植える際に使われる
この堆肥を使い数年後にりんごの実がなると、
お茶やジャムなどの食品を作ることができる。
その地域のビジネスが育ち、果物の木を冬に
剪定する際には枝から炭を作ることも可能となる。
このように、芋づる式に複数の成果物が出来上がり、
複数の収入源が作られていく。
この理念は“システミック・デザイン”と呼ばれ、
“一つの生産活動で生まれた製品やエネルギー、
ゴミなどは全て次のシステムの素材になるべきだ”という考え方だ。
まさにDYCLEはこの理念が活かされている。
実は今回のビジ達で一緒に紹介した“石坂産業”。
しばらく前からこの“リジェネレーション”をテーマに
取り組んでいた。
ただリサイクル率を100%に近づけるだけでなく、
それらをアップサイクルへと展開することで、
より価値あるものとし、いい地域づくりや
社会構築に向け展開している。
私たちも未来のために、“リジェネラティブ”を
意識していきましょうね!