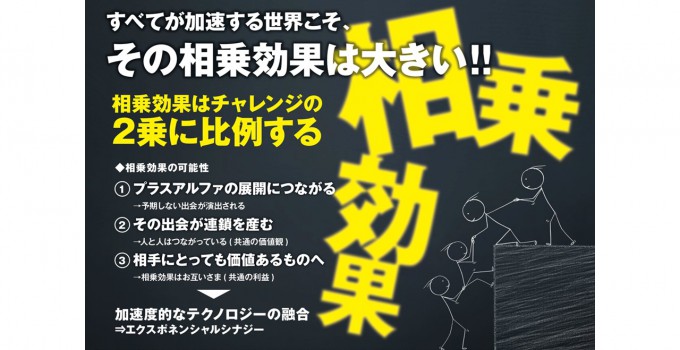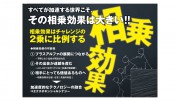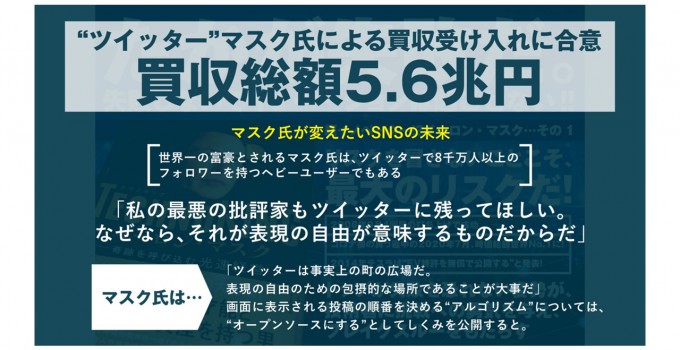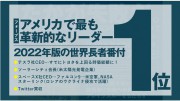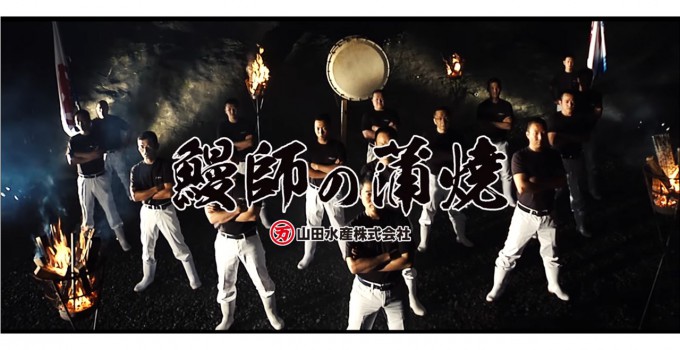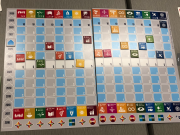05/23
2022

100年続く企業小野株式会社4代目のチャレンジ精神!
今書店に行くと、
『何があっても潰れない会社』―100年続く企業の法則―
という経済ジャーナリスト田宮寛之著の本が平積みされている。
“今こそ老舗企業から学ぼう”というプロローグから
始まるのだが、そのトップに紹介されているのが、
大型手芸専門店“ドリーム”を展開している小野株式会社。
この小野株式会社の小野兼資社長は4代目で、月刊CD
ビジネスイノベーションにも登場してもらっている。
私の友人でもあり、香川NBCに所属する仲間でもある。
そして、ビジネスイノベーションを10年以上(?)
聴いてくれている受講者なのだ。
小野株式会社は、明治44年創業、今年で創業111年目。
初代の小野耕作氏は、香川県財田大野村出身。
33才のときに熨斗(のし)や贈答品を扱う“小野だるま堂”を開業。
1945年に空襲で店が全焼し、土地を売却。
2代目が高松市にて手芸用品の問屋として事業を復活させる。
戦後は洋服や身の回りの品は手作りがあたりまえだったこともあり、
問屋業としても発展。
3代目小野耕一氏は、勉強熱心で勤勉で、
2代目が脳梗塞で倒れたこともあり、
介護しながらも事業拡大を図った。
そして4代目の小野兼資氏。3代目からは、
「仕事だけに集中できる環境に感謝しなさい」と言われたという。
そして、問屋業は今後厳しくなると予想し、BtoCの店舗展開を始めることに。
ただ、香川で問屋商売をしていた手前、
あえて一号店は瀬戸内海対岸の岡山県で、田んぼの中にオープンさせた。
店名は手芸センター“ドリーム”。
手作りの夢や、スタッフの夢をのせてこのネーミングにしたという。
そして今や、関東・関西・中四国に展開し97店舗まで拡がった。
多店舗展開によりオリジナル商品も増加し、利益向上にもつながり、
それが次なる店の出店へと。
信用が信用を生んでの約100店舗の規模となったという。
私が着目したいのは3代目の体験だ。
本社ビルを建てる予定で進めていた矢先に
土壇場でメインバンクからの融資の話が消えてしまうことに…。
最終的にあきらめるか? というときに
銀行が貸してくれることになったというが…
そんな経験から
「お金はいつでも儲けられる。あせるな。信用を失うな」と。
3代目は商売で重要なことは“信用”だと常に言っていて、
これが迷ったときの小野家の判断基準となったようだ。
3代目のときにバブル時代が到来したが、
信用を考え、財テクに手を出さなかった。
成功しても失敗しても本業に精を出し、
現在もその価値観を大切に商売を続けている。
これからも100年以上にわたり受け継がれた価値観が
5代目、6代目へと繋がっていくのだろう。