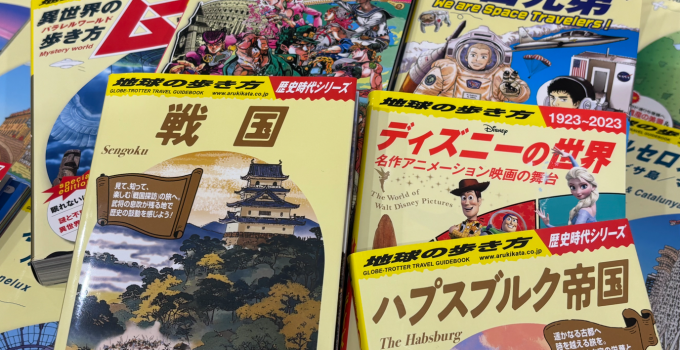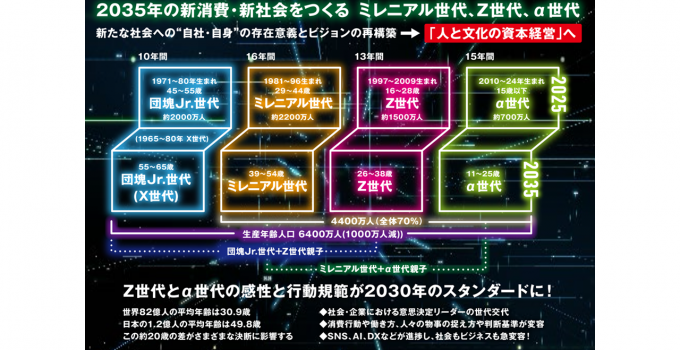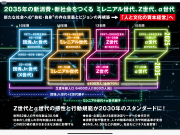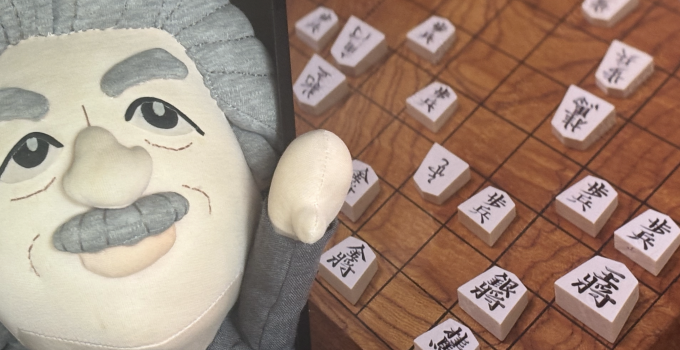01/26
2026
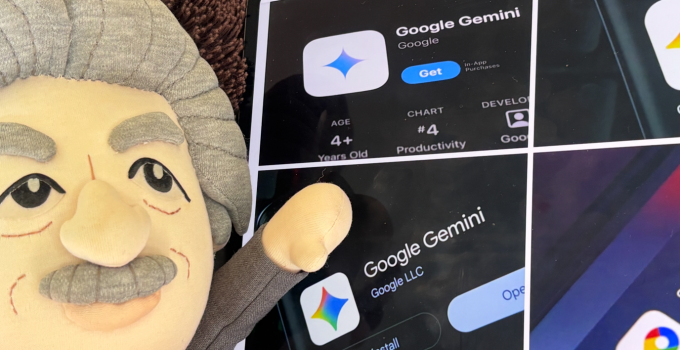
人間中心×AI共存の“ビジネスの達人”へ。 “シン・不易流行”へのテーマ続々と!
「“ビジネスの達人”の過去のキーワードや、
これからの時代に求められる“シン・不易流行”
“美意識×凡事徹底”といった視点
非常に興味深く拝見しました。
2026年、そして2030年、2040年を見据え、
中小・中堅企業が生き残るための
“次の一手”となるテーマをご提案します。
これまでの文脈…未来志向、人間中心、AIとの共存、
本質的な経営…を踏襲しつつ、
新たな視点を加えたテーマ案を紹介します」
だって!
これは“Gemini 3 Pro”に、このところの
“ビジ達”のテーマを取り込んでもらい、
次なるテーマ案を出してもらったときのプロローグ。
「○○と言った視点、非常に興味深く拝見しました…」
へ~こんなお上手をプロローグに入れられるようになったのだ。
いよいよ生成AIが“気の利いた会話”の下地ができてきた
ということなのだろう。
【Geminiが提案してくれた2030年を見据えたテーマ案】
ということで、Geminiが提案してくれた
…未来志向、人間中心、AIとの共存、本質的な経営…
をベースとするビジ達「シン・不易流行」へのテーマ案。
その1◆“週3正社員”がエースになる日?!
フルタイムだけが正解じゃない。
優秀なパラレルワーカーや介護・育児中の人材を
“週3正社員”として核に据える組織戦略とは?
→いいねえ~、まさにピープルマネジメントであり、
人的資本経営の実践ということ。
その2◆Z世代・α世代が選ぶのは
“就職”ではなく“就社”でもなく“就志” ?!
会社の規模や安定性ではなく
“志(パーパス)”に共感できるかどうか。
採用サイトより先に磨くべきは経営者の“言葉”。
→うんうん、入口は“パーパス”ってこと。
次はその仕事内容?!給料の多寡?!
その3◆オフィスは“働く場所”から“雑談する場所”へ?!
リモートワークが定着した今、リアルなオフィスの価値は
“偶発的な出会い”と“無駄話”にこそある。
→弊社もリモートワーク中心で、出社は当番制となっているが、
確かにオフィスの役割であり、使い方が大きく変わってきた。
その4◆サイバーセキュリティは“コスト”ではなく“信頼の証” ?!
情報漏洩は一発で信用を失う。
堅牢なセキュリティ体制こそが、大手企業と取引するための
最強のパスポートとなる。
→アサヒビール、アスクルとたて続けにランサムウェアに
やられたようだが、どこから忍び寄ってきたのか?!
私たち中小企業から入り込んだとしたら…
その5◆M&Aは“乗っ取り”ではなく“時間を買う”戦略?!
後継者不足の解決策としてだけでなく、
異業種の技術やノウハウを
一瞬で手に入れるための友好的M&A活用法。
→今後は中小企業においてもM&Aは、
もっともっと多くなるに違いないのだ。
その6◆“事業承継”は親子のバトンタッチではなく
“創業の精神”のインストール?!
株式や役職を譲るだけでは失敗する。
先代の“想い”や“美意識”を次世代がどう解釈し、
アップデートするか。
→私はすでに創業40数年の会社を無事承継したが、
経営者会議とリーダーズセミナーを事業のベースとする
“株式会社QB総合研究所”の承継はこれから。
パーパスは明確だし、ここには娘がいるので、
スムーズにいくことを祈っている。