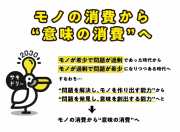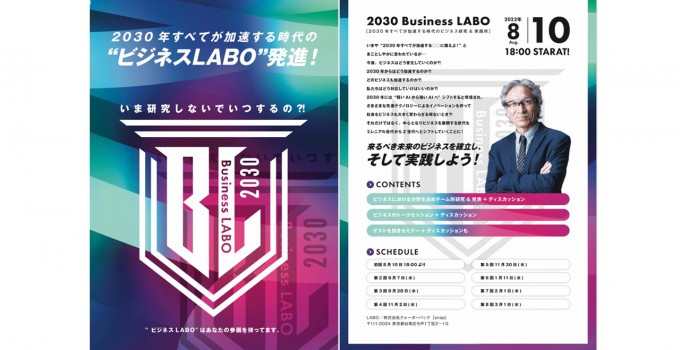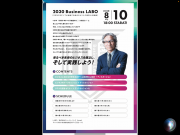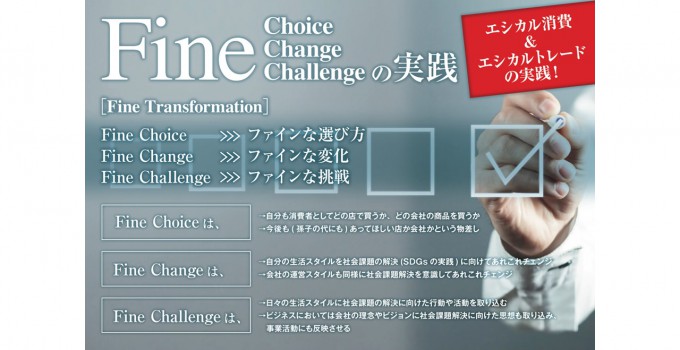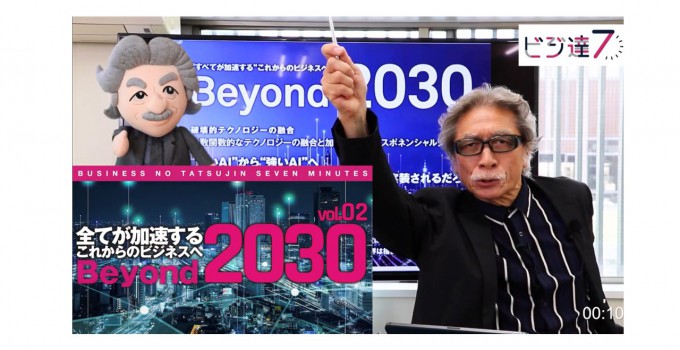08/29
2022
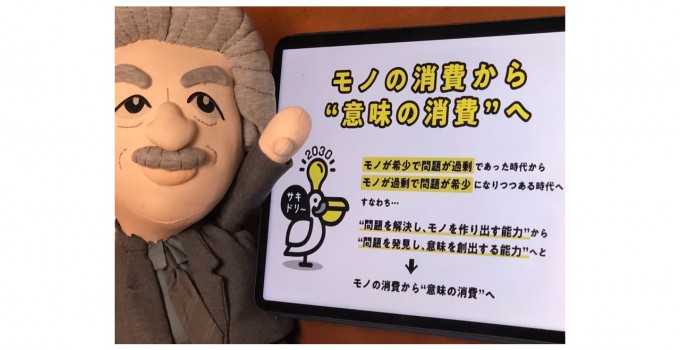
→モノの消費から“意味の消費”へ
“モノの消費からコトの消費へ”はよく使われていたし
私も度々口にしていた。
すでに30年以上前から使われていたかもしれない…
今回、私が発信するのは“コトの消費”ではなく“意味の消費”だ。
先にも紹介したが、成熟化時代というのは
“モノ”が過剰で“問題”が希少になりつつあるということ。
すなわち…
“問題を解決し、モノを作り出す能力”から
“問題を発見し、意味を創出する能力”へとシフトしているという。
そこで中島流の解釈は、
ミレニアル世代、Z世代の人たちは
“モノの消費”でも“コトの消費”でもなく、
「意味の消費」をしているのではないかということ。
マーケティング的な捉え方でも、“意味の消費”と捉えると
そのアプローチの仕方が見えて来るのではないか!?
先週のビジ達“令和のアップデートの実践”でも話したが、
アップデートしなければならない理由の一つとして
この“モノの消費から意味の消費へ”価値観が
シフトしていることがあげられる。
この価値観のシフトによって大きくビジネスが変わった。
クルマ、自転車、部屋もシェア。サブスクの導入。
モノを所有しないで、その用途だけを利用するという発想。
すなわち“所有する意味”が見いだせなかったということだろう。
一方で、若い人たちがUber eatsや出前館などの
デリバリーサービスにお金を使い、頻繁に使用するのは
そこになんらかの意味が見いだせてのことだ。
この感覚は、まさにミレニアル&Z世代の
人たちでないとわからないと言っていいだろう。
少なくとも私たちの時代の価値観や選択とは変わってきている。
このところ注目のNFTでは、
日常に使えないメタバース空間上の商品が
破格の高値で売れているという。
これもそこに意味を見出した人たちの行動ということだろう。
また私たちの、ビジネスや企業にも“意味”を求められている。
先に紹介した“パーパス時代のビジョンの山”でも発信したが
「パーパス=企業の存在理由」が明確でないと多くの若者は、
そこで働く意味をみつけることができないのだ。
VUCAな世界且つ“モノが過剰で意味が枯渇している”状況では
これまでのリーダーシップ“HOW=どうやるのか?”だけでは、
組織の方向づけも、モチベーションを引き出すことも難しい。
“WHY=なぜやるのか? WHAT=その目的は?”を示すことが
組織に勢いを与え、モチベーションを引き出すこととなり
組織のパフォーマンスを高めることにつながるのだ。
これも“意味の消費”の現象といってもいいのかもしれない。
これからのビジネスにおいて“意味”を意識していくことが
選ばれる側になる重要な視点になってくるだろう。