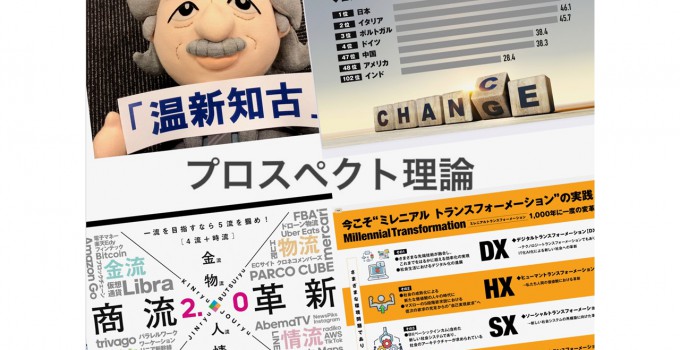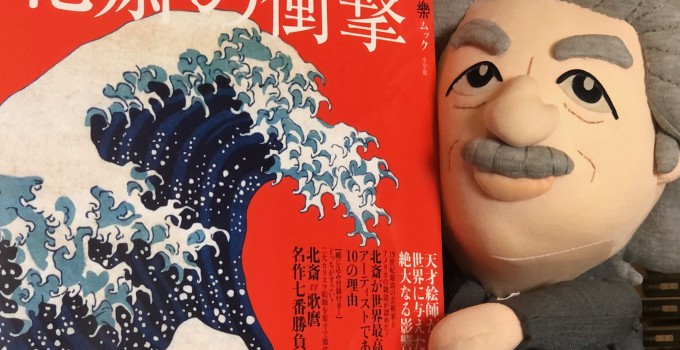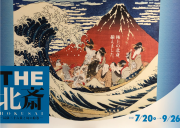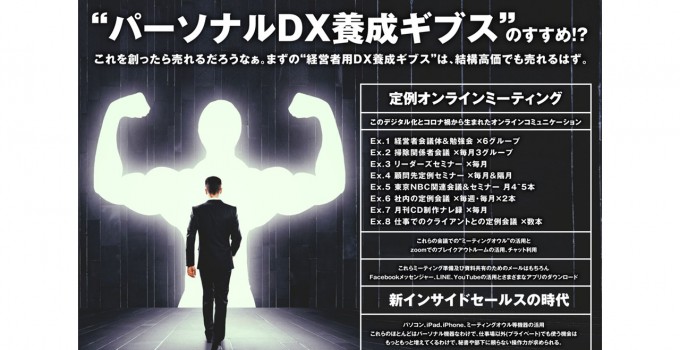11/22
2021

経済合理性から“サスティナブル合理性”へ
前回のビジ達モバイルで紹介した話を試行錯誤した結果、
経済合理性から“サスティナブル合理性”へ
という考え方に至った。
再度になるが話を紹介しよう。
『「ここまで災害が多くなってきたら
そろそろ引越しを考え始めないとねぇ〜」
「じゃ、どの星にする?!」
「あんまり天候が急変したりするのもイヤだし、
地震が多いのもイヤ、津波も怖いし。
怪しいミサイルも無いほうがいいし、
やっぱりパンデミックはもうイヤ!」』
これは、ある夫婦の会話として書いた。
この後、セミナーで話をし、皆さんの反響もあり、
こんな話につなげた。
↓ ↓ ↓
地球って素晴らしいなぁって思いますよね?
もちろん、地球以外の星に行ったことありませんが…
大雨もあります
雪の日もあります
寒い季節もあります
暑くてたまらない季節もあります
そして、台風も来ます
でも…
地球は私たち78億人をしっかり支えてくれています
90億人になっても、100億人になっても
多分支えてくれるだろうなぁという安心感があります
地球は無くならないという安心がありました
ところが…
地球は無くならないし
支えてくれようとしてるんですが
私たちが自分たちで住み難くしているわけです
地球の人同士で争い合い
せっかくの地球の資源を無駄遣いして
目先の経済性を優先して
地球の裏側の人たち、未来の人たちを無視して、
“今だけ、自分だけ、お金だけ”という欲に任せた日々を送る
この浅はかな行動こそが
“素晴らしい地球”を持続させられない理由なのです
これって地球人の“自業自得”ですよね
言っておきますが、引っ越す次の地球は無いんです
多分探してもないでしょう
だから、今から心を入れ替えましょう
“今だけ、自分だけ、お金だけ”をやめましょう
↓ ↓ ↓
続けて、
『経済合理性から、“サスティナブル合理性”へ
地球規模の社会課題にみんなで取り組もう!
仕事でもプライベートでも』と書いた。
さて、ここで語った“経済合理性”とは・・・、
原材料、動力源、人件費などのあらゆるコストを
低くおさえ、コストを重視。
すなわち、安い動力源として、
地球の限りある化石燃料を使い、さらにCO2を排出する。
石油化学由来のプラスティックを使うことで、
廃棄の結果としてマイクロプラスティクとなり海洋汚染へとつながる。
そして、人件費をおさえることで、格差をつくりだす社会となる。
コスト重視の経済活動は地球や社会にさまざまな
ひずみを生み出すことに。
これに対して、たとえば、コストのかかる再生エネルギーを動力源とし、
石灰石からつくる紙やプラスティックを使用し、
働く人に十分な賃金を支払うことは、
コスト高となり、非経済ではあるが、“持続可能”に叶っている。
これが“サスティナブル合理性”
以前“新・パラレルワーク”として、“経済合理性にあった仕事”と
“経済合理性には合わない仕事”をパラレルに展開することが
これからの企業に求められるのでは?と提案した。
人類にとって持続可能な地球や社会とするために、
“サスティナブル合理性”について研究をし
地球規模の社会課題に、仕事はもちろん生活の両面でも
みんなで取り組もうではないか!