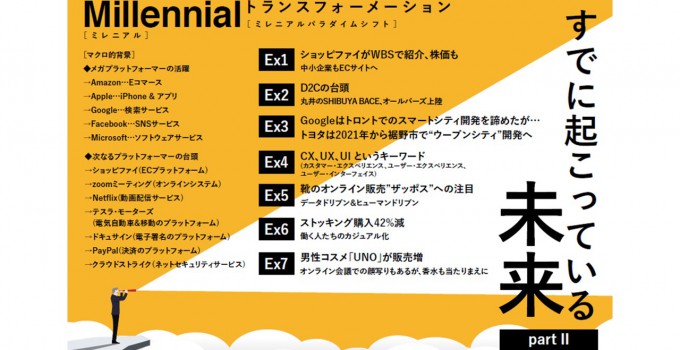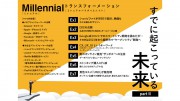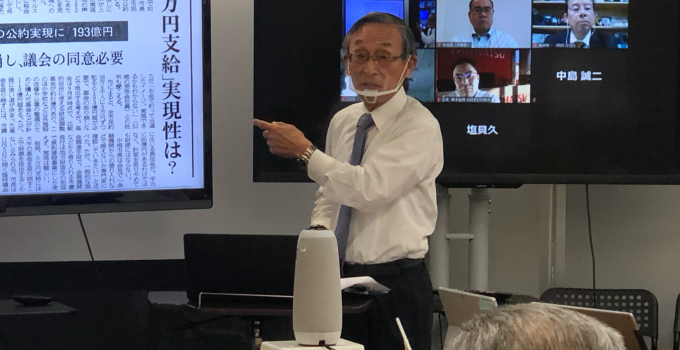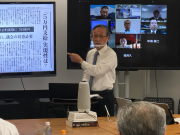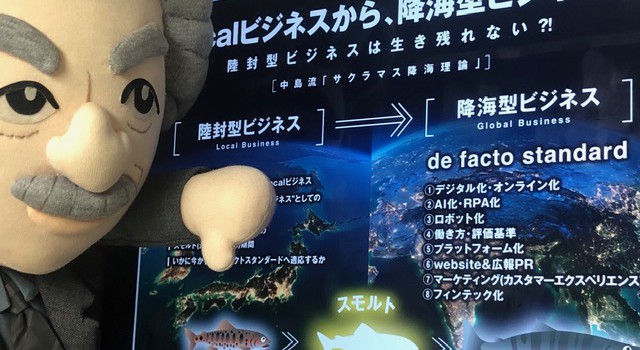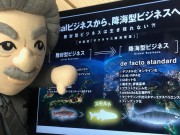01/12
2021

果して、TTG無人決済は拡大する?!
“TTG”とは”Touch to Go”の略で、無人決済システムのことだ。
以前ビジ達で高輪ゲートウェイ駅の売店のこのシステムを紹介した。
基本的に、“(店に)入る” “(商品を)手に取る” “(店から)出る”
だけでよく、店から出る時に“スイカ”で決済をする。
今回、TTGを導入した無人決済小型スーパーマーケット
“KINOKUNIYA Sutto”(キノクニヤ・スット)が
目白駅にオープンしたと聞き行ってきた。
写真は試しにせんべいと飴を買ってみたもの。
ここでも、商品をそのまま鞄に入れてもよいそうだ。
高輪ゲートウェイ駅との違いは店を出るときに、
カードやスイカなどのどの決済システムを利用するのかを
選択をする必要があった。
このTTGシステムはKINOKUNIYAを皮切りに
様々な場所で展開する予定で、
ファミリーマートとも提携したと聞く。
また“トライアル”というディスカントスーパーの千葉県長沼店で
導入されている“スマートショッピングカート”という
システムも注目されている。
自分でカートを押しながら、欲しい商品を手に取り、カートの
読み取り機にバーコードをかざせばいいのだ。
大きくて重たい商品に関しても、ハンドスキャナーで対応
可能となっているという。
レジは、“クイックゲート”を通る仕組みで、
そこで決済をすることになっている。
お客様の半数以上がこのシステムを利用するという。
この“トライアル”を経営する会社は、
創業期にはソフトウエア構築及びパソコン販売していていた。
流通向けのITシステム開発を手がけていたのだが、
自らスーパーマーケットを展開し、“スマートショッピングカート”を
開発・導入したという。
コロナ禍もあり、このような無人決済が拡大していくだろう。
当然、経営的には人件費削減の効果も見込んでのことだ。
ある意味では、アマゾンのネット販売も無人決済だ。
問題が発生したときだけ人が対応、介入するシステム。
店をもたず、人件費を抑制すると商品を安く売れるし、
効率もよくなっていく。
従いこのような無人化のためのシステムはこれからも
拡大していくだろう。
私が好んで食べていた“陳建一の麻婆豆腐”の素は
近所のあるスーパーにしか置いていなかったのだが、
突然取り扱いがなくなり、今ではアマゾンで取り寄せしている。
アマゾンは商品数が多いので、かなりの確率で欲しい商品が
手に入るというわけ。
また、マスクも手に入りやすくなったとはいえ、お気に入りのマスクには
なかなか出会えない。
そこで、マスクもアマゾンで買ったりもしている。
私ですら、このようにオンライン購入が多くなっているわけだ。
欲しいものをネットで注文をし、無人レジの
スーパーで買い物をするというのが“ニューノーマル”となっていく。
まだ無人決済システムの店はほんの一部ではあるが、
これからは無人決済がもっと進化し
それが当たり前になっていくだろう。