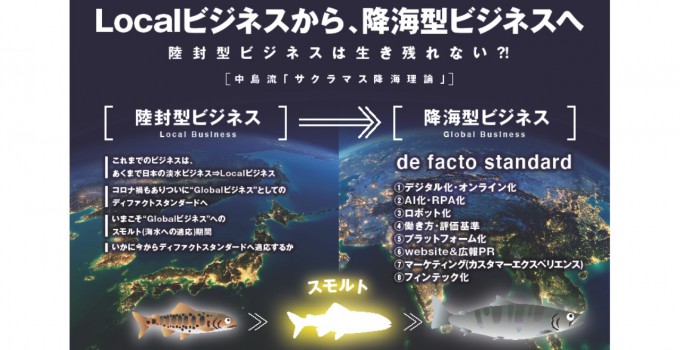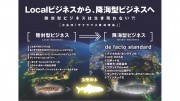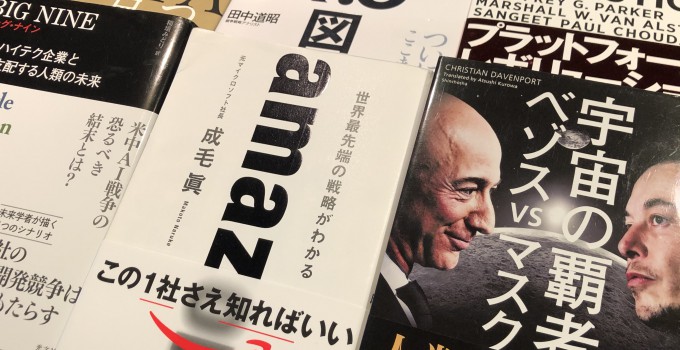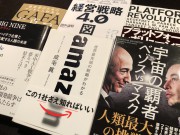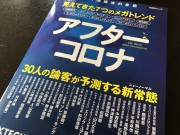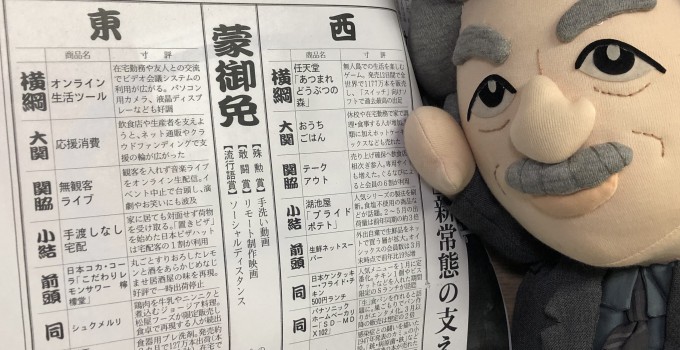09/23
2020
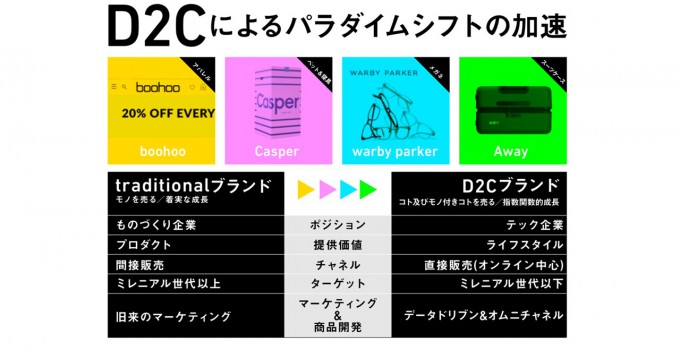
“D2C”が加わってもっと加速
今やアメリカのショッピングモールは、あちこちで
歯抜け状態。いや、モールの1/3が閉鎖の危機だという。
その立役者がアマゾンであり、D2Cブランドだ。
ZARAも、ECサイトで直接販売するスタートアップの
アパレル企業を意識して、1200店舗を閉鎖して
ECシフトするという。
今、H&MやGAPも厳しい状況におかれているのも
D2Cブランドの影響によるもの。
“D2C”とは“ダイレクトトゥコンシューマー”の略で
メーカーが直接消費者へ販売すること。
もちろんそのほとんどがオンライン上で行われている。
少し前にビジ達で紹介したイギリスのECファストファッション
ブランド“boohoo”(ブーフー)もD2Cだ。
D2Cブランドでは“テスト&リピートモデル”と言い、
初めに多品種、小ロットで生産をし、テスト販売の結果を見て
リピート再生産をし、さらにそのデータを元に本格的な販売となる。
販売の裏づけがされてからの生産なので
リスク回避されるというわけ。
“データドリブン”と言って、データをベースにし
次なる展開を決めていく手法だ。
マットレスや枕などの寝具を販売する“Casper”もD2Cブランド。
オンライン販売のため、家賃、人件費の節約ができ、
当然価格は安価にできる。
また100日間の無料体験というサービスをしているのだ。
しかも10年の補償付きだという。
キャスパーでは、マットレスを実際に触れてみて、しかも寝てみることが
できる有料のデモルームがある。
そこは昼寝ができる体験サービスショップなのだ。
実は、このキャスパーの出現からわずか4年ほどで、
アメリカのマットレスの最大手、“マットレスファーム”が破綻
したという。
消費者にとっては、価格が安いだけでなく、洗練のUI,UXでサービスも
充実していることで、キャスパーが選ばれるというわけだ。
(UI/ユーザーインターフェイス、UX/ユーザーエクスペリエンス)
今、ニューヨークのソーホー地区周辺にはD2Cブランドの
ショップや体験できる場所が増えている。
メガネやスーツケースのスタートアップ店が開店し
今までとは違う店構えがあちこちにあるという。
[概念図参照]
●さてここで、今までの“既存ブランド”と“D2Cブランド”の違いを
ポジショニング・提供価値・チャネル・ターゲット、
マーケティング手法の観点から分析してみた。
↓ ↓ ↓
→既存ブランドは、ものづくりの企業であり、間接販売、
ミレニアル世代以上がターゲットで広告代理店を通す旧来のマーケティング手法。
→一方D2Cブランドは、テクノロジーを駆使したテック企業であり、直接販売、
提供するのはライフスタイルで、ミレニアル世代以下がターゲットとなり、
マーケティングは“データドリブン”で“オムニチャンネル”なのだ。
この対比から見てもD2Cブランドが今後成長していく
ことはわかるだろう。
これからはオンラインがもっともっと加速していくのだ!!