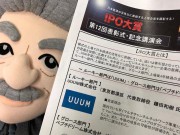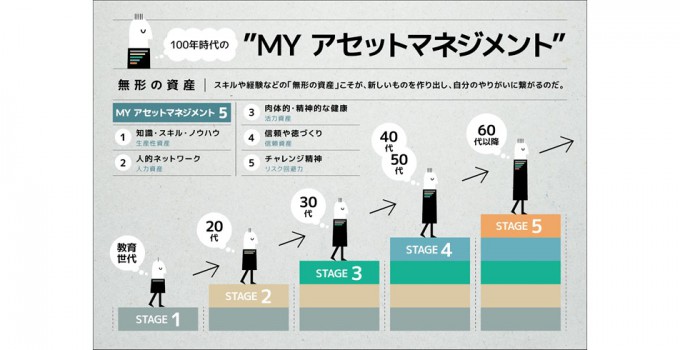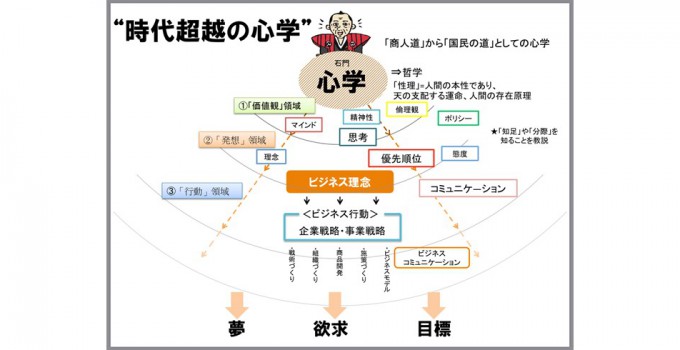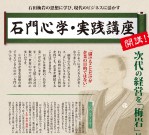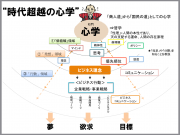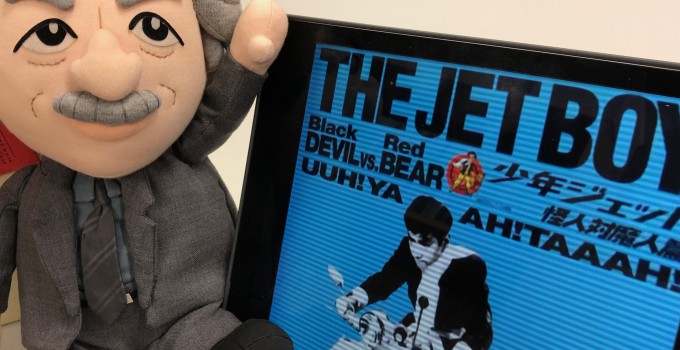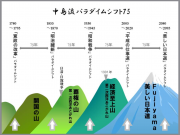03/26
2018
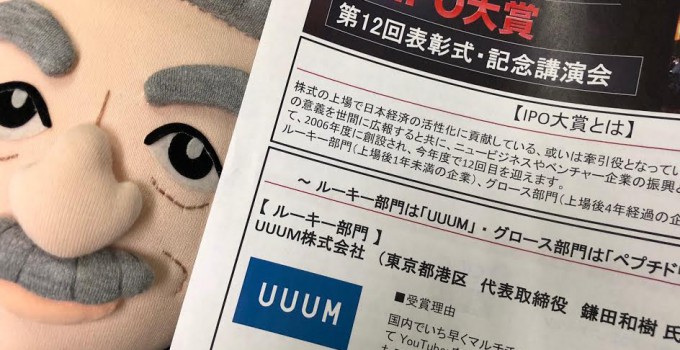
“UUUM株式会社”が発信していること
2017年8月、東証マザーズに上場した
“UUUM(ウーム)株式会社”が、
日本経済を活性化させている企業として、
IPO大賞に選出された。
(かなり風変わりな名前ではあるが…)
設立から5年目だが、既に80数億円を売り上げる
今大注目の会社だという。
これは、今若者に絶大な人気を誇る
「YouTuber」専門の初の芸能事務所!
YouTuberが一生懸命動画をつくる代わりに、
UUUMが企業とのタイアップや、イベント運営、
グッズ販売支援など動画以外の部分をサポートしているということ。
そんなUUUMの代表取締役・CEOは鎌田和樹氏。
さらに、最高顧問はYouTubeチャンネル登録数が(私が見た時点で)
5,760,261人にもなる、日本のYouTuber界のメインスター
「HIKAKIN(ヒカキン)」だという。
UUUMが設立されたのは、2013年6月。
そしてなんと! 2017年8月には東証マザーズに上場している。
私からすると、まるで誰かに後頭部をガツン! と殴られた気分…。
たった4年で、80億円を売り上げ、上場してしまったのだ。
しかし、その人気の裏付けは確かに存在する。
中学生男子の「なりたい職業ランキング」を見てみると、
1位はITエンジニア、2位はゲームクリエイター、
そしてなんと、YouTuberが3位にランクインしているのだ!
さらに、アメリカでも13歳~18歳に最も影響力があるスター
トップ5の調査で、1~5位をYouTuberが
独占している(6位にやっと映画俳優が入っている)という。
このような事実を目の当たりにすると、
テレビを見る若者が減少しているということが
リアリティを持って伝わってくる。
15年後には、今中学生の子どもたちは30歳になる。
すなわち、ビジネスシーンにおいて
彼らがバリバリと活躍する頃ってこと。
ということは、このYouTubeを観て育った人たちの
価値観が反映されビジネスが展開されていくに違いない。
私たちも経営者として、若い人たちが起こす次なる流れを
意識して行動していくことが、判断を誤らないための要素となるだろう!