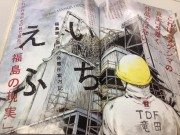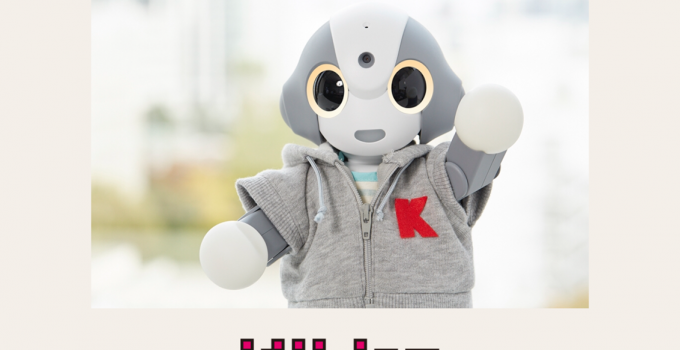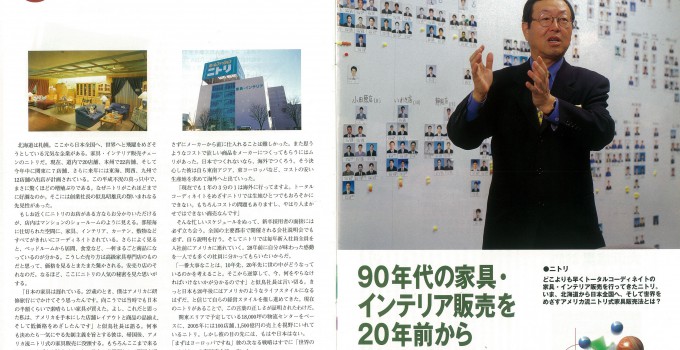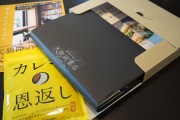04/24
2017

いまカンボジアが“テイクオフ”
“テイクオフ”をご存じだろうか!?
もちろん、飛行機が離陸するときのこと。
ところが今回の意味はちょっと違う。
経済用語の“テイクオフ”なのだ。
これは、アメリカの経済学者が提唱した、
国が本格的な経済成長をむかえ、
経済的に大きく飛躍していく段階を示した言葉。
先日、いままさにこの“テイクオフ”をむかえている
カンボジアのプノンペンへ初めて行ってきたのだ。
プノンペンの道路を入り乱れて行き交う
車、バイク、トゥクトゥクに、経済成長への可能性を
非常に感じたんだよねえ~!
海外へ行くと必ず早朝ランニングをする私。
今回もランニングをしていたのだが、
まあ~プノンペンのドライバーは信号を守らない!
1分間信号待ちをしていると、その間に
10台ほどのバイクが信号無視をして走り抜けていく。
当然、事故もあちこちで起こっているそうだが、
このプノンペンの交通事情と行きかう人たちの顔つきから、
私はカンボジアにみなぎる若いエネルギーを感じたのだ。
ポル・ポト政権の残した傷跡が未だ癒えないカンボジア。
それでも少しずつ政治が安定し、教育にも力を入れ、
経済産業の基盤も固まりつつあると言えるだろう。
そして、インフラが整備され流通が確立されるとともに
産業による需要が産まれはじめ、税収が上がり、
その税収でインフラを整備して…と、
この成長循環が徐々に回りはじめているということ。
そう、まさに今のカンボジアは経済成長が次なる経済成長を促す
自己増幅的なプロセス、つまり“テイクオフ”の段階へ
入っているといっていいだろう!
ところで日本の“テイクオフ”はいつだったかというと、
1945年の終戦からおよそ約20年後の1960年代中頃。
その25年後、世界第二位の経済大国へ大躍進したわけで、
まさにそのときが日本の“テイクオフ”だったと私は考えている。
そしていま、カンボジアは日本の1960年代のような状況へ突入しているのだ。
この成長がカンボジアをあっという間に
変えていくのだろうねぇ…。
私たちの国、日本がかつて体験したことが、
いま世界のあちこちで起こっている。
世界に向かって大きく“テイクオフ”しようとしているカンボジア。
今後に期待するとともに、また訪れたいと思ったのだった!