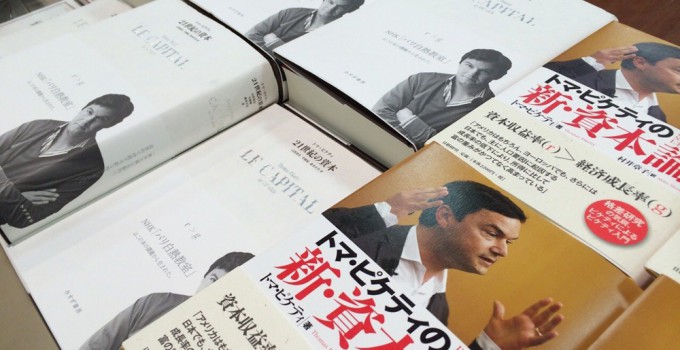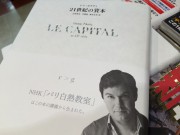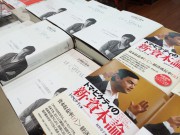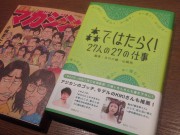03/16
2015

“集客アジ”理論の証明
このところの私の関心事のひとつが、
スーパーマーケットの躍進だ。
都心ではコンビニよりも「マルエツプチ」などの
「ミニスーパーマーケット」の売上が伸びているという。
スーパーマーケットの“売り”は、
なんといっても生鮮食品とお惣菜だろう。
惣菜と生鮮食品こそ、お客様支持率のバロメーターなのだ。
私がこれまで何度かご紹介したスーパーマーケットチェーン
『オオゼキ』では、売上高経常利益率がなんと7%台!
これはこうした業種の中ではかなりの数値なのだが、
驚くべきはその内訳。
なんと、売上高の50%を生鮮食品が占めているところだ!
すなわち、繁盛の理由は、
この生鮮食品とお惣菜売り場にあると言える。
惣菜売り場による繁盛店の代表と言えるスーパーが、
宮城県の秋保(あきう)温泉にある「さいち」というお店だ。
私も何度かお邪魔して、その繁盛ぶりを体験している。
この小さなスーパーマーケットの繁盛の話は、
NHKの『プロフェッショナル 仕事の流儀』でも
取り上げられたのでご存知の方が多いだろう。
こういっては失礼だが、
少々辺鄙な場所にあるのに売上は年間7億円!
そのうち、おはぎと惣菜だけで3億円の売上があるという。
特におはぎは、一日平均で5000個も売れる人気商品だ。
こうして人気のスーパーマーケットを並べてみると、
改めて惣菜や生鮮食品の重要性が分かる。
これはずばり、ナカジマ理論で言うところの“集客アジ”理論!
これは、“美味しいアジフライ”を扱う
お店は、必ず人気店であるということ。
いやいや、この言い方はもしかしたら正しくないかも?
アジのような足の速い魚を美味しい惣菜にするためには、
きちんとした仕込みと、手間をかけた調理が必要になる。
すなわち、技術が必要だから、とか手間がかかるから…と、
ついつい手を抜いてしまう作業を、
人手と時間を割いてしっかり行える店は必ず繁盛する、
ということだろう。
その昔、このビジ達でも
「オオゼキvsマルエツ」な~んて記事を書いたことがある。
マルエツがダイエーグループだった頃のこと。
当時オオゼキのスタッフは、面積比でマルエツの約3倍もいたのだ。
お客様の要望を聞くため、対面販売のため、欠品しないため…。
もちろん一人一人がその役割をしっかり担ってくれているのだ。
お客様に選ばれるためのきめ細かなサービスを実現するには、
それだけの人員が必要だったということ。
オオゼキもやはり、“集客アジ理論”を証明してくれるお店だったのだ。
変化の時代だからこそ、
普遍的法則はよりはっきりと見えてくる。
“集客アジ理論”もまさにそれ。
多くのお店が、この理論を信じて対応してくれることを
願ってやまないのだ!