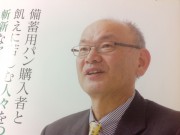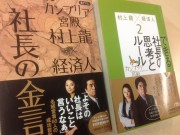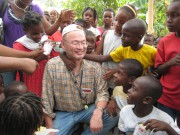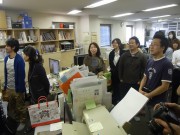03/17
2014

ビジ達流 BCP
陸前高田市でしょう油や味噌などの
醸造業を営んでいる八木澤商店。
3年前の東日本大震災では、
工場から事務所、店舗まで
全てが津波で流されてしまったという。
それにも関わらず、
たまたま研究所に預けていた「もろみ」のおかげで、
代々継承してきた味を守ることができたのだそうだ。
きっとこれからは計画的に
「もろみ」のバックアップを取っておくことだろう
(「もろみ」はバックアップとは言わないだろうが…)。
そして今、八木澤商店が取組んできたような
“BCP”が改めて注目されている。
BCPとはBusiness Continuity Planの略。
すなわち「事業継続計画」。
災害や事故などの危機が発生した際、
重要業務への影響を最小限に抑え、
速やかに復旧・再開できるように
あらかじめ策定しておく行動計画のことだ。
例えば、自然災害や事故などのリスクごとに、
システムに与える影響を洗い出して、
社内の連絡体制やバックアップシステムへの
切り替えルールを構築すること。
また、復旧の優先順位や手順などをマニュアル化して、
まとめておくなどがあげられる。
つまり、緊急事態に備え、
あらかじめ対処のし方について検討を重ね、
日ごろから継続的に訓練しておくことが、
企業の継続を大きく左右するということだ。
先にも語ったように八木澤商店は、
たった1杯の「もろみ」のおかげで、
伝統の味を守ることができ、
今では通常の営業ができるまでになった。
しかし、本当に八木澤商店の復興を支えたものは、
そこで働く“人材”が無事でいてくれたことだろう。
しょう油や味噌作りのもととなる
「もろみ」は、当然大切。
しかし、それを活用して商品づくりする
職人がいなければ、
八木澤商店がその先に進むことは難しいのだ。
人材こそが、あの震災からたった3年という期間で
八木澤商店を復活させた“生命線”であり、
“ビジ達流BCP”ということ。
やはり、これからのビジネスは「人」。
すなわち企業は、組織を成長させる前に
まずは人を大事にしなければ
ならないということなのである。
設備やデータ以上に
フレキシブルな人材づくり、人材の確保こそ
“事業が継続する計画”には重要なのだ。