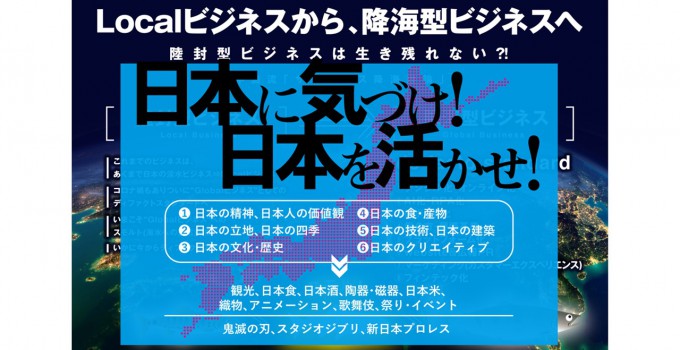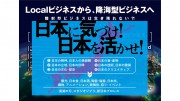09/06
2021

真夏の作業現場の救世主“空調服”
“ファン付き作業服”(空調服)をご存知だろうか。
左右の腰のあたりにファンがついていて、
ファンが廻ると風で服がふくれ、
送られた風が服の中を通り、身体の熱を首筋から逃がすしくみ。
真夏の作業現場でも涼しさを感じる画期的な商品だ。
先日NHKの“逆転人生”で紹介されたのが、
株式会社セフト研究所の空調服だ。
弊社が、ある企業の月刊情報誌を
制作していた時に、この株式会社セフト研究所を
取材させてもらったことがあり思い入れがある。
10数年前のことだ。
まだこの商品を開発してそれほど経っていない頃で、
もちろん今ほど売れていなかった。
「売れればいいですね」と言って取材を終えた覚えがあるが・・・。
(このファン付き作業服があたりまえになるのは
難しいだろうなぁ~と思っていた)
ということもあり、真夏の暑い時期に作業をしている
人たちがこの空調服を着ているのを見ると嬉しくなる。
自宅近くの作業現場でこれを着ている人がいて、
ある時、その空調服について尋ねてみたら、
「これ、一度着ると脱げませんよ」とまで言っていた。
なんだかうれしく思い写真を撮らせてもらったわけだ。
このように、私が空調服をあちこちで見るようになった
そのタイミングでNHKの「逆転人生」にとり上げられていた。
私が取材した時は、残念ながら、会長の市ヶ谷氏には
会えなかったのだが、その際に、もうひとつ自信を持って
「売れる」と言い切れていなかった理由はもしかすると
裁判を抱えていたからかも?と番組を観て思った。
取引先から特許侵害で訴えられていたという。
数年後、裁判で勝利し、多くの人たちにファンつき作業着が
拡大していったようだ。
開発に時間とお金をかけた市ヶ谷会長にとっては嬉しい事だろう。
私も経験があるが、中小企業にとって、そして
経営者にとって裁判をかかえながら
ビジネス展開をするのは本当に大変なことだ。
NHKの“逆転人生”には石坂産業の石坂社長も出演したことあるし
八木澤商店の河野社長も出演した。
石坂産業は所沢のダイオキシン問題で、地元から「出ていけ」
とまで言われたが、地元では自慢の企業へと成長した。
当時、陸前高田にあった八木澤商店は東日本大震災で
大切なもろみも建屋ごと流されたが、
たまたま釜石市の水産技術センターに預けていたのが
残っていたのだ。
そのわずかなもろみから代々続く醤油を復活させたという。
両者とも私の月刊CDやラジオ番組にも
出演してもらい“逆転劇”を語ってもらった。
企業経営をしていると、闘わねばならないことも
時にはでてくる。
そういう不遇の時代を生き抜き、
何度も何度も起き上がってくる
中小企業には、“日の目”を見てほしい。
不遇の時代を経て、空調服があちこちで認められて本当に
良かったと思う。
皆さんもあちこちの作業現場で
“空調服”を確かめてみてほしい。