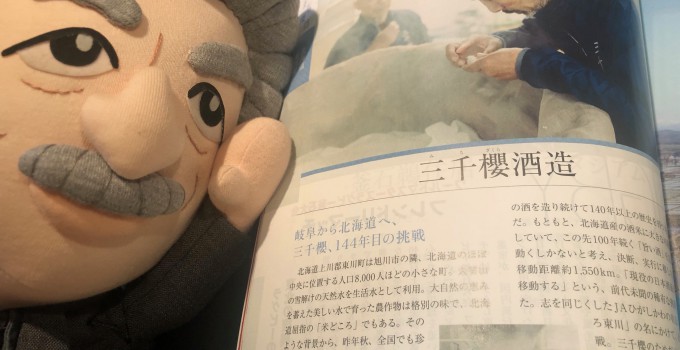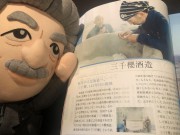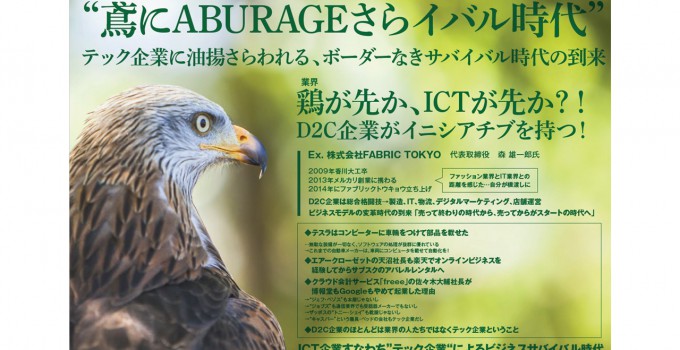05/17
2021

“ユニクロPARK”によるブランディング!
先日“ユニクロPARK”を体験してきた。
横浜の港が見える場所にある
“三井アウトレットパーク横浜ベイサイド”にある
3階建ての独立棟だ。
三角形の建屋は1階がユニクロ、2階がGU、
3階がユニクロとGUの合同のフロアで屋上が遊び場。
いや屋上はもちろんだが、三角形建屋の一辺すべてのカベが
遊び場なのだ。(写真を見てもらえば・・・)
そこには、滑り台、クライミングウォール、
トランポリン、ジャングルジムなどの遊ぶためのスペース
があり建物まるごと公園という造り。
私は祝日に行ったこともあり、大勢の子どもからその親たち
みんなが楽しんで遊んでいた。
売り上げは分からないが、これを見てる分には大繁盛状態。
さてこの“ユニクロPARK”は、建築家の藤本壮介氏が
建物の基本構想とデザイン監修をし、そして皆さんご存知の
“佐藤可士和氏”がトータルプロデューサー。
佐藤氏は2006年からユニクロの世界戦略にかかわり、
ニューヨークのソーホ地区はじめ、ロンドン、パリ、
銀座、NY五番街と旗艦店全てのクリエイティブディレクターを
務めている。
お店の売り場は1階から3階まであるのだが、
このお店の本来のコンセプトは
“PLAYプレイ”で、“わざわざ行きたくなる店”を
目指して創られている。
佐藤可士和氏は、ビジ達でも紹介した“ふじようちえん”を
プロデュースしている。
そこも“園舎自体が遊具”というコンセプトで創り、
多くの園児が楽しく通っている。
今回はユニクロの売り場をベースにしながら
建屋を遊具になぞられたというわけ。
既存のユニクロ店にない試みとして、
1階の入り口脇にはフラワーコーナーを設けてある。
一束390円、3束で990円と値段も安い。
UTの売り場も好きな写真やイラストを使い、自分でカスタマイズ
できるTシャツ やトートバックをつくれるコーナーもある。
様々なワークショップが開催され、ナーシングルームもあるという。
来る人にとっても使いやすく、居やすい場所作りをしている。
売り場に地域性、社会性を加味したデザインは、
しっかりユニクロのブランンディングにつながっているということ。
すなわち、半パブリックな店づくりをすることで、
地域の人たちにも受け入れられている。
佐藤可士和氏は、今や時代に受け入れられる“ブランド請負人”なのである。
ユニクロに携わって15年経った中での“ユニクロPARK”。
佐藤可士和氏プロデュースのもと、
確かにユニクロは世界でも認められるブランドに成長している。
この海の見える横浜の地での“ユニクロPARK”が、
そのブランドをより好印象にしてくれるのだろう。