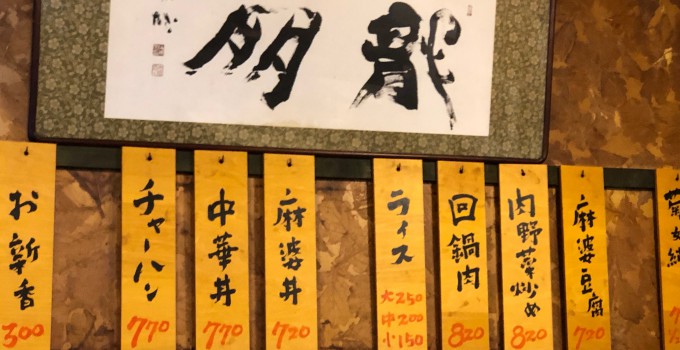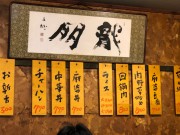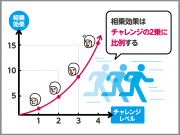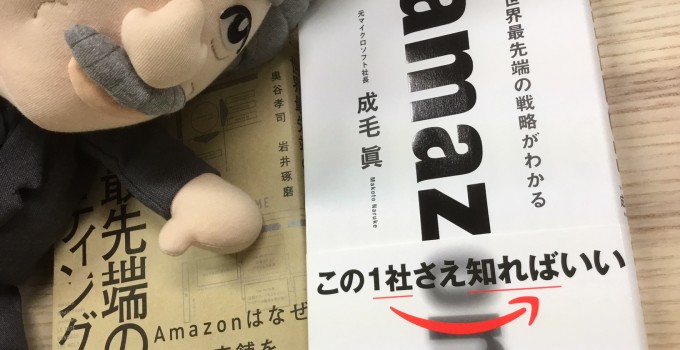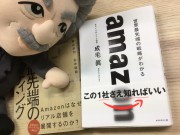02/04
2019
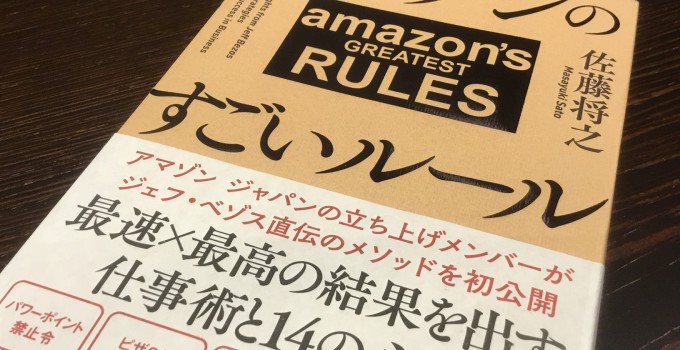
Amazon’s ルール
web通販サービス「Amazon」には・・・というよりは、
創業者の1人であるジェフ・ベゾス氏には、
いくつかの揺るがないルールがあるらしい。
その中で最も大切なものは「Customer Rule!」。
お客様第一主義!とでも訳せばいいだろうか。
すべてはお客様が決めるのだ、
という姿勢のもとに、全てが決定されるという。
他にも、社名候補にまでなった
「relentless=冷酷な、情け容赦ない」とか、
「Good intention doesn’t work/Only mechanism works
=『善意』は働かない。働くのは『仕組み』だ」などなど、
彼一流のルールがいくつもあるのだ。
Amazon立ち上げ前は金融業界の
ネットワークシステム構築をしていた、
という出身が影響しているのかもしれないが、仕組みづくりと
ルールの徹底にかける情熱が伝わってくるではないか。
数多くのフレーズの中で、私が着目したのは「OLP14か条」。
Our Leadership Principles=
私たちのリーダーシップのための理念、というもので、
リーダーだけでなく全社員が首かけストラップで
ぶら下げているというのだ。
以下にざっと紹介すると、
1.顧客へのこだわり
2.オーナーシップ
3.想像と単純化
4.多くの場合正しい(←正しくないときもある?!)
5.学び、そして興味を持つ
6.ベストな人材を確保し育てる
7.常に高い目標を掲げる
8.広い視野で考える
9.とにかく行動する
10.質素倹約
11.人々から信頼を得る
12.より深く考える
13.意見を持ち、議論を交わし、納得したら力を注ぐ
14.結果を出す
・・・という14の項目だ。
とりわけ、“2.オーナーシップ!”
平社員にまでオーナーシップを持て、
ということは、経営者のように全体の利益のために動け、ということ。
私の仕事じゃないからできませんとは言わせないのだ。
“9.とにかく行動”などは私の日頃のモットーでもあり、
はたまた“10.質素倹約”などは、まるで石田梅岩!
(まさか石田梅岩的価値観が行動指針に出てくるとは…)
創業の頃はドアに足をつけ、机代わりにしていた
というベゾス氏ならではの言葉だ。
いまや地球規模でサービスを展開する
Amazonだが、そこにはまずmechanism(仕組み)があり、
その中に従業員一人ひとりにまで浸透する理念がある。
だからこそ成長し続ける企業なのでは・・・。
そう思い、私たち中小企業の現状を振り返ると、
仕組みが不十分かも、
ルールは徹底されていないかも、と反省しきり。
私たちがAmazon’s Ruleに学ばなければならない部分も、
また沢山あるように思うのだ。