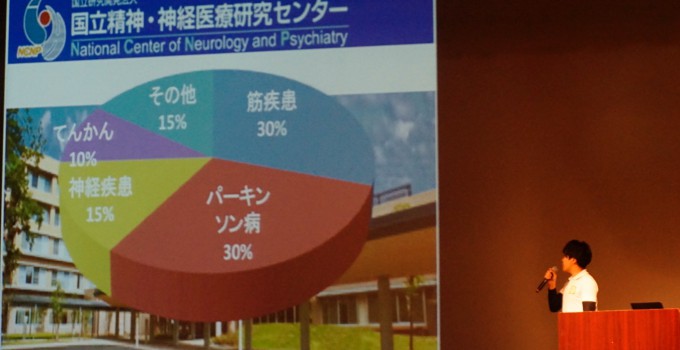07/02
2018
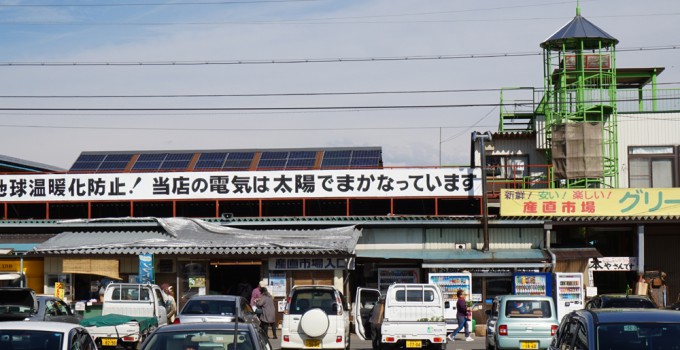
「リアルなつながり」の創出が選ばれる
以前のビジ達、
“オンラインを基点にオフラインへ”でお話したように、
オンラインの大手がリアル店舗への展開を始め、
マーケティングの革新に乗り出している。
このような状況で、リアル店舗が生き残っていくには
どうすればよいのだろうか…?
オンラインの大手が手出しできないような、
選ばれしリアル店舗を例にご紹介しよう!
たとえば、しばらく前にご紹介した、
長野県伊那市にある“産直市場グリーンファーム”。
外観はお世辞にもキレイとはいえないが、
なんと年商10億円以上の売り上げを
毎年継続している人気のマーケットなのだ!
ここではヒキガエル(買っていくお客さまがいるとは…)や
ひよこなど、通常のマーケットにはないものに出会えるという
イベント性があるのだ。
また、数か月前にご紹介した
白Tだけの専門店“#FFFFFFT(シロティ)”。
ここにも全国からお客さまが訪れ、お店の前に行列をなしている。
こだわりの白Tを購入するという目的もあるが、
豊富な知識を持ったスタッフたちとの会話を
楽しみにきているお客さまも多いという。
先日ご紹介した“秋保のおはぎ”も
まさにリアルな店舗ならではの体験がある。
このような体験・関係づくり・ワクワク感は
オンラインでは味わえないもの。
買い物に行くというより、“イベントに参加して体験を創る”って感じ。
つまり、“リアルなつながりの創出”が大切なのである。
まさにこれは、ビジ達でくり返し語ってきた
“選ばルール7”に合致しているのでは…!?
(それぞれの業務業態で選ばれるために、とことん追求しようという項目)
1.本物にこだわる
2.手間をかける
3.とことん追求する
4.必要以上のコミュニケーションを図る
5.大胆で潔い
6.積小為大の発想
7.徹底の二乗
以上の7つのルールを満たすことで、
選ばれるビジネスになるのである!
“リアルなつながりの創出”すなわち
“選ばルール7”を満たすことで、
オンラインを基軸としたリアル店舗のアプローチに
十分対抗できるのではないだろうか…!?